ー再委託研究室ー
脳における記号とパターン統合の理論と計算アーキテクチャの研究
大森 隆司
(東京農工大学 工学部 電子情報工学科)
■脳における情報統合の理解に向け#k帖!RWCPにおける東京農工大学大森研究室の研究課題は、「記号とパターンの相互変換」となっています。記号処理とパターン処理は工学的には異なる概念であり、それを統一的にまとめることは容易ではありません。しかし、人間は世の中を各種感覚で認識して、言語を使って会話しています。それなら、脳は記号もパターンも同時に扱え、統合していると考えざるを得ません。そのメカニズム・アーキテクチャ・理論を知ることは、現在の実世界でのパターン認識や知識処理に欠けている部分を明らかにして、その解決に向けての研究の方向を明らかにしてくれると考えます。
脳における記号とパターンの統合に関して、我々は以下の二つの作業仮説を持っています。一つは、脳はモダリティの異なる複数のパターン表現システムと、それらをつなぐ記号表現システムの両方を持っていて、必要に応じて情報を任意に変換することができるという二重符号化の仮説です。もう一つは、脳には順次的に働く注意システムが存在し、どの情報表現・処理システムをどういう順番で使って情報を処理するかは、その注意のシーケンスによって決まるという順次的注意の仮説です。
これらの仮説は、数理的な記号とパターンの定義という観点からも脳科学の観点からも、充分に可能性があると考えています。現在の論点は、それがいかに実現されるのか、工学的なシステムとしてどれだけ有効なのか、知能システムの理論・アーキテクチャ・設計論にどう影響するのか、という工学的な視点に移りつつあります。
■基本モデルと実用 :>二つの研究の流れ ◆脳の記憶モデルPATONの理論化
記号とパターンの統合の基本モデルとして、脳のマクロな構造に基づいた記憶モデルPATONの解析と応用の探索の研究を行っています。PATONは注意によって活動度を制御できる連想記憶モデルであり、理論的な解釈が可能な程度に単純でありながら、認識や連想等の認知行動の文脈依存性を自然に発生できるだけの機能を持っています。
現在は、PATONと従来の知能システムの計算過程の比較・解析を行い、その計算モデルの違いから脳の知的動作の理論を引き出そうとしています。また、概念記憶の文脈依存の操作ができることから、非文法的な自然言語の理解に応用できるのではないかと考え、検討しています。
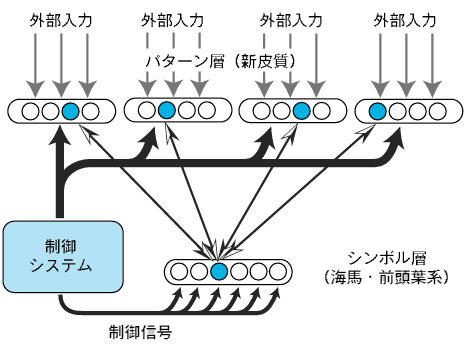
図1 PATONの構造図
◆記号とパターンの相互変換による画像理解
基本概念を実際の課題に適用して問題点を検討・抽出することを目的として、画像処理と記号処理のハイブリッドによる画像理解システムを実現しようとしています。そのシステムの鍵は、ネオコグニトロンという、画像と記号という異質の情報の相互変換を実現するニューラルネットです。
相互変換系の技術的な難しさもあって、実現された画像理解の動作はまだ未熟です。しかし、脳の情報統合についての仮説を背後に持つことにより、異質な処理システムを組合せるハイブリッドシステムの利点について理論的な説明を与え、実世界の雑多な情報や問題を処理するシステムの構築の方向が探れるのではないかと考えています。例えば、昨年11月の情報統合ワークショップで話題となった階層的な世界の記述のための言語は、実世界の多様な情報を扱うには避けて通れないわけですが、ハイブリッドシステム記述言語はその最初の課題と考えることができます。
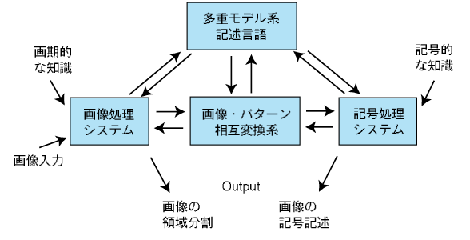
図2 ハイブリッド画像理解モデルの機能ブロック
■記号・パターン統合アーキテクチャに向け
以上、脳の視点から情報統合について考え、記憶モデルPATONとハイブリッド画像理解システムの目的について説明しました。ここからは、これらの研究から考えられる記号・パターン統合アーキテクチャについての個人的なイメージです。
まず言えることは、脳は注意と入力に駆動される状態遷移機械として解釈可能だということです。チューリングマシンもシミュレートできます。すなわち、計算機械としての脳は原点では現在の計算機と似ています。但し、実現デバイスとアーキテクチャが大幅に異なります。アーキテクチャから見ると、脳は演算と記憶が一体となった素子で構成され、演算は連想記憶の収束過程により実現されます。そのプログラムは注意というマクロレベルで記述され、ノイマン型とは異なる方式で計算を実現しているようです。さらに脳は、学習によって遷移の状態そのものが変化します。これは通常のCPUで、その構造が変化することに相当すると考えればいいのでしょうか。これだけの計算原理が分かれば、通常のシリコンデバイスでも類似の計算装置を作ることができるかもしれません。
さらにハイブリッドシステムの計算論は、注意よりもっと抽象的なレベルでの問題解決のプログラミングの可能性を示しています。現時点では、それは制約充足と考えています。脳は多くのモダリティについて現実に起こることを一般化して記憶しており、それは連想記憶の計算によってそのまま制約として使用できます。注意はそれを選んで組合せていると解釈できるのです。制約充足は、脳だけでなくプログラミング言語の方法論としても重要であるということは、情報統合ワークショップでも話のあった通りです。
以上の内容は、これまで
RWCPの「記号とパターンの統合に関するワークショップ」(通称SYMPAT)で議論されてきたものを、脳の理論に当てはめて考えたものです。記号とパターンについては多くの定義・統合の方法が考えられており、ここでの議論もまたその一つに過ぎません。その議論の延長線上に、マルチモーダルな情報統合の研究があるのだと考えています。
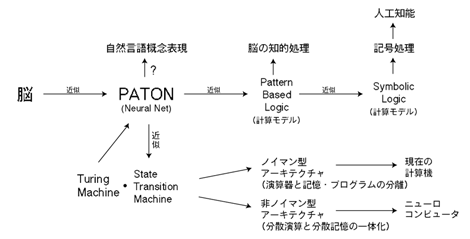
図3 悩の計算アーキテクチャと従来の理論の関係
[参考文献]
|