| (3) HEC R&D(High End Computing Research
and Development) |
HEC
R&Dでは、テラ・フロップス規模のコンピューティングを想定して、プロセッサ、メモリ、入出力装置、スイッチ等のハードウェア・コンポーネントから言語、
コンパイラ、最適化、スケジューラ、メモリ管理等のソフトウェア・コンポーネントにいたる様々な要素技術の研究が行われている。その概要は、以下のとおりである。
|
HTMT(Hybrid Technology Multithreaded)
Architecture [DARPA / NASA / NSA /
NSF]
HTMTアーキテクチャの研究は、DARPA、NASA、NSA及びNSFによって支援されている学際領域研究プロジェクトであり、RSFQ(Rapid
Single Flux
Quantum)超伝導ロジック、光通信とホログラフィック・ストレージ、プロセッサ内蔵型SRAM・DRAM等の研究を行っている。
|
| 図表1-2-1 HTMTのメモリ・アーキテクチャ |
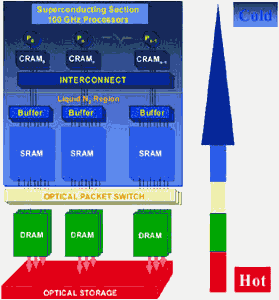
(出展: National Science and Technology
Council/Interagency WG on IT R&D) |
Beowulf: High Performance Computing with
Workstation Clusters & Linux
[NASA]
NASAが資金提供しているBeowulfプロジェクトは、ワークステーションのクラスタによって高性能コンピューティングを達成することを目指しており、Linuxベース上にソフトウェア環境を構築している。
|
Weather Forecasting in a Mixed Distributed
Shared Memory Environment [NOAA]
NOAAの支援により、Message Passing
Interface(MPI)ベースの気象予測コードをベースとして、次世代の混合・分散・共有メモリ型コンピューティング・システムにおいて利用される効率的プログラミング・モデルの研究が行われている。
|
MVICH-MPI for Virtual Interface
Architecture [NERSC]
MVICHは、DOEのNERSC(National Energy Research
Supercomputer Center)が資金提供するプロジェクトで、Message Passing Interface(MPI)をVirtual
Interface Architecture
(VIA)に適用することによって、クラスタ・コンピューティング向けのポータプルな高性能通信を実現するものである。
|
DPSS(Distributed-Parallel Storage System)
[MAGIC]
DPSSは、低コストの商用ハードウェア・コンポーネントからハイエンドのストレージ・システムを構築するために、拡張性のある高性能分散・並列アーキテクチャとデータ・ハンドリングを実現するものである。また、DARPAの資金提供を受けたMAGIC(Multidimensional
Applications and Gigabit Internetwork
Consortium)テストベッドは、DOEの支援も受けて開発が行われている。
|
Globus [ANL /
USC]
Globusは、DARPA、DOE及びNSFの資金提供を受けて、DOEのANL (Argonne National
Laboratory)とUSC(University of Southern California)のISI(Information
Sciences
Institute)が行っている共同プロジェクトである。Globusは、地理的に分散した数十から数百に及ぶ装置、ディスプレイ及び計算・情報リソースを統合するアプリケーションを可能とするための環境を構築する基盤技術の開発を行っている。
世界各地の40以上の機関がGUSTO(Globus Ubiquitous Supercomputing Testbed
Organization)に参加して、Globusコンセプトの検証を行っている。
|
SF Express(Synthetic Forces Express)
[CalTech]
SF Expressは、CalTech(California Institute of
Technology)によって行なわれているGlobus
を用いて、複数のスーパーコンピュータ・リソースにアクセスし、大規模シミュレーションを行うプロジェクトである。このプロジェクトは、7つのタイム・ゾーンにまたがる9つのサイトの13のコンピュータの1,386のプロセッサ上で、記録的な大規模分散処理型のシミュレーションを行った。
|
Legion: A Worldwide Virtual Computer
[University of
Virginia]
Legionは、膨大な数のホストとオブジェクトを高速リンクで結合させるためのオブジェクトベースの巨大システム・ソフトウェアを開発するプロジェクトであり、University
of VirginiaがDODのNAVO(Naval Oceanographic
Office)、NSF及びDOEの資金提供を受けて行なっている。Legionは、現在たんぱく質の重なりなどの分子の力学・構造を研究するCHARMM(Chemistry
at Harvard Molecular Mechanics)、 気化物質の堆積を研究するUniversity of
VirginiaのDSMC(Direct Simulation - Monte
Carlo)、及び多数のモデルを結合させた気象モデルなどに試験的に適用されている。
|
Java Numerics [NIST /
JGF]
NISTは、JGF(Java Grande
Forum)と協力して、高性能ネットワーク・コンピューティングにJavaを活用するため、Java環境において科学用アプリケーションに対応できる高信頼性で再利用可能な数値ソフトウェア・コンポーネントを開発している。
|
先進的ハードウェア・コンポーネントの研究
|
連邦政府は、ハードウェア・コンポーネント・レベルでのブレークスルーを実現するため、半導体ベース以外でのアプローチとして、以下のような研究プロジェクトを進めている。(上述のHTMTもその一つである。)
|
VLSI(Very Large-Scale Integration)
Photonics Program [DARPA]
DARPAのVLSI
Photonics計画では、チップ間の信号伝送に光を利用するための基礎技術の研究が行われている。
|
Quantum Computing
[NSA]
NSAは、光量子を用いた量子コンピューティングの研究を行なっており、また量子ドットやジョセフソン接合、シリコン結晶に埋め込まれた核スピンなどを用いる研究も支援している。2000年度には、大学と政府の研究所によるコンソーシアムにおいて、拡張性のあるシリコン・ベースの核スピン量子コンピュータの概念が研究された。
|
Quantum Phase Data Storage and Retrieval
[University of Michigan]
University of
Michiganでは、NSFの資金を得て、セシウム原子を用いて原子の量子フェーズがデータベースに利用できるかどうかを研究している。
|
Quantum Information and Computation
[CalTech / MIT / USC]
CalTech(California Institute of
Technology)、MIT(Massachusetts Institute of Technology)及びUSC(University of
South
California)は、DARPAの資金提供を受けて、量子状態において、情報を蓄積・処理できるデバイスの研究に取り組んでいる。
|
EQC(Ensemble Quantum Computer)-NMR(Nuclear
Magnetic Resonance)
[DARPA]
DARPAは、量子コンピュータを実現するために、核磁気共鳴による分光分析技術を利用する研究を行っている。
|
DNA Data Storage [Duke University
etc.]
デューク大学が率いる9組織から成るコンソーシアムは、DARPAとNSFの資金により、DNA組換え技術を活用してDNAに情報を蓄積する技術の研究を行っている。
|
Advanced Microscopy Tools for IC
Development [NSA]
NSAは、LEEM(Low Energy Electron Microscopy)やPEEM
(Photo Emission Electron
Microscopy)を活用して、半導体の表面状態や内部構造を成製・分析・加工する研究を行っている。
|
3-D Diamond MCM(Multichip Module) Cube
Computer [NSA /
DARPA]
NSAとDARPAによって、エアゾル・スプレーで冷却されたダイアモンドのマルチ・チップ・モジュールを三次元的に結合させたナノ秒レベルのコンピュータが開発され、2000年度にデモンストレーションが行われた。
|
Optical Tape [NSA / NASA /
DOE]
NSA、NASA及びDOEは、大容量で既存のシステムとある程度互換性のある書き換え可能な記憶媒体として、光テープの研究に資金を提供している。
|
Superconducting Electronics
[NSA]
NSAは、超伝導エレクトロニクス研究の一環として、128×128の超伝導クロスバー・スイッチの開発やサブ・ナノ秒のメモリの開発を行っている。
|
Smart Memories
[NSA]
NSAは、スマート・メモリの研究として、様々なアプリケーション向けに開発された既存のアーキテクチャからのエミュレーションやチップ上でのネットワーク結合アーキテクチャの検討など、基本アーキテクチャの研究を行っている。
|
Vendor Partnerships
[NSA]
NSAは、米国におけるスーパーコンピューティング・システムの開発を支援するため、SGI(Silicon
Graphics, Inc.)/Cray社のSV2の開発に協力している。また、NSAはCompaq/DEC(Digital Equipment
Corporation) 社及びSun Microsystems, Inc.社とも協力しており、 DOEとNRO(National
Reconnaissance Office)が要求仕様の策定と評価に参加している。
|
Molecular Electronics
[DARPA]
DARPAは、分子エレクトロニクスを用いてより小型で高機能で高速で動作温度が広く三次元アーキテクチャに向いているデバイスを実現するため、複数の分子やナノ粒子を拡張性のある機能的な電子デバイスと統合する研究を行っている。
|
Nanocrystal Devices
[NSF]
NSFは、電子スイッチやストレージ・デバイスへの適用が期待されるナノ結晶及びナノ結晶アレイ・デバイスを開発するため、ナノ結晶薄膜の合成技術の開発や他の材料とのインタフェースの最適化を行っている。
|