2. NGI計画
97年度、すなわち97年10月から開始されたNGIであるが、正式な実行計画(インプリメンテーション・プラン)ができたのは、98年2月である。このドキュメントには、2002年までの本計画の詳細が各機関毎の目標も含めて記載されている。ここでは、その要旨を述べることにする。
1) 目標
本計画の目標としては、次の3つが挙げられており、それぞれがいくつかに細分されている。
第1の目標は、「先端ネットワーク技術の試験研究」であり、主要なタスクとして、現行のインターネットの100倍以上も高速かつ複雑なネットワークを効率よく管理するための「ネットワーク・グロース・エンジニアリング(Network
Growth Engineering)」、IPv6(Internet Protocol version 6)やRSVP(Resource Reservation
Protocol)などの新しいプロトコルの試験運用を行う。試験運用と併せて、通信の品質(帯域、遅延など)を保証する「エンド・ツー・エンド・クオリティ・オブ・サービス(End-to-End
Quality of
Service(QoS))」や、パブリック・キー・インフラストラクチャー(PKI)をベースとした暗号技術を中心とする「セキュリティー」という分野の技術開発が掲げられている。
第2の目標は、「次世代ネットワークのテストベッド」であり、2つの段階に分かれている。第1段階は「ハイ・パフォーマンス・コネクティビティ」と呼ばれ、現行インターネットの100倍以上(具体的にはend-to-endで100Mbps)で少なくとも100以上の大学や国立研究所等を結ぼうというもの(なお、97年における連邦研究機関や大学の平均のスピードは1.54Mbpsと推定されている)。そして、第2段階は「次世代ネットワーク技術及びウルトラハイ・パフォーマンス・コネクティビティ」となっており、超高速でのスイッチングやトランスミッションの技術開発を行うとともに、現行インターネットの1000倍以上のパフォーマンス、すなわちend-to-endで1Gbps以上の速度で、10程度のサイトを結ぼうとするもの。
第3の目標は、「革新的アプリケーション」で、第1、第2の目標が達成された次世代のネットトワークを必要とするような革新的な応用例を開発し、テストすることにある。候補としてはデジタル・ライブラリー、遠隔手術、環境モニタリング、危機管理、生産、基礎科学及び連邦政府の情報サービスなどが挙げられている。
2) リソースと具体的な実行計画
NGI参加連邦機関は、DARPA、DOE、NASA、NSF、NIST、NLM/NIHの6機関である。それぞれの機関が、上述の目標の細目それぞれについて、自らの既存プログラムとの関わりと具体的な開発計画等を説明しているが、それぞれの機関の特色は以下の通りである。
第1の目標であるネットワーク技術については、DARPAがインターネットのパイオニアとしての実績と最大の予算をもって、実質的なリーダーとなっている。DARPAでは、従来より防衛というミッション・クリティカルなアプリケーションの通信に適したネットワーク技術の開発のため、品質保証のQoS技術を中心に据えた「Quorum」と呼ばれる計画を進めており、これが第1の目標の下敷きとなっている。DOEは、DODと同じように独自の研究ネットワークを有し、核研究などミッション・ドリヴンのアプリケーションに強いことから、ネットワーク技術ではDARPAと並び、全般に及ぶ研究を行っている。NASAもDOD、DOE程の予算規模はないが、独自の研究ネットワークを有し、航空宇宙というミッション・ドリヴンのアプリケーションとシステム・エンジニアリングに強いという面では、両省と類似している。NASAの研究分野も全般にわたっており、ネットワーク・パフォーマンス測定、ネットワーク・インターオペラビリティスケーリング、QoS、ネットワーク・セキュリティ等に注力するとしている。
NSFは、学界との緊密な関係を有し、既にvBNS(Very
High Speed Backbone Network
Service)という第2目標の前段階のベースとなるネットワークを運営していることから、他の省庁とはやや性格を異にしている。vBNSは、既に5つのスーパーコンピュータ・センターとそのパートナーである(Partnerships
for Advanced Computational Infrastructure,
PACI)の一環として実施されており、NSF傘下のNLANR(National Laboratory for Applied Networking
Research)や多くの助成金を与えている大学や民間の研究所の間をつないでおり、広範囲のネットワーク技術の研究が成されている。ATM(Asynchronous
Transfer
Mode)上のIPv6も近く導入されることになっており、第1の目標に完全に沿った技術の研究が既に進められていると言える。残るNISTは、従来より例えばIPv6の開発やテストへの参画や、ATMプロトコールのシミュレータの開発など、評価試験技術等に力を発揮してきている。また、暗号の分野ではPKIの確立などでも中心的な役割を果たしてきており、これらの分野で第1の目標達成に貢献する。
第2の目標の第1段階におけるリーダーは、NSFである。それは、すなわちvBNSが100倍のパフォーマンスのネットワーク・テストベッドのベースとなると言うことである。vBNSは、98年度中には100を超える大学/研究所をつなぎ、その接続速度もDS3(45Mbps)のところはOC-3(155Mbps)にアップグレードしていく(バックボーンは既にOC-12(622Mbps)がほとんど)。続いて、第1目標や第3目標で開発された技術やアプリケーションをとり入れていくという形を取る。NASA、DOD及びDOEは、それぞれのネットワーク(図表・-1参照)のアップグレードを行いつつ、ワシントン、シカゴ、シリコンバレーの3カ所にNGIエクスチェンジ(NGIX)を設置し、vBNSや他のネットワークとの接続を行っていく。
第2目標の第2段階である1000倍のパフォーマンスのネットワークについては、まだ明確なベースがあるわけではないが、DARPAが首都圏で始めようとしている5つのノードをWDM技術により20Gbpsでつなごうとしている計画がベースの一つとなる。NSFは、サン・ディエゴ・スーパーコンピュータ・センター(SDSC)とナショナル・センター・フォー・スーパーコンピューティング・アプリケーションズ(NCSA、イリノイ州)との接続を端緒とする。NASAは、少なくとも2カ所のNASAサイトをDARPAの高速テストベッドに接続していく。
第3の目標である革新的アプリケーションの開発については、その候補が多数存在することから、選定プロセスなどが詳細に規定されている。開発に参画しテストすることができる機関は、NGIファンドを受けている上述の機関の他、NGIに密接な関係を有する政府系研究機関に原則限られており、かつアプリケーション開発予算は第1目標や第2目標の技術開発に大きな寄与があるもの以外は、NGIファンドからではなく、それぞれの機関での手当が求められている。国家安全保障のためのDODのアプリケーション及び航空宇宙エンジニアリングのためのNASAのアプリケーションという単一機関にのみ関係し、国家として不可欠であるもの以外は、専門分野別並びに技術分野別(専門分野横断的)に関連グループを組織して、アプリケーションの選定や開発に、協力して当たることとされている。
それぞれの関連グループの参加機関と候補とされるアプリケーションは、以下のようになっている。
| (専門分野別関連グループ) |
| (1) |
健康:NIH、AHCPR、NASA;画像情報の通信を含む遠隔医療、患者情報を含むマルチメディア・ライブラリー、遠隔操作/診断のためのテレプレゼンス・アプリケーション |
| (2) |
環境:NASA、NSF、NOAA、EPA、DOL、USDA;気象予報協力、チェサピーク湾バーチャル環境、中規模気象研究のための分散モデル研究所、リアルタイム環境データ交換 |
| (3) |
教育:DOED、NASA、NSF;遠隔学習、ユニバーサル・アクセス |
| (4) |
生産:NIST、NASA:昆虫型マシンの遠隔アクセスとシミュレーション、走査顕微鏡の遠隔ロボット操作 |
| (5) |
危機管理:FEMA、NOAA、NASA、DOD/DARPA、USGS、DOL、CEOS、G-7/GEMINI、GDIN、NOAA/NESDIS;危機状況(自然災害を含む)下での協力、危機状況下でのデータ・アクセスと拡散、セキュリティーとプライバシーの政策と執行、危機状況下での誘導コンピューティングとネットワーク管理 |
| (6) |
基礎科学:NSF、NOAA、NASA、NCRR;基礎的な科学と関連する現象を洞察するのに寄与するようなアプリケーション(今後グループとして検討) |
| (7) |
連邦情報サービス:各機関;アーカイブ情報へのアクセス、情報統合、データ・マイニング、電子商取引 |
| |
| (技術分野別関連グループ) |
| (1) |
協同技術:NIST、NASA;(例)ネットワークベースのビデオコンファレンス、データベース共有 |
| (2) |
分散コンピューティング技術:NSF、NASA |
| (3) |
ディジタル・ライブラリー技術:NSF、NASA、NIH |
| (4) |
遠隔操作技術:NIST、NASA、NIH、NSF;(例)反作用感応型の遠隔手術 |
| (5) |
セキュリティー/プライバシー技術:NIST、NASA |
3) タイムライン
上述の目標を達成していくタイムラインの全体をまとめると、以下のようになっている。示された年は、それぞれの目標が最初に達成されるはずの年を示している。
| (1) |
100以上のサイトをOC-12(644Mbps)のインフラストラクチャー上でOC-3(155Mbps)
によりつないだハイパフォーマンスのテストベッド -----------------------------------
1999年 |
| (2) |
連邦政府、アカデミー、産業界のパートナーシップにより100倍速テストベッド上での
アプリケーション/ネットワーキングの研究開始 --------------------------------------
1999年 |
| (3) |
10以上のサイトをOC-48(2.5Gbps)でつないだウルトラハイパフォーマンスのテスト
ベッド ----------------------------------------------------------------------------------------------
2000年 |
| (4) |
1000倍速テストベッド上でのアプリケーション/ネットワーキングの研究 ---- 2001年 |
| (5) |
NGIプロトコール、マネージメント・ツール、QoS提供、セキュリティ、高度サービス
のためのテストベッド・モデル -------------------------------------------------------------
2000年 |
| (6) |
ハイパフォーマンス・テストベッド上での100以上の高度アプリケーションの実験(例
えば、選ばれた研究所による遠隔・実時間・協動NGIネットワーク・コントロール) -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000年 |
| (7) |
様々な技術やキャリアへのQoSの統合 --------------------------------------------------- 2001年 |
| (8) |
テラビット/秒でのパケット交換のデモンストレーション -------------------------- 2002年 |
| (9) |
ウルトラハイパフォーマンス・テストベッド上での10以上の高度アプリケーションの実
験 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000年 |
4) 予算
図表III-1 NGI予算(単位: 100万ドル)
| 連邦機関 |
FY1998 |
FY1999 |
FY2000要求 |
| DOD/DARPA |
42 |
50 |
40(TBD) |
| NSF |
23 |
25 |
25 |
| DOE |
- |
15 |
15 |
| NASA |
10 |
10 |
10 |
| NIST |
5 |
5 |
5 |
| NLM/NIH |
5 |
5 |
5 |
| Total |
85 |
110 |
100 |
なお、98年10月に成立したNGI法は2000年度までの時限立法であり、2001年度以降の予算や計画については、別の法律が必要になる。そこで「NGI2000法案」が既に提出されて審議されているが、それについては第4章で述べる。
5) 最新の状況
NGIのテストベッドの目標として、(Goal2.1)100以上のサイトをエンド・ツー・エンドでOC-3(155Mbps)(すなわち97年時点のインターネットの速度(平均1.54Mbps)の100倍以上)で結ぶ(99年度まで)、(Goal2.2)10以上のサイトをOC-48(2.5Gbps)(同1000倍以上)で結ぶ(2000年度まで)、という2段階があるが、DARPAはこのGoal2.2のテストベッドとして、SuperNetを提供しているのである。因みに、Goal2.1のベースとなっているNSFのvBNS(http://www.vbns.net/)は、2000年3月段階で101の大学・研究所が接続されており(別に37が接続準備中)、速度も大半がOC-3としているので、目標はほぼ達成されたということになる。OC-48の接続も、マップに示されているように、99年1月にロサンゼルスとサンフランシスコ間で実現している。なお、vBNSに接続する大学・研究所は、99年3月時点で一時150に上ったのだが、NSFが大学等に対して、98年12月、vBNSから後述するインターネット2のバックボーンであるAbileneに乗り替えても助成を継続するとアナウンスしたため、乗り換えたところもあって、少し数が減っている。
図表III-2 vBNSバックボーン・ネットワークのマップ
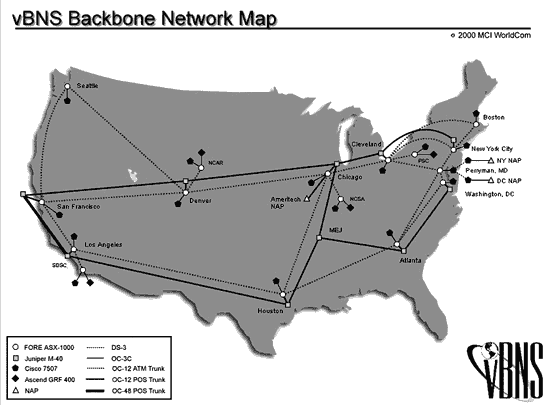 |
SuperNet(http://www.ngi-supernet.org/)は、図表III-3のように、
| (1) |
西海岸をOC-192(10Gbps)で結ぶNTON(National Transparent Optical Network) |
| (2) |
東西をエンド・ツー・エンド2.5Gbpsで結ぶためのHSCC (High Speed Connectivity
Consortium) |
| (3) |
ボストン・エリアで主にWDM(光波長多重技術)の実験を行っているONRAMP(OpticalNetwork for Regional
Access with Multi-wavelength Protocols) |
| (4) |
ボストンとワシントンD.C.を結ぶBOSSNET 、 |
| (5) |
首都圏でDARPA、NASA、NSAなどを 20 Gbpsで結ぶATDNET (Advanced Technology
Demonstration Network)
|
という5つの要素で成り立つものである。その進捗状況を示す好例として、この99年11月にSC99の会場で一つのデモが行われた。それは、NTONを用い、シアトルのマイクロソフト社とワシントン大学が、ポートランドのSC99の会場に向けて、HDTV放送を送ると言うものであった。ソニーの協力を得て行われたこのデモでは、スタジオ品質のHDTV5チャンネルを同時に送ると言うもので、約1Gbpsが使われたが、通常のTV放送では150チャンネル分、放送品質のHDTVでは50チャンネル分に相当すると言う。他のアプリケーションも同時に動かして、全体としては2Gbps以上のスループットを確認している。もちろんマイクロソフトは、これをウィンドウズ2000のワークステーション間で行えると、しっかり宣伝を忘れてはいない。以上述べたように、NGIのGoal2.2に向けての努力も着実に実りつつあると言うことのようである。
NGIのGoal3である革新的アプリケーションと言うことで、NIHを99年11月に訪問した際に聞いたことを付け加えておきたい。NIH(NIHの一部であるNational
Library of Medicine =
NLMを含む)は、以前、HuCSのチャンピオンであったのだが、今やLSN/NGIのアプリケーションのチャンピオンとなっており、大きく、Co-Laboratory、Telemedicine、Large
Database
Accessの3つの研究を行っているとのこと。遠隔医療については、4~5年前から本格化しているが、実現のレベルに達しつつあり、アイルランドとヨルダンの癌センターとネットワークで接続し、例えばX線やCTスキャン画像を送ったり、電子顕微鏡の遠隔操作を行ったりなどができるようになっていると言う。また、NLMではデジタル・ライブラリーのプロジェクトの中で、Medical
Informatics計画を進めており、医療関連のナレッジソースの利用や人のゲノム情報、あるいは個人のカルテに至るまで、大量の情報へのアクセスを可能にする研究を行っている。
|