2. ASCI計画
1996年9月、クリントン大統領は包括的核実験禁止条約(Comprehensive Test Ban Treaty
;CTBT)に署名する最初の世界リーダーとなった。当該条約の結果、DOEは、実際の核実験に依存せず、しかし、核兵器備蓄の安全性、性能及び信頼性を確証する「核兵器備蓄保全の責任と管理(Stockpile
Stewardship and Management Program
;SSMP)」のデザイン設定を要求されることになった。同時に、米国は核兵器のデザインを中止し、その兵器製造インフラストラクチャーを削減することを決定したことから、米国の核兵器の備蓄は、実験またはその伝統的な製造支援システム無しに、デザイン上の有効期間を遥かに越えてその保全をしなければならないことになったのである。
実際の実験を代替するため、DOEは、SSMPの構成要素の一つとして設定したのが、「加速的戦略コンピューティング・イニシアティブ(Accelerated
Strategic Computing Initiative
;ASCI)」である。ASCIのビジョンは、「米国の備蓄核兵器の安全性・信頼性及び性能を確保するために、最先端のコンピュテーショナルなモデリングとシミュレーションの能力を創造し、核兵器の実際の実験ベースからコンピューテーショナル・ベースの手法に、できるだけ早く移行する。」という点にある。ASCIが、2010年までに達成すべき目標は以下の通りである。
| i) |
性能: 実際の核実験のない環境でその挙動を分析し、性能を評価するため、核兵器の予測可能シミュレーションを創生する。 |
| ii) |
安全: 複雑な事故シナリオにおける安全な核兵器システムの行動について、高精度な予測を行う。 |
| iii) |
信頼:
核兵器備蓄の有効期間を延長するため、十分かつ認証された予測能力を達成し、かつ故障のあるメカニズムを予測し、ルーティンな維持管理を削減する。 |
| iv) |
再生:
備蓄兵器の再整備及び代替の作業のための製造と実験施設を減少するため、仮想プロトタイピングを用いる。 |
ASCIは、DOE傘下のローレンス・リバモア、ロス・アラモス、サンディアの3国立研究所が一体となって進めるという戦略をとっており、ユタ大学、スタンフォード大学、シカゴ大学、カリフォルニア工科大学、イリノイ大学の各大学と共同で当たっている。その研究のためのプラットフォームとして使われるスーパーコンピュータ自体の開発も、計画発足当初の95年から5つの段階を設定して開始されているが、このプラットフォームの委託開発の部分に「パスフォワード(PathForward)計画」(http://www.llnl.gov/asci-pathforward)という名称が与えられている。
96年12月に、パスフォワード計画への関心表明のリクエスト(REI)という文書が、米国のコンピュータ業界に向けて、DOEから出されている。併せて、パスフォワード計画の詳細という文書も出されており、その文書に全体の計画が記述されている。そこに示されている開発のロードマップを大まかに読み取ると、以下のように整理されるが、最終的な目標は2004年までに100Teraflopsを達成すると言うこところにある。
ASCIコンピューティング・プラットフォームのロードマップ(96年12月発表)
|
計画段階 開発段階 実用段階 |
|
| 第1段階(1+ Tflop / 0.5TB) |
95初 ~ 95半 ~ 96末 ~ 99初 |
(レッド) |
| 第2段階(3+ Tflop / 1.5TB) |
96初 ~ 96半 ~ 98半 ~ 00半 |
(ブルー) |
| 第3段階(10+ Tflop / 5TB) |
97初 ~ 98初 ~ 00初 ~ 02半 |
(ホワイト) |
| 第4段階(30+ Tflop / 10TB) |
98末 ~ 99半 ~ 01半 ~ 03半 |
~ |
| 第5段階(100+ Tflop / 30TB) |
00初 ~ 00末 ~ 03半 ~ |
|
図表・-1 ASCI計画のロードマップ
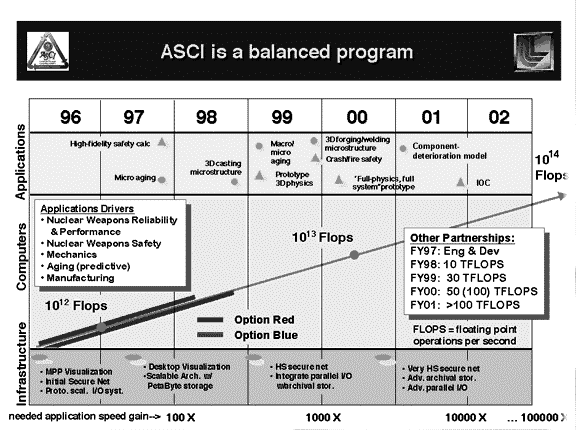 |
まず、95年にスタートした第1段階のオプション・レッドは、インテルが受託し、1.8Teraflopsのマシンが96年10月にサ塔fィア国立研究所に納められている。その後、99年9月にアップグレードが完了して、3Teraflopsを超えてブルーと同等のパフォーマンスのマシンに生まれ変わっている。オリジナルのレッドは、Pentium
Pro 200Mhz(キャッシュメモリ256KB)を9,072個使っていたが、これを Pentium・ Xeon
333MHz(同512KB)に置き替え、さらに594GbytesのシステムRAMを倍にすることで、アップグレードが行われた。オリジナルの開発費が約5,500万ドルであったところ、その15%増しの費用で、これを達成したと言われ、現在稼動中である。
第2段階のオプション・ブルーは、96年にIBMとクレイが受託し、96年中にそれぞれローレンス・リバモアとロス・アラモスに導入されているが、アップグレードが続けられ、98年10月と11月にそれぞれがピーク性能で3Teraflops以上を達成したと発表された。IBM機はブルー・パシフィック、クレイ機はブルー・マウンテンというコード・ネームで呼ばれているものである。ブルーパシフィックについては、10月28日、ローレンス・リバモア研究所で、ブルーパシフィック導入1周年の記念行事があり、続けてきたアップグレードの完了を発表した。その結果、ピーク性能では3.9Teraflopsを達成したと言う。
第3段階のオプション・ホワイトの開発については、98年2月にロス・アラモスを訪問したクリントン大統領自ら、パスフォワード計画を初めて一般に向けて公表するとともに、その要素技術開発(4年間で5,000万ドル)の契約をDEC、IBM、サン・マイクロシステムズ、シリコン・グラフィックス(クレイ・コンピュータ・システムズの親会社)の4社と結んだとの発表を行った。さらに、同月、DOEはオプション・ホワイトの本体の開発を8,500万ドルでIBMと契約したと発表した。現在は、2000年6月にローレンス・リバモア研究所に導入することを目指し、IBMのポケプシ(ニューヨーク州)の研究施設で組立て中である。ホワイトは、ブルーパシフィックが32ビットのPowerPC
604Eチップを5,856個使っていたのに対し、64ビットで銅配線のPower3-・チップを8,192個使う。さらに、計算そのものより全体のパフォーマンスに影響するようになっているデータのやり取り(スイッチング)の速度が、現行の150Megabytes/secからコード名「Colony」と呼ばれる500Megabytes/secの技術に変更されることで、10Teraflopsが実現できると言う。このホワイトを導入するローレンス・リバモア研究所の新451ビルディング(http://www.llnl.gov/asci-scrapbook)は完成しており、既に99年7月から「Baby
Huey」と名付けられたホワイトのプロトタイプ機が稼動中である。Baby
Hueyは、16個のNightHawkと呼ばれるノードからなる114Gigaflopsの性能を持つ機種で、10月には上述のColonyスイッチングを導入して、ホワイトのハード及びソフトの評価を開始している。
さて、ホワイトの次が何色になるのかはわからないが、ASCIプラットフォームの第4段階の30Telaflops機(とりあえず「T30」と呼ばれているらしい)のRFP(Request
for
Proposal)(http://www.acl.lanl.gov/30TeraOpRFP)が99年5月にロスアラモス研究所から出されている。基本的には、2001年6月30日までに、30Teraflops
のハードウェアをロスアラモスに納入することを求めるものであるが、もし時期が2002年1月31日までずれ込む場合は、最終マシンは35Teraflopsとし、2000年12月31日までに中間マシンとして10Teraflopsのものを納めておく必要がある。さらに、時期が2002年4月30日になる場合は、最終マシンは40Teraflopsとし、中間マシンは13Teraflopsである必要がある。さて、この公募は99年9月29日に提案書の締切りが設定されていたが、2000年3月の段階でも、どの企業がこの提案を出し、どの企業が契約を受けることになるのかかは明らかにされていないようである。ただ、報道などによると、SGI/クレイとサンが応募していることは確認されており、コンパックも出しているようである。SGIは、従来のSGI製チップのMIPSとOSのIRIXの組み合わせではなく、インテルのIA-64チップとLINUXの組み合わせを考えているようである。また、サンは、もともとクレイから技術導入をしたE10000コンピュータの64プロセッサのものをベースにして、次期チップであるUltraSparc-・に置き替えることで、30Teraflopsを達成できる見込みと言う。
さて、ホワイトを製作中のIBMであるが、T30には、応札していないようである。その理由として、IBMは独自のスーパーコンピュータ開発に専念するためとされている。現に、99年12月6日、IBMは、1億ドルをかけて独自のペタフロップス機を開発するとのプレス発表を行っている。このマシンは、「Blue
Gene(遺伝子の意味)」と呼ばれ、5年以内の完成を目指し、たんぱく質の折り畳み構造の解析を主要な目標に掲げている。構造としては、1Gigaflopsのプロセッサ32個を1つのチップ上に搭載し(32Gigaflopas)、そのチップ64個を一つのボードに載せ(2Teraflops)、そのボード8枚を一つのラックに納め(16Teraflops)、そのラック64基をリンクさせる(1Petaflops)。アーキテクチャーの特徴としては、できるだけ切り詰めたインストラクションのみを用い、マッシブ・パラレル・システムを今日の最大5千threadsから8百万threadsに拡張し、自己修復能力を持たせるという「SMASH(Simple,
Many and Self-Healing)」アプローチをとる。
なお、10月中旬に、上院が核実験禁止条約(Comprehensive Test Ban
Treaty =
CTBT)の批准を否決したが、これに対して大統領が「米国は核実験の一時停止を継続する」との声明を発表していることから、DOEとしては核兵器保全管理計画(SSMP)(ASCIはこの一部)は、ほとんど影響を受けないと言及している。
|