光インターコネクション技術の開発
並列分散システムアーキテクチャつくば研究室
工藤 知宏 |
■光インターコネクション技術サブ領域の開発計画の概観
光インターコネクション技術サブ領域は、シームレス並列分散コンピューティング技術領域の一部であり、シームレス並列分散コンピューティングに必要な光インターコネクション技術の開発を行うことを目的としています。従来の光技術のように長距離の伝送をターゲットとしているのではなく、比較的近い、計算機の世界で言えばローカルエリアと呼ばれるような範囲か、あるいはそれよりも狭い範囲に分散した計算機などの間をつなぐことを想定した光インターコネクション技術の開発を行っています。
この領域の一つ目の柱は、高速伝送技術と、これを実用に供するための高バンド幅、低レンテイシなネットワークの実装技術の開発で、1999年度までに基礎技術の開発を行うことになっています。もう一つの柱として、更にこのプロジェクト全体が終わった後で使える、将来のシームレス並列分散コンピューティングで使う光技術の開発があります。従って大きく分けて、このプロジェクトの中で使っていく技術開発、それから将来のシームレス並列分散コンピューティングで使われるであろう技術開発という二つに分かれる形になるかと思います。これを図で表しますと、図1のようになります。シームレスの方では、2001年までに5Gbpsから10Gbpsクラスのインターコネクションを使ったシステムを実際に作って、これを最終のデモシステムにしていくという想定でおります。このために、光領域の方で高速、高密度なインターコネクションモジュールや、高速モジュールと電気回路のインタフェース技術の開発を行います。更に、将来のシームレス並列分散コンピューティングのために低消費電力化とか、波長多重といったような様々な技術開発を行っていく計画になっています。
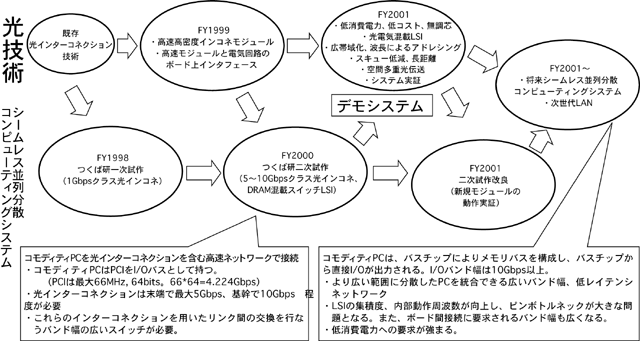
図1.光インターコネクション技術サブ領域・技術計画
■
各研究室の平成9年度の研究成果
光インターコネクション技術サブ領域は、各企業の8つの研究室から成りたっています。ここでは、各研究室の平成9年度研究成果について、簡単に概要を紹介させていただきます。私自身は、光技術の専門家ではありませんので、お話する内容や図は各研究室でご用意いただいたものです。
1)光インターコネクション日立研究室
光インターコネクション日立研究室では、日立版の光RWC-1を開発しました。これは、実際の超並列計算機のボード上に光インターコネクションモジュールを実装したもので、光インターコネクションの実証試験を目的としています。図2がそのボードです。光インターコネクションのモジュールが載っており、これによってボード間が接続されています。一つのボード上に4つのノードが載り、全体で8ノードの並列計算機が光インターコネクションでつながれるという構成です。RWC-1のような超並列計算機の中のインターコネクションに光技術を使う利点としては、光を使うことによって、レイアウトのフレキシビリティが出てくることが挙げられます。電線でつなぐと最大長がせいぜい10mだったものが、100mまで距離が伸ばせるようになります。また、電気信号で伝送する距離を短くすることができますので、LSIピンボトルネックを緩和することができます。さらにケーブルやコネクタについても、電気信号に比べて少ない面積で実装することができます。日立研究室では、この他に高い温度特性を持つ高効率面発光レーザ(VCSEL)の開発を行っています。
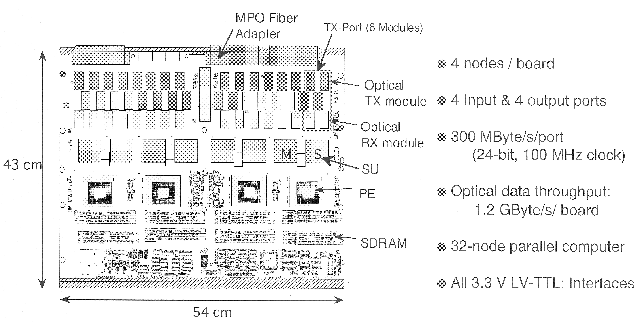
図2.光インターコネクション日立研究室
ー日立版光RWC-1プロセッサボード-
2)光インターコネクションNEC研究室
光インターコネクションNEC研究室でも日立研究室と同様に、光RWC-1の実装評価を行っています。また、将来につながる技術として長波長レーザ材料の開発が行われています。図3(a)がNEC版の光RWC-1のボードです。NEC版と日立版の光インターコネクションモジュールをくらべると、いずれもパラレルファイバーを使っていますが、日立版の方は材料に工夫をすることによってファイバー間の信号伝搬の遅延の差(スキュー)を減らし、送り手側で一斉に送り出したものは受け手側でも一斉に受けることができるようにしています。これに対してNEC版の光モジュールでは、受信側に調整回路をつけることによってスキューを吸収する技術を使っています。図3(b)にありますように、一本だけファイバーを2m長くするようなことをしても正しく伝送されることが実証されました。一方の超波長系レーザ材料の開発では、アンチモン系の材料を使って1.3μmの長波長の面発光レーザ(VCSEL)を作ることを最終目標にし、平成9年度には実際に発光するという成果をあげました。
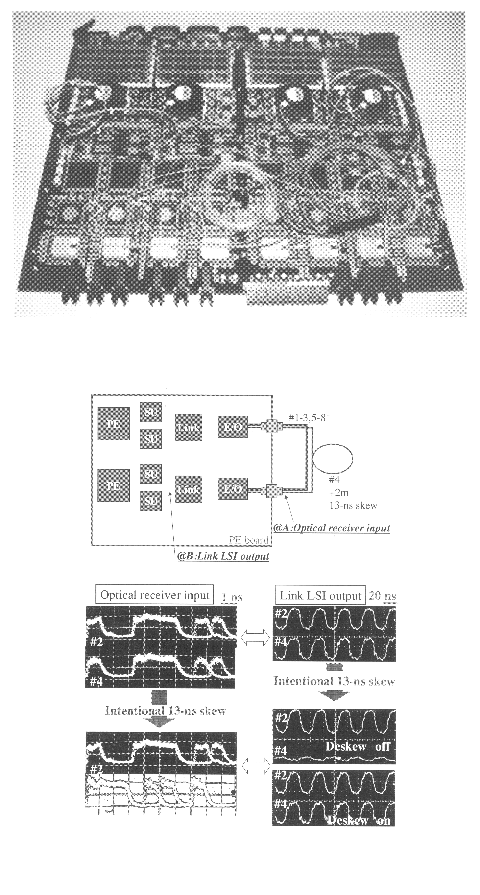
図3.光インターコネクションNEC研究室
(a)
光接続RWC-1/Nのプロセッサボード
(b) ワンチップリンクLSIでのdeskew
3)光インターコネクション富士通研究室
光インターコネクション富士通研究室では、光インターコネクション用に、波長1.3μmの低電圧動作の面発光レーザー(VCSEL)開発を行っています。このレーザーは、図4に示すように一番下の部分に3元基板、即ちインジウムとガリウムとヒ素の三つの元素を使った基板を用いるのが特徴です。この基板を用いることで、深いポテンシャルの量子井戸と高い反射率のミラーを形成して温度特性の優れた低電圧動作の面型レーザを製作しようというものです。図4は最終的にこのプロジェクトの中で開発するものです。平成9年度は実際にこのインジウム、ガリウムとヒ素からなる3元基板を使ったレーザーを作り、その特性の評価を行いました。このレーザーの特徴は非常に高い温度でも安定して動作するということです。
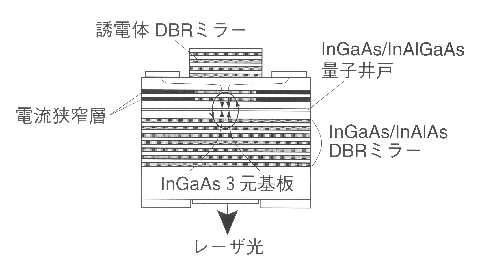
図4.光インターコネクション富士通研究室
--InGaAs
3元基板上の光インターコネクション用低電圧動作面型レーザー
4)光インターコネクション沖研究室
光インターコネクション沖研究室の一つ目の開発目標は125μmピッチのファイバーアレーです。これは実際にこのプロジェクトの中でシステム実証を行う予定です。従来、ファイバー間のピッチが250μmのパラレル光ファイバーが主に用いられているのですが、沖研究室では図5(a)のように実際にモジュールに接合する部分で125μmピッチにする技術を開発しました。これによってモジュールの部分を非常にコンパクトに作ることができるようになります。次に、将来のシームレスシステムに向けての技術開発として、シリコン上に回折レンズを生成し、LSIのシリコン間を直接光で接続する技術の開発を行っています。シリコンの基板上にレーザーダイオードを作り、ピンボトルネック等を解消することを目指しています。最終的にはレーザーを開発しますが、平成9年度は図5(b)に示すようにシリコンの基板上にLEDを形成し、さらにそのシリコン基板上に回折レンズを作って、LEDからの発光をシリコンの基板を通してレンズによって集光する素子の開発を行いました。
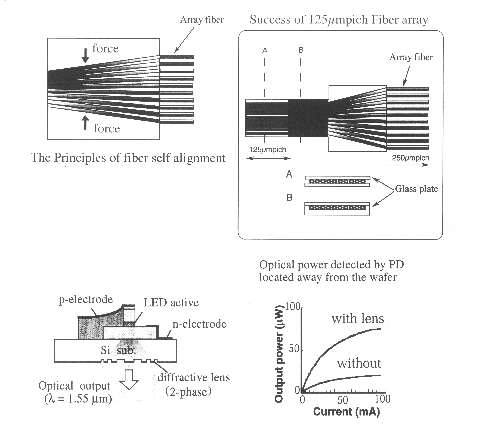
図5.光インターコネクション沖研究室
(a)125μmピッチファイバーアレー
(b)シリコン上に集積されたLEDと回析レンズ
5)光インターコネクションフジクラ研究室
光インターコネクションフジクラ研究室では、将来のシームレスシステムのための研究開発として、スキュー低減型テープファイバの開発を行っています(図6)。目標値としてスキューは、ケーブルで1mあたり1ps以下、テープファイバのレベルで1mあたり0.5ps以下という目標です。平成9年度は、8本のファイバからなるテープファイバでスキューが1mあたり0.56psのものの開発に成功しました。また、このスキューを測定する技術の開発等も平行して行われており、合わせて最終目標値に向けての研究開発が行われています。将来像としては、装置間で100m程度をつないでもスキューが実用上問題にならないというようなテープファイバの開発が目標になっています。
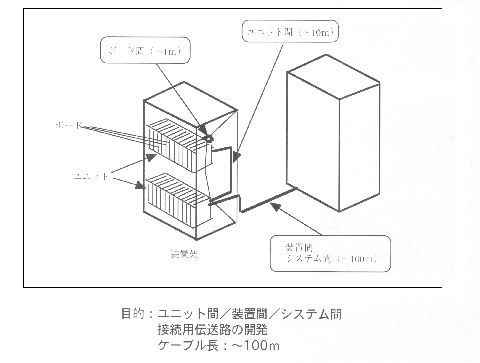
図6.光いん他ーコネクションフジクラ研究室
--光並列伝送用テープファイバー使用例--
6)光インターコネクション古河研究室
光インターコネクション古河研究室では、10Gbps以上の伝送帯域をもち、低消費電力で動作し、更に、低コスト化を目指した無調芯型面発光レーザモジュールの開発を行っています。無調芯というのはアライメントフリーということで、面発光レーザ(VCSEL)のビーム広がり角が狭いという特徴を活かし、通常、モジュールを組み立てるときに必要なレンズを用いず、ファイバとレーザを直接高効率で光結合させるモジュールで、その位置合わせ及び固定時に、精密作業をほとんど必要としないものを指しています。低消費電力動作の観点から、VCSELには、極低しきい値発振、高電光変換効率動、また、低コスト化を考慮して、パッケージ、フェルール等のモジュール構成部品にはプラスチック成型部品を用いることを検討しています。平成9年度は、酸化アルミニウム・ヒ素(AlAs-oxide)を電流閉じ込め構造(図7(a))に採用した980nmVCSELの開発を行い、図7(b)に示す特性(最小しきい値電流0.4mA)が得られました。
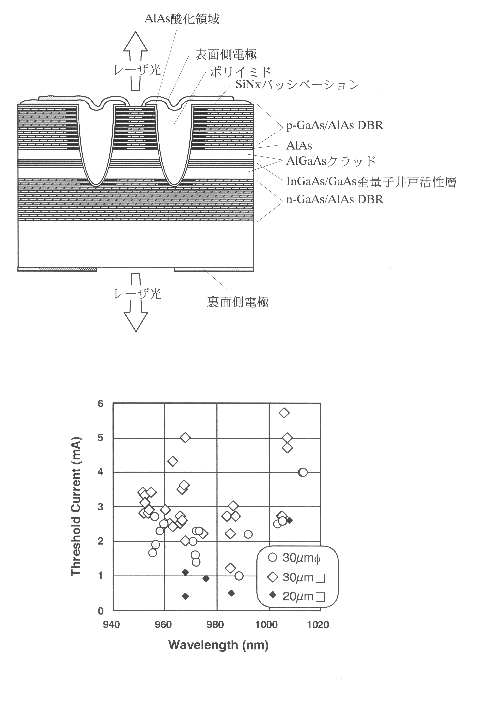
図7.光インターコネクション古河研究室
(a)
980nmVCSELの構造
(b) 980nmVCSELの発振特性
7)光インターコネクション住電研究室
光インターコネクション住電研究室では、波長多重(WDM)方法を用いた光LAN技術の開発を行っています。平成9年度は、キーデバイスであるファイバーグレィティングレーザーを開発しました。シングルモードファイバー中に形成したグレーティングを外部共振鏡にすることにより、
グレーティングの回折波長で決まる特定波長で安定に発振するレーザーが実現できます。そのためには、半導体光アンプの出射端面の残留反射を下げ、ファイバーグレーティングからの光帰還を安定にする必要があります。そこで半導体光アンプ出射端面の反射率を低減するために、図8のように半導体光アンプの端面を活性イオンエッチング(RIE)を用いて斜めにする技術を開発しました。これによって、単一波長で、安定した光出力のレーザ発光が得られました。
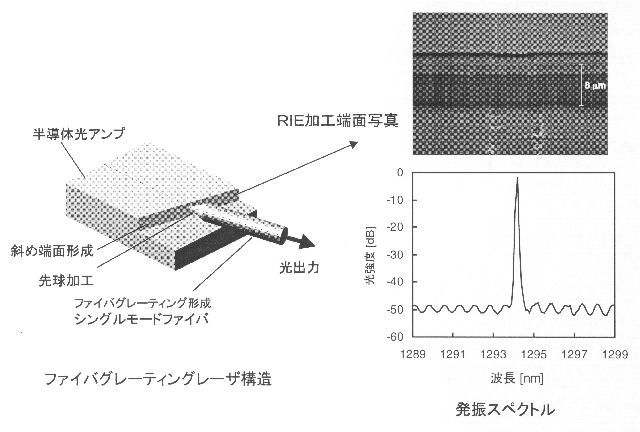
図8.光インターコネクション住電研究室
--
RIE斜め端面半導体光アンプを用いたファイバーグレーティングレーザー
8)光インターコネクション日板研究室
光インターコネクション日板研究室では、空間多重光インターコネクションのための技術開発を行っています。具体的にはファイバーを2次元に配列することにより空間を効率良く使うことができるようにし、空間当たりのバンド効率を向上させます。この際、2次元にならんだファイバーに光を入れるために、図9(a)のような平板のレンズアレー(平板上にレンズが並んでいるもの)とホールアレー(平板に細かい穴が開いているもの)を開発しています。平成9年度は図9(b)の写真のようなレンズアレー、ホールアレーの開発に成功しました。
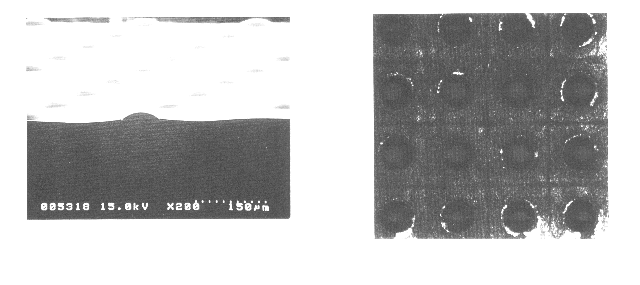
図9.光インターコネクション日板研究室
--空間分割多重光インターコネクション用素子--
(a)平板マイクロレンズアレー
(b)平板マイクロホールアレー
■
おわりに
ご紹介しましたように、光インターコネクション領域は8つの研究室から成っています。図10の○で示した部分がこのRWCプロジェクトの後期5年の中で実際にシームレス並列分散コンピューティング技術領域で応用される技術、※でマークされた技術は将来のシームレスシステムにおいて使用される技術ということになります。
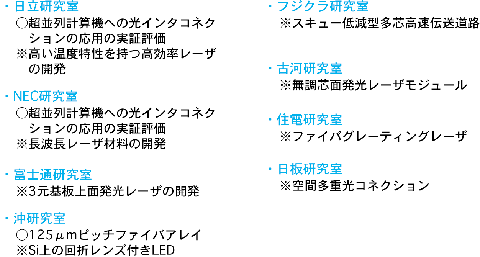
図10 光インターコネクション技術サブ領域の開発項目
|