実世界適応デバイス領域における研究開発
■
はじめに
実世界適応デバイス領域のリーダーを担当しております電総研の樋口です。実世界適応デバイスの研究開発状況についてお話をさせていただきます。
この領域では、実世界応用を効率的に支援するための適応デバイスの研究開発を行っています。大きく2つに分かれており、その1つは次世代電子的デバイス、もう1つは光デバイスです。
次世代電子的デバイスの方は、さらに2つに分かれています。1つは静的適応デバイス。これは簡単に言ってしまえば従来のFPGAの発展形といえるリコンフィギュアブル・ハードウェアで、RHWと呼んでいます。もう1つは動的適応デバイスと言いまして、アルゴリズムが変動する場合に対応します。つまりハードを設計する時いろいろなタスクで一番いいハードウェア設計をして、それを実際にハードに焼くわけですが、それが時々刻々変動する場合が動的適応です。
電子的デバイスと並ぶもう一方の柱である光デバイスの方は、ディジタルスマートピクセルといった方が早いですが、簡単に言ってしまえば小規模なデータプロセスエレメントに光ポートを組み合わせたものを1ピクセルとして、これを多数2次元に並べたものです。つまり普通のCCDとか液晶デバイスというのはみんなビデオレートで制限されてしまうわけですが、その限界というのを全部とりはらって高速かつコンパクトなシステムを実現しようとするわけです。
■
研究体制と再委託先の成果
まず、大枠でいま申し上げた電子的デバイスと光デバイスの説明を行います。主に分散研の研究体制と大学の再委託と電総研RWIセンターの成果で、電子的デバイスで中心になっているのがNEC研究室です。光のデバイスの中心になっているのは、松下技研研究室です。
まず電子的デバイスの研究体制ですが、先ほど申し上げたように静的適応と動的適応の2つに分けまして、それぞれについてまず基盤となるハードウェアデバイスがあります。それにどのようにアプリケーションをのせるかということ。さらにその応用技術。それぞれ応用をいろいろな再委託先と連携して研究しているわけですが、大きく分けると一方がNEC研究室が主体で、もう一方は電総研のRWIセンターがNECと連携して研究を行っています。
個々の再委託先の成果について簡単に申し上げますと、1番目が早稲田大学です。RHWと呼ぶ静的適応デバイスのためのCADの研究を行っています。つまり回路設計をハードウェアにどうやってうまくマッピングするかの研究ですが、従来に比べるとだいたい40から60倍高速で、しかもうまいマッピングができているので、論理段数も少なくなって速い。このRHWというのは、従来のFPGAは細かいゲートを集めたようなものですが、これは算術演算回路を基本単位にしたものです。要するにいろいろなハードでもその算術演算主体に特化したいと、そういう応用を狙っています。
坂上さんの発表や松井さんの発表の中で顔認識で高次相関というのがありますが、まずこのパターン認識への応用を考えています。これを今のRHWというチップで実現するわけですが、シミュレーションではDECのアルファの400メガ、要するにワークステーションのとても速いものに比べて、50倍ぐらい早い結果が得られています。今年はさらにそれをPCIボードというかパソコンの中に収納するように作りますから、それができると本当にパソコンレベルで極めて早く顔認識ができるようになります。ですから本当にマルチモーダルパソコンがハードウェア的にサポートする土台になり得るという感じがいたします。
2番目の再委託は東邦大学です。これは応用技術のディジタル通信ですが、ビタビアルゴリズムというものをFPGAで実装しました。ビタビアルゴリズムの細かい話は省略しますが、簡単に言ってしまうとディジタル移動通信です。つまり車が走っていて、そこからの映像をどこかに飛ばす。ところがこの受信端では、いろいろな反射とか気象条件によってひずんだり遅れたりしてもまとめてここで受信されるわけです。ここの言わばひずんだデータから元のきれいなデータを復元する、そのアルゴリズムであると思っていただければいいと思います。それを市販のFPGAで実現してかなり早いのができたのですが、今年はこれをNECのチップでやってみる。要するにどれだけ市販チップに対して早いかということを実証したいと思っています。

図1
3番目の再委託先は北海道大で、筋電制御の義手の開発が主です。現物はこれ(図1)ですが、実際は指紋付きのゴムを被っています。なぜ義手かということについてご説明します。これは筋電義手と言いまして、力を入れるとき筋肉から電位が出るわけですが、そのパターンによって握るとか開くとか、回転とかの制御をします。こういう義手は日本にずっと前からありますが、とにかく人間がその義手に慣れなくてはいけないのが問題でした。つまり、普通患者さんが新しく義手をはめると、手が実際にはないのでボディイメージをうかべることで握る動作を実現しようとする。その通りにうまく動くまでにだいたい1ケ月ぐらいかかるらしいんですが、あまり使い易いとは決して言えず、これが義手の普及を妨げています。その過程を我々はいまだいたい10分以内に縮めることに成功しました。それは動的適応チップを使っていることによります。明後日のデモでは、開く、握る、と音声でトレーニングしていくうちにだいたい数分で、最初パッとつけたときウンともスンとも言わないものが、音声で開く、閉じると言っているうちにその通りに動くようになるのを見て頂きます。
海外の再委託先としては、ベルギー自由大学ですが、これは動的適応のための学習モジュールの研究開発です。動的適応では遺伝的アルゴリズムを使っていまして、その理論基盤の開発をお願いしています。スイス連邦工科大学では、耐故障性アーキテクチャの開発を行っています。普通FPGAというのは、たくさんの細かいセルから成っているわけですが、どれか壊れたときにそれを回避して、さらにきちんと動くようにしたい。そういう耐故障性のアーキテクチャということでは、ここは歴史があるし、特許を持つところです。それをNECのRHW用に考えてもらうことになっています。
つぎに電総研のRWIセンターの成果についてお話します。大別して2つありますが、ここでの研究というのは要するに動的適応デバイスの基本設計と応用の評価ということです。ここでは進化するハードウェアと呼んでいます。これを応用した研究として自律移動ロボットEvolverを構築すると共に、動的適応デバイスの基本設計をいたしまして、NECとともに実際にチップを作りました。
まず最初に進化するハードとは何かということを簡単にお話します。ハードウェアというものは1度作ってしまうと機能が固定的ですし、自分で中身を変えるということはできない。しかし、ちょうどカメレオンが新しい環境へ入れられたら色が変わるように、ハードウェア自身を自律的にダイナミックに変わらせたい。自律的ということと、ダイナミックということ。この2つをハードウェア自身にやらせたいということです。そのメカニズムとして遺伝的アルゴリズムと、FPGA的な再構成可能型ハードウェアを使おうというわけです。
簡単に遺伝的アルゴリズムについて申し上げます。0,1のビットパターンの染色体をいくつか用意しておいて、この間でいろいろなかけあわせを行い、良い染色体を残す。非常に大きな探索空間でもわりと効率的にみつけることができるのが特徴です。
一方、進化するハードウェアのもう1つの基本アイディアというのは再構成型ハードウェアです。ビット列を書き込むことで任意のハードウェアができあがるのが特徴です。そのビット列がいろいろなコネクションとか、ブロックの中の機能選択とかに相当しているわけです。進化するハードウェアのキーアイディアは、再構成可能型ハードウェアのコンフィギュレーションビットを遺伝的アルゴリズムの染色体とみなして、これを変化させることです。要するに自律的に環境に応じた適切なハード構成をとらせようというわけで、最初に作った例がEvolverというロボットです。これは簡単に言いますと、カメラが2台あって、赤いボールを絶えず追いかける。普通のロボットというのはだいたい一挙手一投足が100%プログラムされているわけですが、ところがこのロボットには、ボールを追いかけろということしか、言わば本能として置いていない。どうやって追跡するかということはその環境に応じて決定されるので、我々自身もわかりません。障害物もその場所も変わるし、障害物の形ももちろんどうでもよろしい。たとえばセンサがこのロボットの周りにくっついているんですが、センサを意図的に壊しても残りのセンサだけで動くようにロボット自身が再構成して動くわけです。これもデモでお見せしますが、ここのロボットの周りに8つ近接センサがくっついています。そのどこかを意図的に壊す。そうするといままで避けられたのにぶつかってしまう。ところが、あまりぶつかるうちに自分でもこれはおかしいとロボットが思い始める。それでもう1回、ロボットの制御回路をロボット自身が動的に再構成し直して、今度は後ろを向いて動き出す。どのくらい後ろを向くかというのはその時々なんですが、要するにまったくこのふるまいがイマージェントになっているわけです。このようなことをコントロールしているのがすべて進化ハードということです。
このロボットの位置付けですが、いままでいろいろな自律移動ロボットがありましたが、大まかに言うと、本当に自律移動ロボットとしてオンラインでその場で動くというのはスタンフォードとスイスのこの2つです。スイスのほうはだいたいニューラルネットを使って65時間、つまり環境を変えて65時間で適応するわけです。スタンフォードは強化学習なんですが、これもだいたい10時間から20時間。これらに対して、我々のロボットはだいたい5分から10分でその場で適応できるわけです。たまたま運が悪いと10分になってしまうし、早ければ5分で適応する。つまりどう再構成するかというのは実環境においてみなければわからないので、このようになるわけです。
このロボットは市販のFPGAを使っているんですが、結論的に申しますと、いまこの3番目の適応制御LSIをNECといっしょに作りまして、これを載せる予定です。このLSIは義手にも使います。両方ともいまは市販のFPGAを使っているんですが、それをこのチップと置き換えると何がいいかというと、とにかく義手というのは700グラム以下でないと重くて困ります。ですから、義手にパソコンを積めばいいかというと、そういうことは成り立たない。なるべく小型化しなくてはいけない。ロボットだって小型化しないとバッテリーがすぐになくなる。このLSIを使えば当然スピードも圧倒的に速くなるのはまちがいない。ロボットはいま適応時間が5分から10分で、それでも世界チャンピオンのデータなんですが、これがさらに速くなる。何で速いかというと、遺伝的アルゴリズムが完全に専用ハードウェアでできているからです。そのハードの速度というのがだいたいSUNウルトラの62倍くらいの速さになっています。
順番が前後しましたが、適応通信LSIというのは、要するに自分でトポロジーを変えるニューラルネットのハードウェアです。ニューラルネットを実際、認識なりいろいろな応用に使うときに一番いいパフォーマンスが得られるのは、最適なネットワークの大きさが設定されたときです。ネットワークのノードの中の基底関数も、応用によってシグモイド関数がよい場合と、ガウシアン関数がよい場合とがあります。それらの選択をすべてGAで選択させようというのが、このLSIの狙いです。これら、つまりニューラルネットワークの情報全部が遺伝子で表現されます。このLSIというのは、32ビットのRISCプロセッサと、ここにツリー状に繋がった15個のDSPがあるんですが、これらの上に直接ニューラルネットはマッピングされます。スピードについてはまだ完全な評価をしていませんが、19インチラックぐらいに使うと、46GCPSぐらいは出るものと思われます。
動的適応の2番目の例ですが、電子写真印刷用データ圧縮です。電子写真というのは皆さんあまり聞き馴染みがないと思いますが、簡単に言ってしまいますと、いま世の中の印刷というのはオフセット印刷です。本をつくるときに、例えば1ページ目を1000部印刷して、次に2ページ目を1000部印刷して、最後にソートして製本します。電子印刷というのはそうではなくて、100部とか小部数でかまわず、1ページずつ印刷し、おわればすぐ製本です。社内のマニュアル等によく利用されます。最近よく写真画質だとか言ってますが、それを高速にします。普通例えばこういうカラーのOHPをつくるのにへたすると10分かかります。ゼロックスのカラーコピーだと1分間7枚程度ですが、この電子写真印刷はだいたい1分間72枚です。毎秒1枚以上です。それを1ページ目、2ページ目、3ページ目で書き替えながら印刷していきます。これはものすごいスピードです。またこのデータ量がきわめて大きい。だいたいA4、1枚4色で32メガぐらいです。そうすると100ページあったら3ギガ。それが要するにこの印刷機の中で蓄えられて高速に印刷されなければいけないのですが、それだけのものを中に入れておく為には当然データを圧縮しなくてはいけない。圧縮するだけでなく、今度は、一分間に72枚も印刷しますから、ものすごい速さで解凍しなくてはいけない。つまり高圧縮率と高エクスパンションの2つを満たさなければならない。高エクスパンションをソフトでやったらぜんぜん間に合いません。結論的に言いますと、この進化ハードというものを使うことで、圧縮率が業界標準のJBIGの2倍になります。たんに2倍というと、なんだ2倍かと思われるかもしれませんが、ロスレスデータ圧縮の世界で2倍というのはとんでもない話なんです。これは動的適応の一番象徴的な例かと思います。このLSI写真を図2に示します。
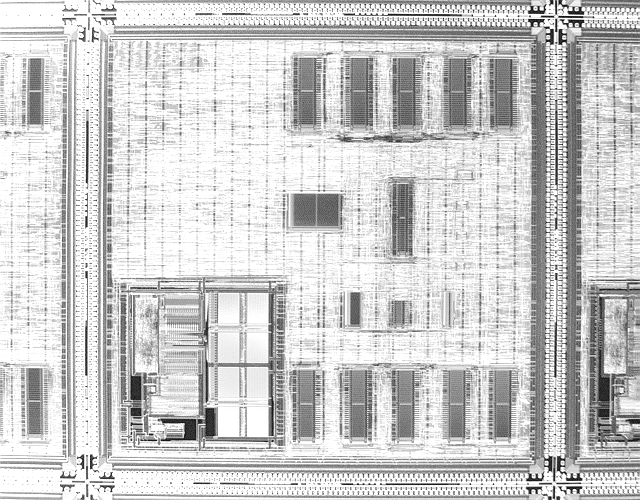
図2
以上が電子的デバイスの説明です。次に光として、ディジタルスマートピクセルの話に移らせていただきます。
まず体制図ですが、松下技研研究室と東大への再委託、そして電総研という形です。東大の方でディジタルプロセッシングアレイとフォトディテクタが組になったものを作り、松下技研はその上にLEKの設定、実装をする。実装といってもかなり細かく、しかもLEKが発熱します。その熱をどう逃がすかという実装上の問題があります。このディジタルスマートピクセルを作って、それをターゲットトラッキングと光ニューラルネット、この2つで評価をしようというわけです。
まず東大の方です。スマートピクセルの概念図ですが、要するにプロセッシングアレイのところにフォトディテクタがくっついている。これが2次元状になっています。スーパーグラファイトを入れる実装技術によって発熱の問題を解決しています。今年は2×2のスマートピクセルを実現しました。
また電総研のRWIセンター光情報処理ラボでは、30×30ぐらいの顔の画像を認識していますが、だいたい顔を15度ぐらい動かしても学習、認識できます。学習の1サイクルは200ミリぐらい。だいたい7200コネクションをアップデートしていますが、ディジタルスマートピクセルができたら、これに置き換えて評価をするという体制になっております。
以上がこの領域の概要です。
それからRWIセンターというのは電総研の中でこのRWCプロジェクトと対応しているスーパーラボと言います。電総研が研究室からラボ制に移行しまして、8つのラボでこのRWCを側面支援していることになっております。特に、実世界知能分野を推進するという意味で我々は所内的なスーパーラボと呼んでいます。
|