新しい情報の世界に向けて
 |
通商産業省
次世代情報処理基盤技術
開発推進委員会
委員長 田中 英彦 |
「新しい情報の世界に向けて」というタイトルで、RWCPの今後について皆様と共に考えていきたいと思います(図1)。
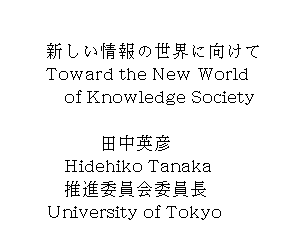
図1
このタイトルの「新しい」がどこに係るかは大江健三郎の「あいまいな日本の私」というのに少々似ておりますが、そういうつもりでタイトルをつけさせていただきました。 今年はちょうど後期2年度にあたります(図2)。
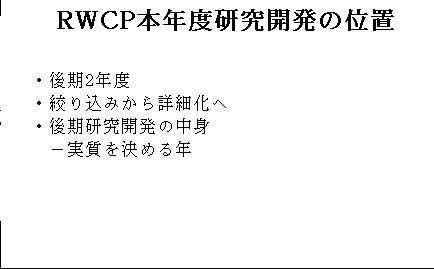
図2
昨年度は、前期からの沢山の研究から絞り込みが行われました。そして今、「詳細化へ」ということが行われている最中です。従って今年は後期研究開発の中身を決めるという、正に「実質を決める年」です。このような年にあたり、情報の世界を少々考えてみたいと思います。
情報の世界を支える技術として期待したいものは何だろうと思った時に、AとB、二つが挙げられるかと思います。(図3)
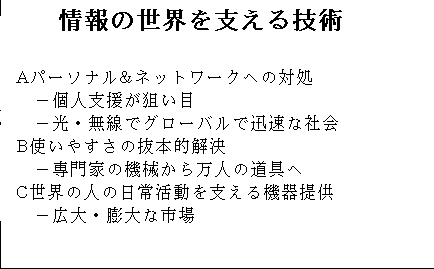
図3
一つはパーソナルな支援、個人支援をできるだけやっていくということ。それから、とても速いスピードの光とか、場所によらない無線とか、そういった通信技術が非常に発達してきています。それらを利用して融合した自由な、コンピュテーショナルの世界を作っていく、パーソナル&ネットワークへの対処というのが一つだろうと思います。
もう一つは使いやすさへの抜本的な解決だと思います。現在コンピュータは確かに沢山の人々に使われています。しかし、使っているのは、日本の場合ですとおそらく人口の10数%の人たちでしょう。その人たちはコンピュータの使い方を一生懸命勉強して、馴れてきたわけですが、信頼性など、色々な点でまだまだ満足できない点が多いのではないかと思います。今後、人口の80%の人たちが情報処理の機械を何らかの意味で使う時代が来るだろうと思いますが、そういう時代の機械という存在には未だなっていない、ということが、もう一つのポイントです。それに対する支援というのは、正に、非常に知的な処理を多用したサポートが必要ではないかと思います。このような二つの支援が必要だと思いますが、そういった機械はまだまだ世界的にもスタンダードがない、デファクトの存在しない状況だろうと思います。しかも、その市場はパソコンの数倍といえる市場だろうと思います。そういう意味で膨大な市場が目の前にあるわけで、それに対して是非アタックしたい、しなくてはならないと思います。
RWCPでの取り組みについては、このような二本柱が立っています(図4)。
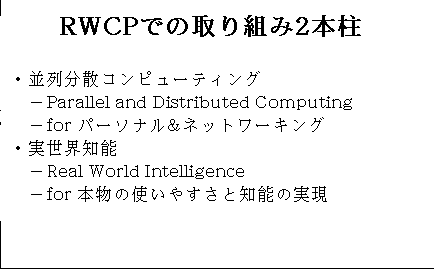
図4
一つは「並列分散コンピューティング」、もう一つは「実世界知能」。これらを先ほど申し上げたやりたいことに対比させてみますと、並列分散の方はパーソナル&ネットワーキングに対する支援研究と考えることもできますし、実世界知能の方は、本物の使いやすさ、また、本物の知能というものを実現していく、といったことへの基礎研究と言えると思います。これは正にこれから必要とされるような機能を中核としてとらえた研究になっているのではないかと思うわけです。
では、この一つ一つをもう少し眺めてみたいと思います。先ず、パーソナル&ネットワーキング(図5)。
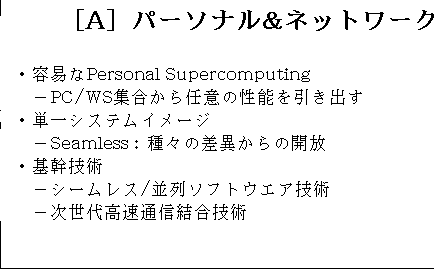
図5
その一つは容易なパーソナル・スーパーコンピューティングです。PCとかワークステーションとか、現在LANには多くのものが接続されていますが、そういった現在手にしているものから利用者が自由に自分の欲しい計算パワーを引き出す、というようなことをしたい。そして、そういった性能を引き出すことができたとしても、利用者にとって非常に分かりやすい、単一システムのイメージで提供してくれなくては意味がない。これがシームレスの部分です。また、こういうものの基幹になるのは、シームレス技術、並列ソフト技術、それから次世代の高速通信や結合の技術など、色々あると思います。
この点、従来の計算環境を振り返ってみますと、皆さんが、日頃経験されているように色々な問題点があります。(図6)
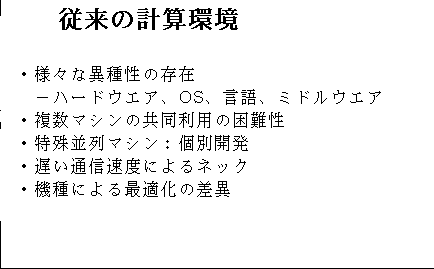
図6
一つは様々な異種性の存在。様々なハード、OS、言語、また、複数のマシンを同時に使って自分の計算パワーを出してもらうというのは、現在なかなか難しい状況にあります。使っているマシンは一つというのが普通で、多数のマシンを合わせて使いこなすというようなことはなされてないのが現状です。もう一つは、非常に大量の処理をしようと思った時には、並列スーパーコンピュータなど特殊なマシンを使うことがあると思いますが、そういうマシンは個別に開発されたもので、一般の人々が欲しい時にパッと使えるようなものではないということ。それから、通信速度のネック。このために複数マシンを一台にするなど出来ないような状況になっているし、最適化の差異という問題もあります。細かい話になりますが、あるマシンで動く並列プログラムがあった時に、それを別のマシンに持っていって、さっと動いてうまく能力を出せるかというと、まず出せません。なかなか困難なのが現状です。
現在、こういった困難に対処するために、RWCにおいてこのような研究が行われています(図7)。この中身については、これから多くの議論があるかと思いますので触れませんが、こういったタイトルで、先ほどのような色々な目的に合わせて研究が行われているのではないかと思います。この中のシームレスコンピューティング、これをもう一度絵で書いてみますと(図8)、Windows、UNIX、Massively
Parallel
Machineなどが高速のLANで結ばれて、利用者から見るとスーパーコンに見えたり、ある時は小さなパソコンに見えたりする、それは非常に自由である、というイメージがある。何かソフトをかませてやれば、ユーザから見れば、煩雑な作業のない、単なる非常に使い易い計算機であり、その計算パワーはフレキシブルに動く、というイメージではないかと思います。注意すべきは、たとえこのLAN上のシステムのOSがすべて同じOSであったとしても、シームレスの目指すような単一イメージ、すなわちコンピュテーションパワーは自由に変えることができる。システムは単一に見える、となる迄には程遠く、まだまだ大きなギャップがあるということで、そのギャップを改善するのがシームレスと言うことができると思います。
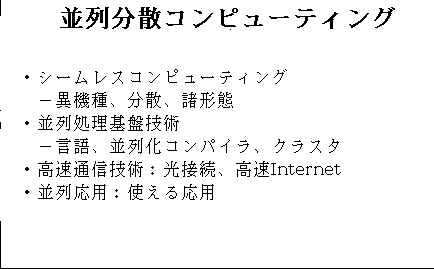
図7
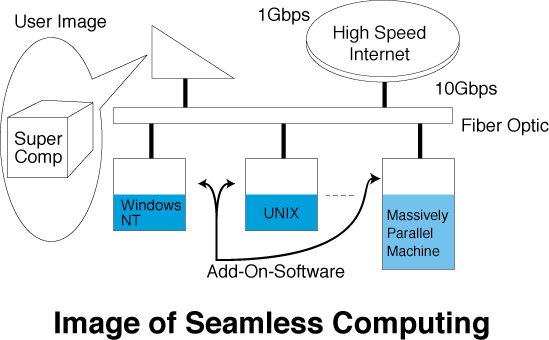
図8
では、このような研究で成果としては何が期待できるのでしょうか(図9)。
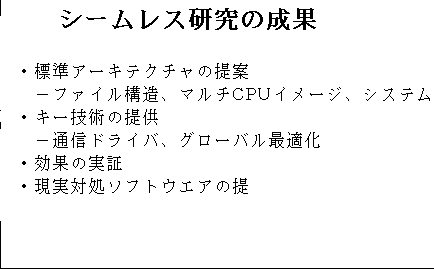
図9
これは、今後これらに関係している方々がどんどん詰めていかれるべきものですが、現段階でこんなものが期待できるかなということを想像して書いてみました。一つは、単一のシステム、標準アーキテクチャですね。計算機ってこんなもの、というアーキテクチャを提案すること。それへの変換機を作れば、複数のマシンが単一システムイメージに見えるということですね。もう一つは「キー技術の提供」と書いてありますが、単一システムに見えるには何が必要かという、キーとなることがいくつかあります。そのキー技術を解決し、提供するということ。三つ目は効果の実証。そういった単一システムイメージ、シームレスコンピューティングの環境が出来た時に、結局何が嬉しいのか、何が可能になったのかということを実感を持って示すこと。アプリケーションと共に、それは非常に重要なポイントだと思います。さらに、現在、現場で使われている様々なパソコンやワークステーションに、ポッと載せればシームレスができる、そういったソフトウェア自体が提供されること、というのが成果の一つになるかと思います。
最初にお話しした二つ目の使い易いコンピュータの開発部分、これは即ち、知能技術を開発することになるかと思います(図10)。世の中には多様な情報がある。マルチメディアに代表されるものだけではなく、整理されてない世の中の様々な情報を上手く整理してコンピュータが使えるように自己組織化する。また、世の中は変わっていきます。状況も変わっていきます。そういうものをどんどん取り込んでいく自律学習というようなことも、もう一つの必要な機能になってきます。また、メディアにもいろいろある。単なるテキストデータだけでなく、いろいろなメディアを人間のように使いこなしていく。コンピュータ自身が、そういうものを使っていく中心になる。更には、コンピュータなり情報システムなりは、人並の知識というものを持って欲しい。人並の知識をコンピュータが持てば、がらりとインタフェースが変わると考えられますが、もちろんこれは非常に難しい問題で、あらゆることに人並みなんてとんでもない話ですが、ある特定部分については人並み、という意味で知識を持って欲しい。こういうことが知的な道具を作るときの中核要素として位置づけられます。
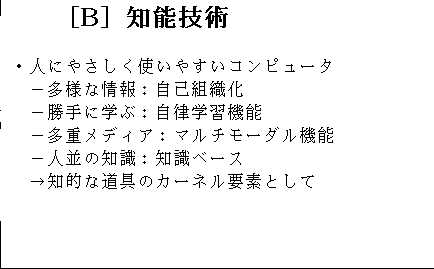
図10
これは実世界の特徴を書いた絵ですが(図11)、言い換えると、いろいろな問題点や情報間の複雑な関係、実世界に埋もれたあいまいな情報、また、環境はどんどん変わっていくし、色々な形態の情報がある。そのようなことに関しては従来、人が整理したり、発見したり、人が合わせたり、数値的に整理するという具合にやってきたわけです。それをコンピュータ自身にやらせるというのが、もう一つの重要な研究テーマだと思います。
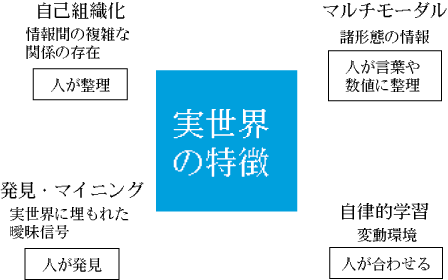
図11
では、使いやすい機器とは何だろうという方向を考えてみたいと思いますが(図12)、おそらく、知識と学習機能を備え、それから情報の重要な部分を自分で、あ、これだと判断できる、そしてマルチモーダルな機能を持った機械。また、様々な制約、場所、距離、OSに捕らわれない機器。こういう機器が一つのイメージかなと思います。もう少し言い換えて、利用者がどのように情報機器を使うかという使用レベルについて考えてみると、現在は読み書きソロバンのレベルではないかと思います。Wordを使ったりExcelを使ったり、というレベルではないでしょうか。そういうレベルからもっと高いレベル、探索、相談、設計というようなインタフェースでコンピュータを使うというレベル、例えば、旅行計画を立てるというようなことを想像していただければいいかと思います。探索というのは、多量なビデオソースから、ああ、ここに行きたいなという場所を探す。その時どの飛行機がいいか、どのホテルがいいかということを、計算機にコンサルテーションしてもらう。もちろん計算機の中はネットワークで結ばれて色々処理しているわけですが、コンサルテーションをする旅行エージェントとしての計算機に相談する。それに基づいて自分の旅行の計画を立てる。何月何日に出発して、お金は幾らである、というような計画を立てる。計画を立てるというのは設計と言い換えてもいいかも知れませんが、このようなイメージ、老いも若きも計算機を使う、情報機器を使うという時代には、こういった意味でのインタフェースというのが考えられるのではないかと思うわけです。
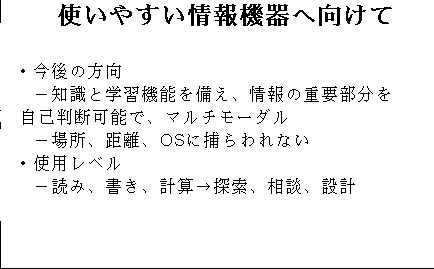
図12
これは、いろいろなモジュールを単に絵に書いただけですが(図13)、情報機器というのは、実世界に対してこのような新しい機能を付け加えることによって、エンハンストされているわけです。そういう機器として情報システムを考えていくことができるかな、というイメージ図です。
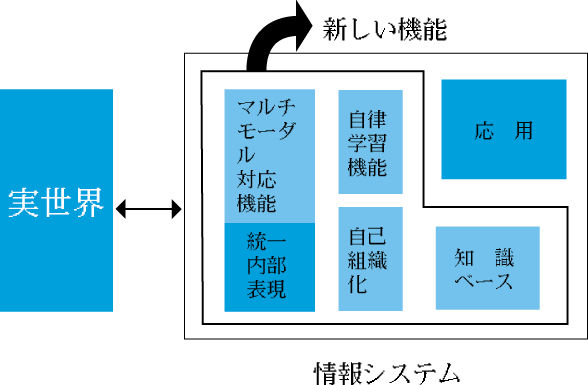
図13
こういう分野におきまして、RWCプロジェクトでは、このようなグループが形成されており、様々な研究が行われています(図14)。
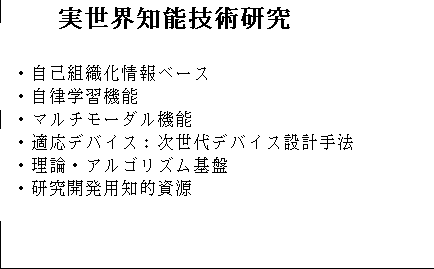
図14
上の三つについては言葉を引用させていただきましたが、下の三つについてはお話していないので追加しておきますと、適応デバイスの研究では、次世代デバイスの設計手法としてなかなか面白そうなものがいろいろ検討されています。もう一つはこれらを支える理論、アルゴリズム基盤としてのグループというのがありますし、また、全体を支えるソフトとか、ツール、データベースといったものを整理するというグループもある。これらが全体のアクティヴィティといえるかと思います。
では、このような研究の応用としては何が考えられるのか(図15)。
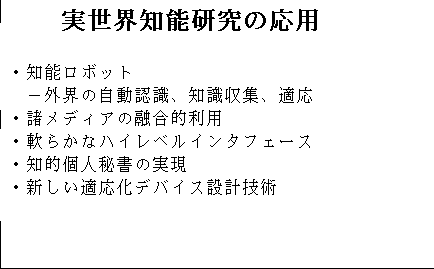
図15
これについても、それぞれのグループの方がいろいろなアイディアを持っておられることと思いますが、非常にシンプルに考えてみると、一つは知能ロボットですね。外界を自動認識し、知識を収集し、適応していくようなロボット。それから、いろいろなメディアを融合的に利用していくようなツール。また、人間にとって柔らかいハイレベルなインタフェースを考案し、提供すること。それから知的個人秘書の実現。もちろんこれは人間ではなく、人間の方がいい場合もありますが、電子的な秘書。そして、新しい適応化デバイス設計技術がもう一つの応用だと思います。
このようにRWCプロジェクトの活動を考えてみますと、特徴としてはこのようなことが考えられるかと思います(図16)。一つはシームレス分野。ここには、「近い未来技術の直視」と書いてありますが、比較的近い未来技術を念頭において研究をしていく。また、単なるアイディアにとどまらず、使える技術としての研究であること。そしてまた、この分野はとても変化が激しいので、方向変化への迅速な対応を常に考え、もしくは何か使えるものが出てきたときにはすぐに取り入れる。最後に、いろいろなことに分散して研究するのではなく、キー技術を集中的に研究開発するということがまずRWC研究のシームレスコンピューティング分野における特徴かと思います。
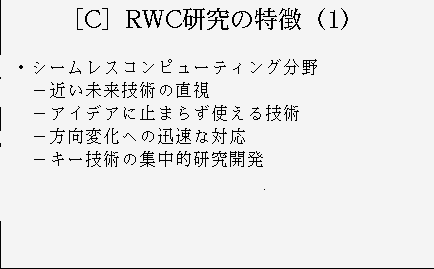
図16
実世界知能分野におきましては少々違いまして、少し遠い未来の実用化を対象とし、知能技術の基盤を研究開発することが目的になっています(図17)。
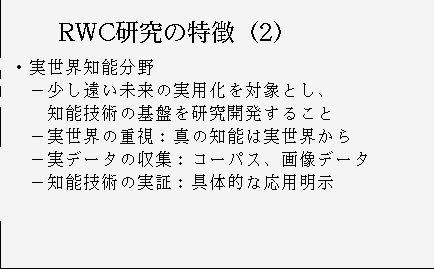
図17
この分野においては、「真の知識は実世界から」というスローガンがありますが、それをベースに実世界重視の研究が行われていると思います。従って、コーパスを作るとか、画像データや音声データを実際に集めるといった作業、それ自身は単なる研究のツールとしてやっているのではなく、その収集自身が重要な仕事であるというのがもう一つの特徴であると思われます。そして具体的な応用を明示しつつ、知能技術の実証をしていくということがターゲットになっているかと思います。
それでは、このような研究をすることによって、何が期待されるのでしょうか(図18)。もちろんそれは、大ざっぱに言えば数年後の基盤技術であり、つまり先行研究といえますが、例えば万人向け個人用情報端末のモデルを提案する、とか、高度知能ロボットのモデルに対する大きな影響などが考えられます。
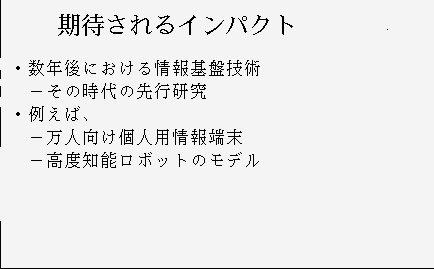
図18
情報端末という部分について、もう少し見てみると、このようなイメージが考えられると思います(図19)。一番下にはデファクトのいろいろなOSがあります。その上にシームレスの技術を置き、さらにその上に、いろいろなエージェント、お互いの間はとてもwell-definedなインタフェースになっているエージェントをたくさん集める。そして利用者には探索とか相談、設計といったインタフェースを提供する。従来のインタフェースである、読み書きソロバンに加え、エージェントを構成する基盤技術はインテリジェントテクノロジーであり、知識ベースであります。このエージェントとシームレスを合わせた部分を新しいミドルウェアと呼んでみたいと思います。
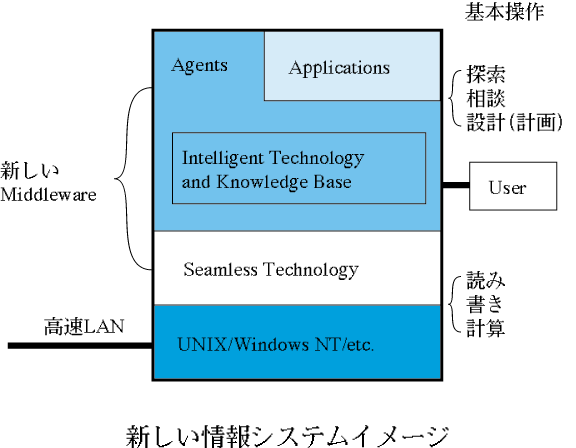
図19
では、このミドルウェアの構成をもう少し見てみましょう(図20)。
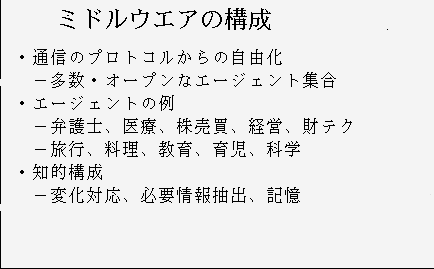
図20
多数のエージェントを集めるという言い方をしましたが、例えば、弁護士エージェント、医療エージェント、旅行、料理等。このようなエージェントがエージェント間の通信をすることでいろいろな仕事をこなしていく。こういう世界ではおそらくオープンであるということが必要不可欠だろうと思います。
従来の計算機は、システムとシステムの間がプロトコルというものできちんと決められていて、それに従った通信を行うのが普通ですが、こういうレベルのエージェントにおいては、プロトコルからの自由化が必要です(図21)。

図21
例えば、自然言語などはそうだろうと思いますが、人間と人間がインタフェースする時には自然言語を使う。自然言語というのは言ってみればプロトコルみたいなものですが、それよりははるかに自由です。そういう意味でのインタフェースを備えたエージェント集団、というようなものです。エージェントというのは変化に対応しなければいけない。自分から必要な情報はこれだということを抽出して自分の必要なことに使うということも必要ですし、また、情報を構造化して記憶していくというようなことも必要になるわけです。
最後に、こうありたいというようなことを少々まとめてみたいと思います(図22)。
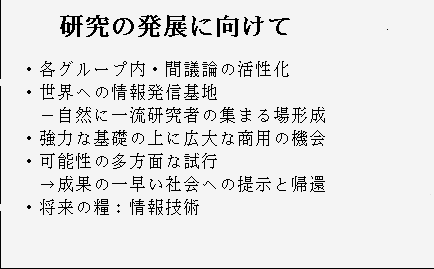
図22
一つは各グループ内、グループ間で議論を活性化していこうということ。また、そういうことで自然に研究者たちの集まる場を形成することによって世界の情報発信基地になっていって欲しいと思いますし、しっかりした基礎の上に広大な商用の機会があるということを考え、基礎的なことに関してはアイディアを持ち寄り、もしくはそういった基礎を出来る限り早く公開して、世の中に使っていってもらうことによって、そのフィードバックを受け、良いサイクルを形成していく。可能性の多方面な試行というのはその中の一つです。そして、社会への成果の一早い提示。実際RWCPの研究の中で、先ほど岡田課長から話がありましたように、おもしろい研究がいくつか出てきました。社会への還元がすでに見られるものも多々あります。そういった研究を温かい目で見守って、育てていきたいと思います。何といっても、将来の糧は情報技術であると思われますので。
|