並列分散コンピューティング技術分野
並列分散コンピューティング技術 -A,D&G-
 |
早稲田大学 理工学部
教授 村岡 洋一 |
今日は、RWCプロジェクトをアウトサイダーから見た印象を前半にお話させていただいて、後半で、それに関連して私自身、今どんなことに興味を持っているかということを少しお話するということにしたいと思います。
副題を「A , D & G」とつけてみました(図1)。
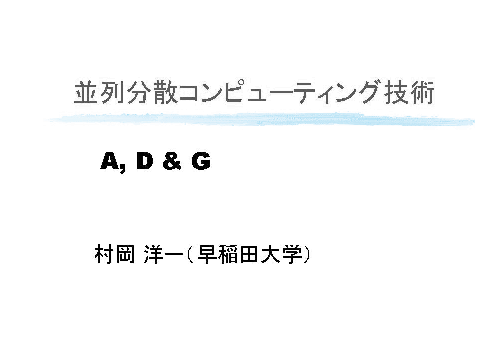
図1
私は、RWCを含めてナショナルプロジェクトには次の三つを満足して欲しいという夢というか希望をもっています(図2)。
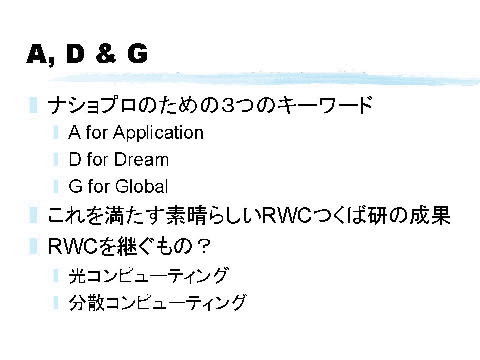
図2
先ずは、新しい応用分野を開くものであって欲しいと思うわけです。A for
Applicationですね。その技術ができたおかげで新しいアプリケーションを開くものであって欲しい。それからやはりD for
Dream、夢をひらくものであって欲しい。昨今夢があるのかどうかわかりませんが、夢をひらくものであって欲しい。最後に、グローバルであって欲しい。グローバルという意味にはいろいろあると思いますが、成果がグローバルに役立つと評価されるものであって欲しいと思います。また、グローバルコーポレーション、グローバルコラボレーション、要するに地球規模の協力をするような、気宇壮大なものがナショナルプロジェクトであって欲しい。これは1タックスペイヤーとしての希望です。
そういう観点から見た時に、私が常日頃伺っているつくば研では、なかなか素晴しい事をやっていらっしゃると思います。具体的にはこの後いくつか、私から見た例をお話したいと思っています。そして、このRWCを継ぐプロジェクト、あるいは継ぐ研究として、私個人がどんなことに興味を持っているかという話を最後にさせていただきたいと思います。具体的には、光コンピューティング、分散コンピューティングという二つのキーワードが、後でご紹介する内容です。
RWCつくば研の成果については、私がここで申し上げるまでもなく、今日の午後、詳しい話があるわけですし、先ほど島田所長からも具体的な成果について話がありましたが、もう一度おさらいすると(図3)、大きく分けてクラスタコンピューティングのハードウエア、ソフトウエア、そして、光インターコネクト、それから並列応用という三つの分野で素晴しい成果を上げられています。前半に使うOHPは私がつくば研の方々にお借りして使わせていただいているものですので、あらかじめお断りしておきます。
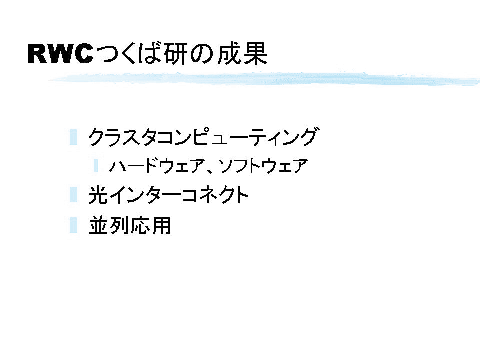
図3
RWC PCクラスタについては後でも触れますが、これはSC97に持っていかれたものです(図4)。
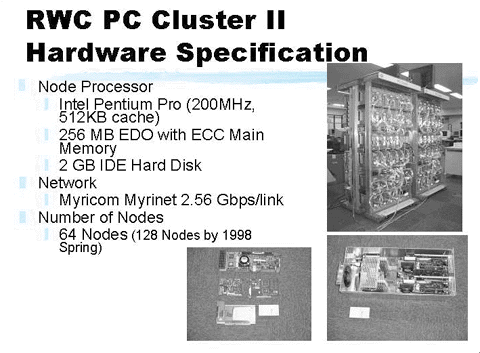
図4
私はSC97には伺えなかったのですが、世界的に著名な人の印象を聞いたビデオを拝見しました。私も存じ上げている素晴しい世界一流の方々が、このクラスタについて、本当に役に立つ、実用的でなおかつ先端的な成果であるということを口を揃えて褒めておられます。先ほどのお話では、この会場でビデオを見られるそうですから、ぜひご覧になることをおすすめします。
私個人は昔から並列のコンパイラを研究していますのでコンパイラを取り上げると、特定の計算機に対するコンパイラはなかなかできないのですが、それを昨今のようにShared
MemoryやDistributed
Memory、ましてや分散まで至る広い環境に対するコンパイラはなかなかできない。しかし、RWCつくば研では、それを目指して素晴しいプラットフォームを作っています(図5)。

図5
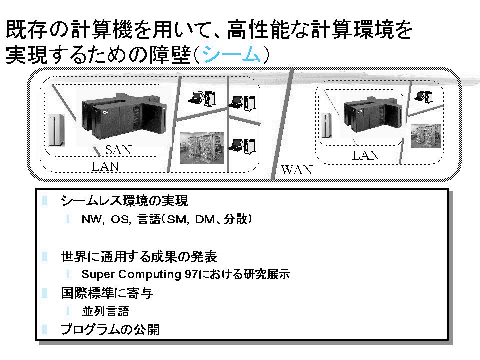
図6
目標はシームレス環境の実現ということで(図6)、ネットワーク、OS、言語に至るまで、実際に役に立ち、しかも世界に通用する成果としてSC97で評価されました。SC97は私から申し上げるまでもなく世界のトップランナーが成果を披露する場であって、ここで評価されなければもちろん世界では何も評価されませんし、ここで評価されれば世界で通用する、そういうところです。また、研究されている並列言語その他が国際標準の世界でも通用する成果を出している。私は常日頃、勝手なアウトサイダーとして申し上げているのですが、ナショナルプロジェクトは国の予算を使うので難しい法律的な制限その他があるようですが、かまわないから成果はどんどんアメリカで使ってもらったらいいのではないかと思います。それで日本が幸せになるのなら、少なくとも1タックスペイヤーの私としてはハッピーです。もちろんお国はどうお考えになるか知りませんが、私はそのような暴言を吐いています。日本で役に立ってもどうしようもないというと言い過ぎかも知れませんが、日本で役に立つだけではどうしようもない世の中ですから、これはつくば研だけでなく、このプロジェクトを推進しておられる通産省その他のお考えもおありだと思いますが、ここまできたわけですから、ぜひ成果を世界で使ってもらう事を推進すれば、先ほど申し上げたグローバル化を、本当の意味で達成できるのではないかと思うのです。プログラムの公開も日本だけではなく、最近はご存じのようにWebの世界で企業内部だけのイントラネットはありますが国内だけを目指したインターネットはありえない訳ですから、プログラム公開を含めて、ぜひインターナショナル、グローバルな成果の公開ができることを望んでおります。
次に光インターコネクションです(図7)。
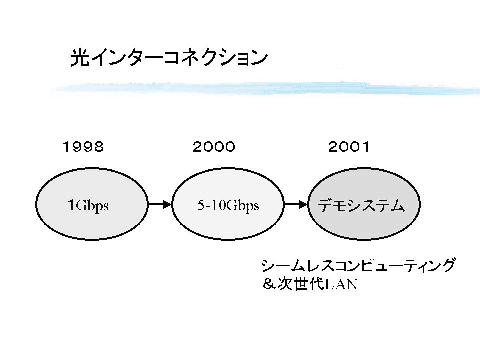
図7
実は光については、こういうことを申し上げては非常に失礼に当たるかとも思いますが、RWCが始まる以前から光、光、光はいいんだという話をいろいろな機会に聞いて来た割には、なかなか手の上にはっきり乗っかるものが出来てこなかったというのが実情かと思います。それに対して、今年(1998年)1ギガ、2000年には5~10ギガということで、いよいよ本格的な意味で、私共が光を使える時代がやってきたというのは喜ばしい限りだと思います。光インターコネクションも、日本の中だけで使えて、日本の計算機をつなぐだけでは役に立たないわけで、世界の計算機をどこでもつなげるインターコネクションにしていただきたい。そのためには技術も当然オープンにしなければならないと思いますし、コネクタの形状から始まって色々な意味での仕様もオープンにして世界標準にしないといけないわけですから、ぜひその辺もよろしくお願いしたいと思います。
最後は応用です。応用というのはどの分野でも大事だと思います。特にコンピュータ、ネットワークの世界は、応用があってのコンピュータ、応用があってのネットワークだと思います。その意味でパピア(PAPIA)、ご存じだと思いますが蛋白質の構造解析のプログラム、立派なものになっています(図8)。
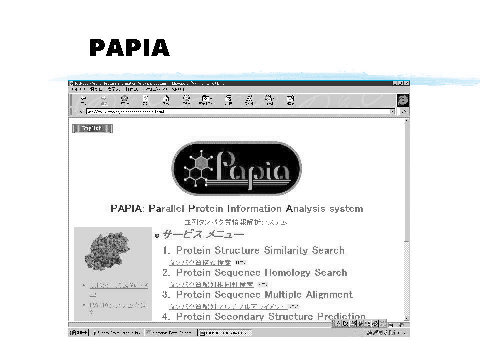
図8
実は、勝手につくば研のWebページを拝見して、簡単なペーストで貼りつけた絵なので著作権違反になるかも知れませんが、それはお許しいだたくとして、実は、このパピア、既に国際的にオープンにされています。日本のナショナルプロジェクトの成果をどこまで外国にオープンにしていいかどうか私は知りませんが、ここでは実はオープンにされているので、非常に心強く、または言葉を悪くすれば愉快に思っています。愉快というのは良くやっていただいているという意味です。
これもパピアのWebページの中からカット&ペーストしたものでご興味がおありでしたら覗いていただきたいと思いますが(図9)、世界中からアクセスされているのがわかります。ここだけ拝見しても、オーストラリアから1000件、カナダから数千件、スイスから200件、アメリカからもたくさんアクセスされています。もちろん、日本からもたくさんアクセスされています。これは是非これからも続けていただいて、もっといい成果ができたら、Webのページでどんどん公開していただければと存じます。ただ残念ですが、昨日でしたか、アクセスして使ってみようと思ったら、今日はダウンしていますというメッセージが出てきました。
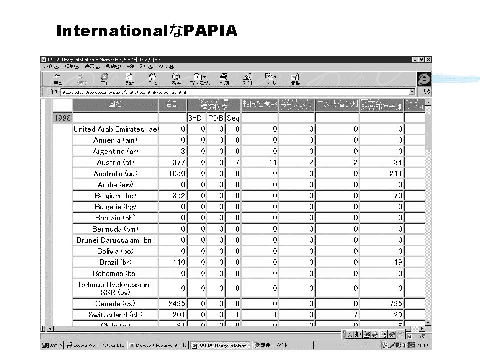
図9
このように、私がナショナルプロジェクト一般、または大規模プロジェクト一般に対してもっている素朴な希望、「新しいアプリケーションを開くものであって欲しい」「夢を開くものであって欲しい」しかも「成果または規模として世界に広がるものであって欲しい」ということを見事満足させて素晴しい成果をあげておられるのがRWCつくば研であるということで、敬意を表わすものであります。
それでは、このような素晴しいプロジェクトにおいて、今後どんなことを展開していただきたいか。もちろん、ここにいらっしゃる方、100人おられれば100人の夢がおありだと思いますが、私はこのあとの時間を使って私自身の夢を語らせていただきたいと思います。
その一つは光コンピューティング、もう一つは分散コンピューティングです(図10)。
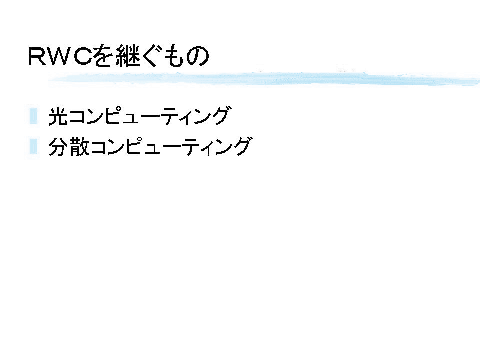
図10
光コンピューティングについては、先ほど申し上げたように、長い間言葉が先行して、ものをなかなか見せていただけなかった。それがいよいよここに来て、言葉がなくてものが出てくる素晴らしい時代になったと思います(図11)。素晴しい時代になったといってもインターコネクトだけで終わるのでしたら光はつまらないわけでして、ロジックの方まで進む。ご存じだと思いますが、アメリカでは現在、ペタフロップス・コンピューティング・プロジェクトというプロジェクトが進行しつつあります。ペタフロップスのマシンをどうやって作るのか、その中の有望な技術として、当然光技術について研究されています。ペタフロップスマシンがいつ出てくるか。アメリカのペタフロップスマシンのプロジェクトでは、西暦2010年を一つのターゲットにしようという議論もなされているようですが、このようなインターコネクトから広がってロジックに至るまでの光コンピューティング。私個人の夢としては、光を使うからにはデジタルと同じようにアナログにも展開できないかという小さな希望をもっていますが、そういうマルチモーダルな光コンピュータができれば、新しい応用が更に展開してくるのではないかと期待するわけであります。
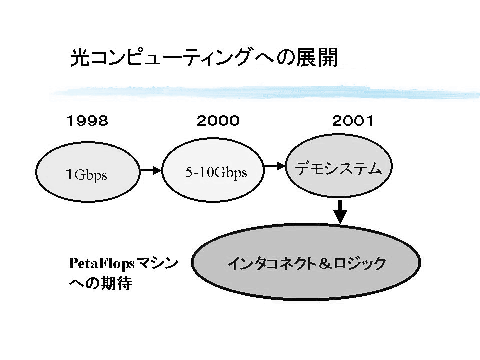
図11
次に分散コンピューティングですが(図12)、私が申し上げるまでもなく、いわゆる分散はつくば研でお作りになっているクラスタから始まってコンプレックス、世界規模のネットワークと、色々なレベルがあると思います。RWC、そして、PDC。これは、先ほどお話になった田中先生が中心になって進めていらして、今から2~3年前に終わった重点領域研究の後期計画です。それらも含めてクラスタからコンプレックスに至る研究は非常によくされていますが、その後に続くというか、それと並行してグローバルコンピューティング、分散コンピューティングにこれから力を投じていく時代になってきているのではないかと思います。アメリカでは現在、イリノイ大学のNCSAが中心になって進めているNCSAというネットワークコンピューティングのプロジェクトがあります。このプロジェクトの一般名称がアライアンス、またはパッキー(PACI)ですね。要するに高速ネットワークで高速計算機をつないで、新しい応用を開こうというプロジェクトが現在進んでいます(図13)。
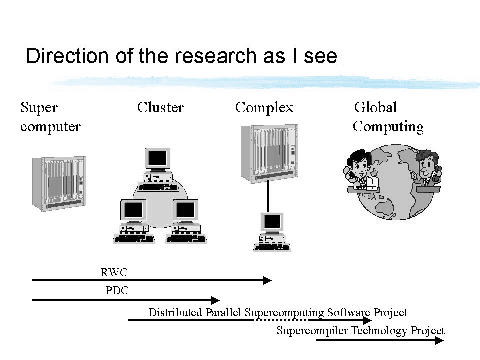
図12
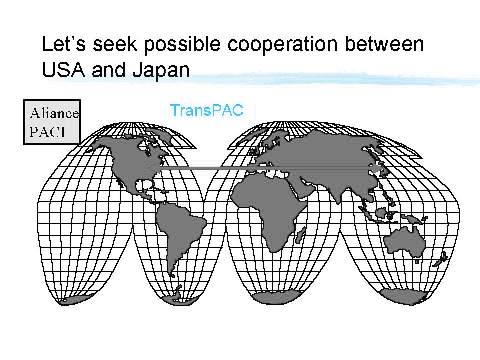
図13
そういったプロジェクトも横目ににらみながら、今年の夏から日本とアメリカをつなぐリサーチ用のネットワーク、トランスパックが、間もなく開通いたします。現在このトランスパックに色々な研究グループが参加していますが、このトランスパックを使って私が次の世代の夢として考えていることを最後に申し上げたいと思います。
三つの方向を考えています(図14)。一つは「情報を探す」方向、二つ目は「データベースと処理の共用」の方向、三つ目は「協調空間を作る」という方向です。

図14
まず情報ですが(図15)、申し上げるまでもなく、Webの世界ですね。Webの世界を考えた場合、次のステップとして少なくとも二つの方向を考えたい。一つは情報をより速く集めたい。ご存じのようにサーチロボットで集めてくるという技術はあります。しかし、サーチロボットでは、現在、日本全国の情報を集めるのに大体数ヵ月かかります。世界全部集めるのにどれぐらいかかるのか。世界中のWebページを1時間以内に集めたい。ご存じのようにこの世界は非常に動きが早いですから、昨日あったリンクは今日はなく、昨日なかった情報が今日あるといった状況です。もう一つは、文字ベースのリンクも大事ですが、情報はだんだんマルチメディアになってきています。Webの世界も当然マルチメディアになってくるわけですから、文字主体の検索からマルチメディア検索へ展開させたい。
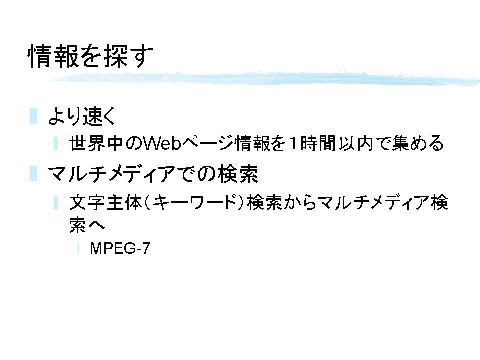
図15
分散ロボットを使うとすると(図16)、当然速くするために分散ロボットをたくさん置いて同時に探すという、ある意味では並列処理の基本を行うわけです。日本全国を調べる場合、例えば、京大、早稲田、電総研、東大と、4ヵ所で現在実験を行っているのですが(図17)、それぞれの場所から日本全国を調べる。
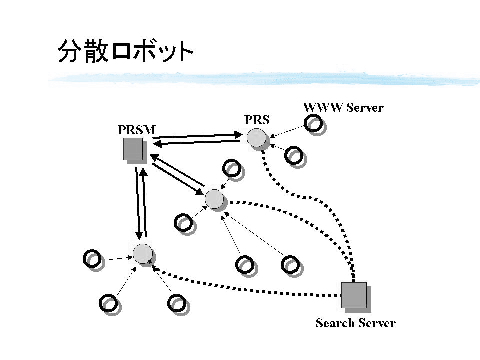
図16
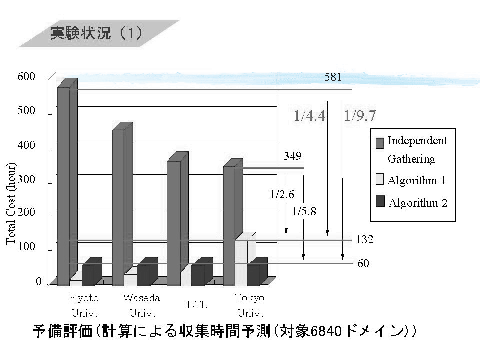
図17
京都で調べると600時間ですから、約200何日、東京大学ですと400時間。それぞれの組織のネットワーク状況によって違いが出てきます。その違いは、この実験では9.7倍、約10倍という結果になりました。なぜノンリニアがスピードアップになるかというと、ネットワークの効果です。それぞれの組織が得意なというか、ネットワーク的に近い所が違っていますので、それぞれを分担させることによって速くなる。例えば早稲田大学でいうと、現在、早稲田大学からは、ワイドは非常に遠くなっています。それぞれの組織に得意、不得意があります。現在これを1時間でやるためにはざっと計算すると50台を日本全国にばらまけばよいということで、50台ばらまいて今年中に実験をやろうと思っています。
マルチメディアの検索ということで言えば(図18)、文字だけではなく音楽もWebの中にたくさんありますし、画像、映像も多いので、Webのリンクを越えるような新しい情報空間を作っていきたい。そのためには、マルチメディアの情報検索をやっていかなければいけないと思います。
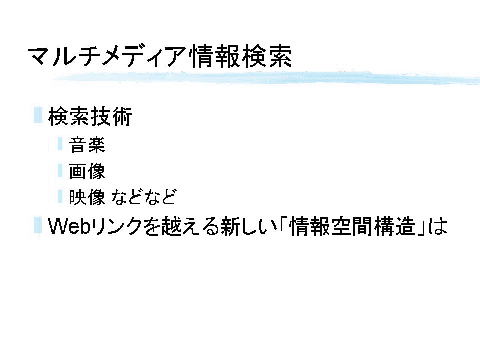
図18
これは一例ですが、うちの学生による音楽の検索(図19)。カラオケの検索と思っていただければいいと思いますが、ハミングすると歌が出てくるということで、この場合は99%正しく検索できます(図20)。ただこれについては、被験者12人の中に音痴の人がいるかどうかは聞き漏らしました。多分いないだろうと思っています。
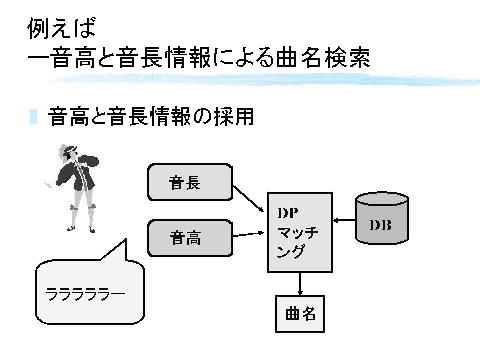
図19
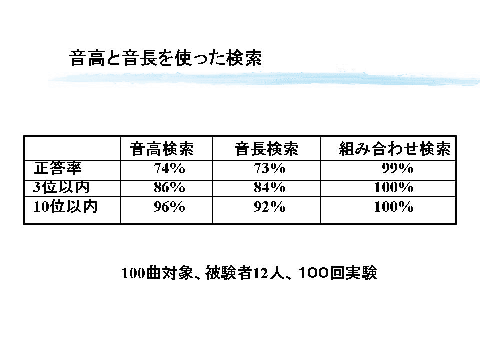
図20
それから2番目のデータベースと処理の共用(図21)。現在、ネットワーク上での分散コンピューティングは当然いろいろなところでやっていますし、Webコンピューティングということで、Webにアクセスするとアプレットを送って、そのアプレットで色々なところで計算パワーを盗むというか、借りるというような仕組みもあります。しかし、最終的にネットワークの世界で分散して何が嬉しいかというと、計算パワーを借りるのもさることながら、データベースを借りるのも嬉しいわけですね(図22)。例えば「宣戦布告」という今話題になっている本があります。その中にも関係することが出ていますが、原子炉が破壊したらどういうことが起こるか。当然汚染が広がるわけです。シミュレーションをしようと思うと、気象情報、原子炉の情報、色々な情報が必要です。それぞれどこに情報があるかというと、気象情報は気象庁ですし、原子炉はまた違う。この場合、多少ナショナルセキュリティー的な問題もありますから、これが良い例かどうかわかりませんが。例えばそれぞれのサイトが持っている得意のデータを、希望する形で料理して提供してくれるような仕組みができれば、ある種の気象情報のシミュレーションの実験をやってみよう、または勉強をやってみようと思う時にできるわけですね。そういうような世界ができてこないか、そういう世界をつくりたいというのが2番目です。
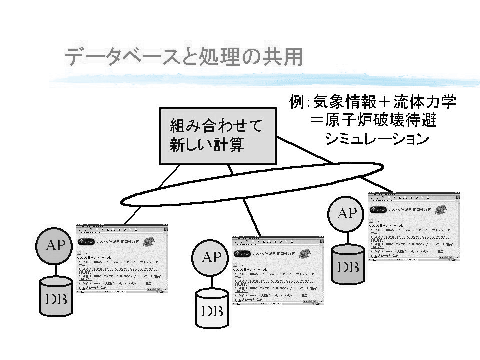
図21
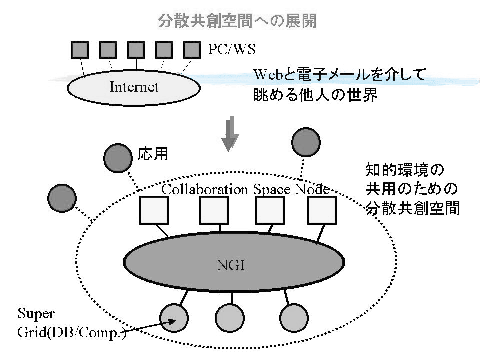
図22
最後は、分散共創空間ということです(図23)。
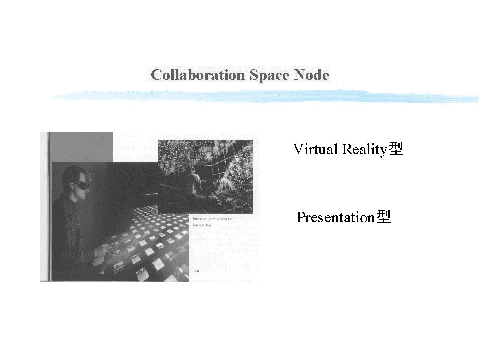
図23
現在のネットワークの世界は、どちらかというとWebと電子メールで小さな覗き窓からネットワークの世界を眺めているような状況ですが、当然、環境も共用したいわけですね。最近、街角にテレビカメラを置いて、それをインターネットで眺めるというシステムがあります。たまたま昨日さるところで聞いたら、現在、世界中で4000位カメラがあるそうですが、これ自身が恐ろしいことではあるなと思います。馬鹿面して歩いていると誰かに見られてしまうというのはちょっと恐ろしい気もします。いずれにせよ空間を共用するということはどんどんあたりまえになってきています。それをもっと押し進めていくとどういうことになるだろうか。例えば、違う場所にいても同じ研究室にいる、違う場所にいても同じ仕事の環境ができる、という状況になるわけです。そうすると従来の端末という概念ではなくて、むしろスクリーンであり、部屋であり、またはオープン・スペースであるというような新しい端末環境、というよりもスペース環境というようなものが出てきて、それをつないだ共創空間というものができてくる時代ではないかと思います。ここに挙げたのは(図24)バーチャルリアリティ、例のケーブルのシステムです。これは本のようなスクリーンですね。応用を考えれば色々楽しいものが出てくると思います(図25)。
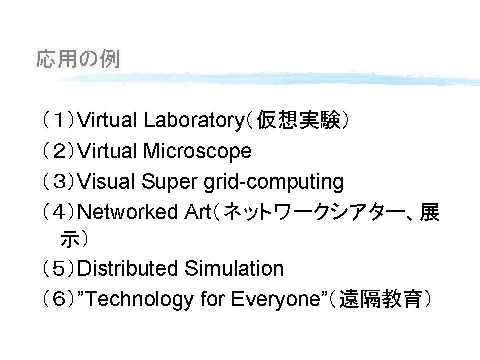
図24

図25
バーチャルラボラトリとか、ネットワークのシアターとか、または、分散してシミュレーションを行うとか、要するに協調して仕事をする。単に協調してディスカッションするというのではなくて、協調して仕事をする、そういう環境がでてくるだろうと思います。
まとめますと(図26)、つくば研を始めとしてRWCは、先ほども言いましたように、私個人としてのA,D,Gの夢を満たしているということで敬意を表したい。これからも是非そういうプロジェクトが多発して欲しいと思います。
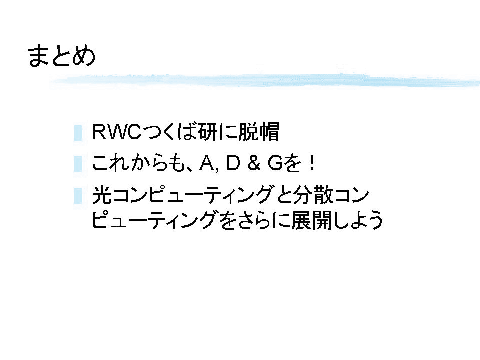
図26
最後は、多少我田引水になるかも知れませんが、そういうプロジェクトの中で、やはり光コンピューティングと分散コンピューティング、これは私自身として興味がありますということを申し上げて、終わりとさせていただきます。
|