並列分散システムアーキテクチャつくば研究室
並列分散システムアーキテクチャつくば研究室
室長 工藤 知宏
並列分散システムアーキテクチャつくば研究室は、平成9年度に新規に設置された研究室です。現在室員は2名で、TRCの中で一番人数の少ない研究室です。分散研、再委託先のご協力を得て、研究開発を行っています。
TRCにある並列分散システムの3研究室では、協力してローカルエリアのシームレス並列分散コンピューティングシステムを開発しています。これは、ビル内、フロア内などのLAN環境に分散して配置された多数の計算機を使って、効率のよい並列処理を行おうというものです。このシステムが実現すると、近年高性能化、低価格化が著しい商用のパーソナルコンピュータを使って、安価に高性能計算環境を構築することができます。
また、今日のオフィスや研究所では、多くのパーソナルコンピュータなどが設置されています。しかし、これらの計算機の計算能力を最大限使用している時間は限られています。シームレス並列分散コンピューティングシステムでは、この現在利用されていない計算パワーをネットワークを通して組み合わせて利用することができるようになります。
このようなシステムを構築するためには、ソフトウェア、ハードウェアともに様々な技術開発が必要です。既存の計算機は、相互に接続して並列処理を行うことを想定して作られてはいないため、解決しなければならない技術課題が多数あります。その中で、当研究室が対象としているのは、
(1)相互の通信には、多くの場合システムコールを伴う。既存のオペレーティングシステムでは、システムコールには大きなコストを伴うため、並列処理を行うには遅延が大きすぎることが多い。
(2)計算機内部の情報の通信能力に比べて、計算機外部との通信能力が小さい。
という問題点です。
(1)については、TRC内の他の研究室と協力してシステムコールを伴わないユーザレベル通信を実現する、軽量メモリベース通信プロトコルの策定と、これを高速にサポートするネットワークインタフェースの開発を行っています。ネットワークインタフェースは各計算機に装着するプロトコル処理と通信を行う装置で、多くの種類の計算機を接続するために、現在広く使われているI/OバスであるPCIバスに装着します。ここで行うプロトコル処理をハードウェア化することによって高速化し、システム全体の性能の向上を図ります。メモリベース通信を用いることにより、マルチタスク環境の通信で重要である保護機能を仮想記憶の拡張により実現でき、また、異機種間を接続する際に、統一された通信モデルを提供することができます。このメモリベース通信をユーザレベルで行うために、保護機能をネットワークインタフェースがサポートします。
(2)については、ネットワークの開発を行います。分散研にご協力頂き、スイッチと計算機間、スイッチ相互間をつなぐリンクには光インタコネクションを用います。光通信には、電気信号による通信と違って、ノイズなどによる距離の制約が少ないという大きな特徴があります。このため、分散して配置されたLAN環境の計算機群を接続する高速ネットワークを構成するのに向いています。この光インタコネクション間のスイッチングを行うネットワークスイッチを開発し、軽量メモリベース通信に適した高速、低レイテンシなネットワークを構成します。このスイッチにはDRAM混載ASICを用います。LAN環境ですから、従来の超並列計算機や多くのSAN(System
Area
Network)のように接続形態(トポロジ)に厳しい制約があるネットワークでは、拡張性が低く、大変使いづらいものになってしまいます。しかし、パケットの消失を許す現在のLANのようなネットワークでは、効率のよい並列処理を行うことは困難です。パケットの消失を許さず、低レイテンシでデッドロックしないネットワークを実現するには、多数のパケットを格納できるバッファが必要です。特に高速ネットワークでは、そのバンド幅を最大限に生かすためには、必要なバッファの量は膨大になります。そこで、DRAM混載の大容量のメモリを持つことができるという性質を生かし、広いバンド幅を持ち、デッドロックフリーで接続形態の制約が緩やかなネットワークの実現を目指しています。
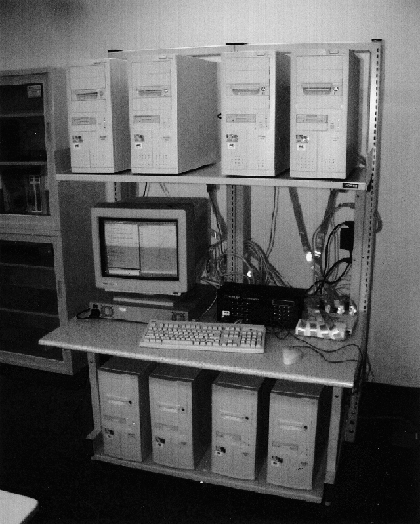
Myrinetを用いたエミュレーション環境MLC/Myrinet
このようなシステムの実現に向けて、平成9年度はMyrinetを用いたエミュレーション環境を構築しました。この上で、プロトコルのエミュレーションを行い、実際に並列処理プログラムを動かしてプロトコルの評価・改良を行っています。また、再委託先と協力して、内部回路の構成を自由に変えることができるLSIであるPLD(Programmable
Logic
Device)を用いたネットワークインタフェースの開発と、ASICによるネットワークスイッチの設計を行いました。このASICは、DRAM混載ではありませんが、将来のDRAM混載ASICの開発を想定して、外付けするRAMによりDRAM混載ASICの機能をエミュレーションするようになっています。平成10年には、これらのネットワークインタフェースおよびスイッチを用いて一次試作システムを稼動させ、システムの性能を実証すると共にハードウェアの構成方式を検討します。
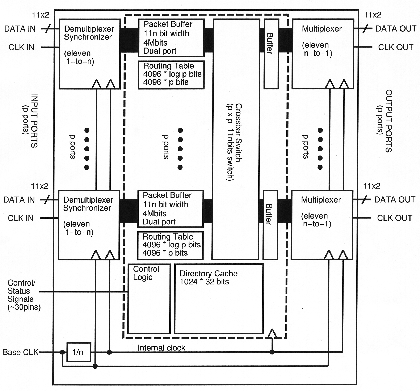
DRAM混載ASICを用いたスイッチの構想
計算機システムの構築には、アーキテクチャとソフトウェアの研究者の協力が不可欠です。また、計算機システムへの光インタコネクション技術の活用は大きな可能性を持っています。今後も、TRC内外の各研究室および再委託先と協力して、様々な分野の研究者が協力できる新情報処理開発機構でこそ可能なシステムの実現を目指していきたいと考えています。
|