シームレスコンピューティング
━並列分散コンピューティング技術分野の目玉 ━

|
RWCP常務理事兼研究所長
島田 潤一 |
大規模な研究所や特殊なオフィスでは、コンピュータパワーに対するニーズは年々強くなってきています。では、小さな研究室や一般的なオフィスではどうかと言いますと、永久にワープロだけでいいということはありますまい。やがてはスパコンを使いたくなるでしょう。それが歴史の教えるところです。しかし、スパコンを導入しようとすると、お金の他に、それなりの場所が要りますし、エアコンも増強しなければなりません。小さな研究室や一般的なオフィスでは難しいことです。
ところで、そのような職場でもかなりの数のパソコンやワークステーションが使われているはずです。それらコンピュータの一つ一つのパワーは小さなものかもしれませんが、全部合わせると大したもののはずです。スパコン並かもしれません。しかし、ひっきりなしにキーボードが叩かれているかというと、そうでもありません。その意味ではそれらコンピュータは、ほとんど遊んでいるのです。言うなれば、スパコン並のパワーが遊んでいるのです。ですから、これらをうまく結んで空いている時間を利用すれば、小さな職場でもスパコン並のパワーが得られるはずです。ということで、つくば研を中心に2年前から発想・策定され、当プロジェクトのこれからの目玉の一つとして採り上げられることになりましたのが、ここに紹介いたしますシームレスコンピューティング技術開発計画です。
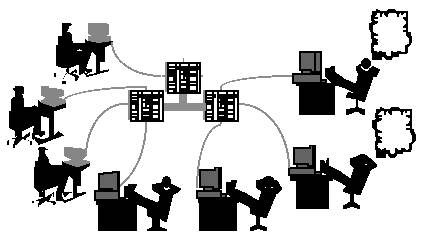
では、どうすればこのようなことができるようになるでのしょう?まず第一にコンピュータ同士が通々でやりとりできるようにならなければなりません。そのためには、今やっているような「rlogin
・・・」といった呼び出し操作を無しにしなければなりません。つまり、お互いがつなぎ目なしに結ばれなければなりません。これが「シームレス」という名前の由来の一つなのです。
次に、よそのプロセサやメモリが自分のと同じように見えるようにしなければなりません。例えば、他所のメモリを読んだり、そこに書いたりできるようにしなければなりません。それどころか、アクセスも同等な早さでできなければなりません。そのためにはコンピュータ間の通信線もコンピュータ内での通信線とほぼ同じ性能のものにしなければなりません。ちょうど都合良く、光通信技術がコンピュータ用にも使えるようになってきました。
大事なことがあります。一つの職場で誰もが同じ方式のコンピュータを使っているとは限りません。しかも、新しい機種が出ると買い換える人もいます。また、新しい人が来て、台数が増えることもあります。ですから、アーキテクチャの違いを乗り越え、台数の増大に対応できるソフトを開発しなければなりません。データの形式の違いを吸収する仕組みも必要です。
さて、パソコンを結んでスパコン並にするとは言いましたが、どう結べばよいのでしょう?言うところの「スパコン」は特別なプロセサが必要ですから、そのようなものにはなりません。小規模なプロセサを集めて、ということですから、自然に「並列コンピュータ」ということになります。こうしてできるのがシームレスコンピュータシステムです。つまり、シームレスコンピュータシステムというのは、各人の机の上に配置され、普段は独立に使われている各種のコンピュータが必要に応じて一つの並列計算機となるシステムなのです。
以上のようなことで、とりあえずは小さなグループでも並列システムを使えるようにし、そこここで並列プログラムが開発されるようにし、やがては「オフィス・スーパーコンピューティング」が可能な時代を切り拓こうというのが本計画の目指すものです。
日本発のトレンドになれば、と頑張っております。
|