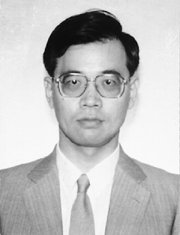
|
斎藤 稔
-並列応用つくば研究室- |
プロフィール
| 所属:
|
RWCPつくば研究センタ並列応用つくば研究室 |
| 生年月日:
|
1954年11月21日 |
| 出身地:
|
埼玉県八潮市 |
| 略歴:
|
1985年名古屋大学理学部物理学科博士課程修了
:1987年名古屋大学理学部物理学科助手
:1988年蛋白工学研究所主任研究員
:1996年4月より現職 |
私は、去年の4月から並列応用つくば研究室で、計算化学分野の分子動力学シミュレーションの並列計算を担当しています。私の研究経歴は、RWCの他の研究者の方と少し違いますので、この紙面を利用して、私の研究のバックグラウンドについてお話をしたいと思います。
私は、学部、修士課程、博士課程を、いずれも理学部の物理学科の理論系の研究室で過ごしました。茨城大学の学部では、浜田哲夫先生から、量子力学、統計力学、古典力学などの物理学の基礎理論を学びました。浜田先生は、日本に電子計算機がまだ無い頃オーストラリアのシドニー大学にいて、フロア一杯の真空管の電子計算機を使ってハマダジョンストンポテンシャルという核力のポテンシャルを作ったそうです。修士課程は、金沢大学の物性理論の樋渡保秋先生の研究室に進みました。樋渡先生は、日本における分子動力学シミュレーションの草分けの一人で、分子動力学シミュレーションを単にシミュレーションと呼ぶのを好まず、計算機実験と呼び、当時から実験と理論のどちらでもない第3の研究手段であると公言していました。
ところで、私は、物理学を学ぶにつれて、個性や意志を持たない原子の集団から、なぜ生命を持った生物ができているのか不思議に思うようになりました。原子の集団の振舞いを記述する物理学を使って、生命の営みの一端を理解したいと思うようになりました。そういう希望をかなえるために、博士課程は、名古屋大学理学部物理学科の理論生物物理学研究室(右衛門佐重雄先生)に進みました。右衛門佐先生は、日本生物物理学会の創設に関わった一人で、若いときに、手回し計算機を使って蛋白質の主鎖のバンド計算を世界に先駆けて行ったそうです。私が入った頃、化学の分野では、経験的パラメータを一切使わない非経験的分子軌道法が小さな分子について行われつつありました。この方法は、厳密なのですが計算量が膨大です。私は、非経験的分子軌道法を身に付けて、生体分子の電子状態の計算をするために、分子科学研究所の計算機センターの柏木浩助教授(現在、九工大教授)のもとに修行に出ました。柏木先生は、その当時の大型計算機の一台のメモリとディスクのすべてを使って、鉄ポルフィリン錯体の非経験的分子軌道計算を行っていました。私は、柏木グループの数万行のプログラムを改良し、鉄ポルフィリンの電子状態による安定構造の違いを計算しました。私の計算結果は、実験値に合わせるパラメータが一切無いにもかかわらず、実験による観測結果とぴったり一致していました。どんなに計算時間がかかろうと、第一原理からまじめに計算をすれば、自然界の振舞いを正しく記述できることを体験し感動しました。
ちょうどその頃スタートした蛋白工学研究所(通産省の10年プロジェクト)にプロパーの主任研究員として参加しました。当時、全ての蛋白質の分子動力学シミュレーションは、困難な計算を端折って行われていました。私は、端折らずに正確に早く計算する方法を考案し、新たにプログラムを開発しました。そのプログラムと蛋白工学研究所のスーパーコンピュータの能力を限界まで使って、不可能だった蛋白質の性質の正確な計算ができるようになりました。コンピュータの処理能力のぎりぎりを使って計算するのは、浜田先生、桶渡先生、右衛門佐先生、柏木先生の影響かもしれません。しかし、コンピュータが進歩しても、その能力の限界を使って計算しなければならないのは、いつの時代も計算物理学や計算化学は最高速の計算機を必要としているからなのです。
|