海外出張報告
| 出 張 者:
|
鬼塚 健太郎(並列応用つくば研究室) |
| 期 間:
|
1997年6月21日~6月25日(5日間) |
| 参加会議:
|
分子生物学のための知的システムに関する第5回国際会議
(ISMB '97)(ギリシャ) |
6月21日より5日間、「分子生物学のための知的システムに関する第5回国際会議(ISMB '97)」が開催された。
1993年に米国国立衛生研究所(NIH)の Larry
Hunter等の呼びかけでNIH(ワシントンDC)で開催されたISMBは、米Stanford、英Cambridge、米St.
Louisと場所を変えて毎年開催され、第5回目となる今年は、ギリシア北部のリゾート地Halkidikiでの開催となった。
Halkidikiはアレクサンダー大王の古代マケドニアの地、ギリシア第二の都市Thessaloniki
から100キロほど南東、三つある半島のうちの中央に会場となったホテルがある。
海に面したホテルから波のないエーゲ海に臨み、夕日を仰ぎ思索にふければ様々な発想が湧いてくる。2500年前に自然哲学を隆盛させたギリシアは、今でも思索するには最適な場所だ。
「ギリシア製自動車っていうのは走ってないが、俺たちには歴史がある。」Thessalonikiと会場を結ぶタクシー運転手の言葉。経済成長、大規模物質文明という目標に向けて発展してきた現代先進諸国の活躍も、古代繁栄の地の人々には、単なる歴史の1コマに過ぎないのかもしれない。
そんなギリシアで開かれた今回のISMBは、計算環境、ネットワーク環境の爆発的な発展の中で翻弄されている研究者にとって、潤いを取り戻すには良い機会だっただろう。
ISMBが最初に開かれた1993年当時、人工知能研究者の間では分子生物学は最も有望な応用分野だと思われたし、分子生物学研究者も「人工知能」は全てを解決しそうな気がした。両者が一堂に会して両分野融合についての熱い討論が繰り広げられた第1回ISMBは、どちらの研究者にも刺激的な場であった。第2回になると、しかし、雰囲気は違っていた。分子生物学者は人工知能が夢のような技術ではないことを知り、情報系の研究者は分子生物学を応用分野とするには膨大なお勉強の必要性があることを知った。残ったのは、地道な研究に耐えることのできる人たち、基礎からデータを収集し電子化し、ネットワークでの利用や情報検索手法を確立することができる人たち。タンパク質の立体構造予測問題、代謝反応経路問題、細胞分化の制御機構といった難問は、計算機科学者にとっても難しかった。
今回の会議では、人工知能研究や先進的な情報科学を分子生物学に応用した研究報告はほとんど無し。データベース作成や論文内容解析システムの開発などの内容が中心だった。画期的、挑戦的な研究報告の無かった今回は、やはり物足りなさを感じる。
会議出席の後、スイスのチューリッヒにあるETH
SCSC(スイス科学計算センター)を訪問し、計算化学系の研究者と討論を行った。分子生物学における蛋白質配列解析を行っている研究者もいた。彼らはISMBなどの会議のコミュニティには属さず、独自に研究を行っていた。それはそれでよいけれど、一方で、ISMBに参加した研究者等のコミュニティは、地道に研究環境、研究インフラを改善している。彼らと関係をもつことのできる我々にはやはり利ありといえる。そこが重要なのだ。
夢はまだ終っていない。一見して、しぼんでしまったかに見えるこの分野は、試練のときを越えて、やがて再び羽ばたくときが来るだろう。より進んだ計算ネットワーク資源が実現すれば、地道な研究成果は大いに活かされる。ISMBの参加者は毎年増加している。初期にこの分野に進出した計算機系研究者の存在は、これまで生物学に無縁だった多くの計算機系研究者を呼び込む結果になった。同じように計算機に無縁だった生物学者が計算機を使い始める状況にもなった。そんな中で新しい研究の芽も、少しずつだが生まれ始めている。今回のギリシアでの会合は、なにかを残すに違いない。今回の海外出張は、数年前の隆盛から停滞期を経て、再び発展する前の過渡期にあって、いろいろと考えさせられるものだった。
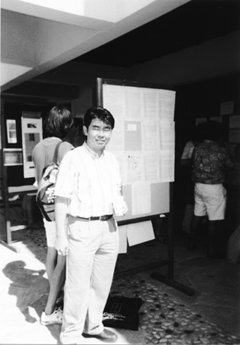
|