実世界知能技術分野の研究開発
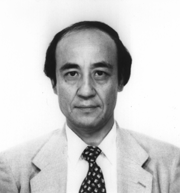
|
実世界知能研究推進センター長
(電子技術総合研究所 知能情報部長)
大津
展之
|
知能の論理的な側面を手本として発達したコンピュータによる情報処理は、生活の様々な場面に浸透しつつあり、マルチメディアやインターネットに代表される情報インフラも目覚しい発展を遂げております。今日の情報技術は、想定された情報世界で予め定められた手順に従って情報を高速に処理する能力においては、確かに極めて強力です。しかし一方で、人が日常行っている柔軟な情報処理、つまり不確かさや曖昧さを含む実世界の多様な情報を総合し判断したり、処理機能自身を状況に適応させたり学習的に獲得していく能力については、未だ不十分です。情報インフラの発展で、記号のみならず画像や音声など多様な実世界情報を生成、表示、伝達する処理能力は飛躍的に伸びていますが、それらの情報を統合し、要約、理解する機能が遅れています。また、GUIの先に期待されるコンピュータとの対話(インタフェース)も、音声や身振りの理解を含むより日常的で自然な形が望ましく、ロボットが工場から実世界へ出ていくにも、情報統合と学習機能に支えられた自律性が必要です。このように、変化する多様な実環境(実世界)で破綻無く機能し、しかもユーザとの親和性の良い知的情報処理、いわば「実世界知能」が、今日の情報処理技術の弱点であり、新しい可能性と応用を切り拓く上での共通の隘路となっています。
次世代情報基盤技術開発事業における実世界知能技術分野の研究開発は、従来の情報処理技術にこうした「実世界知能」、すなわち情報統合・学習型情報処理能力を付加するための基盤技術を開発し、情報処理の可能性と応用分野の拡大を図ることを目的としています。情報統合と学習・自己組織化については、これまでにも個別的な研究はなされてきましたが、実世界知能の基礎としての新規性と課題は、むしろこれらの機能の一体的で総合的な実現にあります。さらに認識や推論と言った機能と一体化して扱う必要があります。そのための理論的な枠組み、方法としては、実世界の不確かな情報を扱う意味でも、多様な事象間の共起頻度や相関、さらにはベイジアンネットなど、確率統計的な手法が重要だと思います。こうした情報統合と学習・自己組織化の機能を共通の柱として、理論基盤の研究と実際の応用場面に即した研究開発とが蜜に連携する体制が重要です。そこで、実世界知能の応用場面を、大きく情報要約、対話、行動の3つに分けて、それぞれ具体的なプロトタイプシステムに即して研究開発を進め、実世界知能の本質的な問題の解決と機能実証を行う。さらに、これらの研究開発をハードとソフトの両側面から支援し、加速、評価するために、進化ハードウェアといった新しい適応デバイスの開発や、実世界の各種データベースや共通手法のライブラリといった知的資源の整備も重要であり、図に示すような研究開発体制となっています。
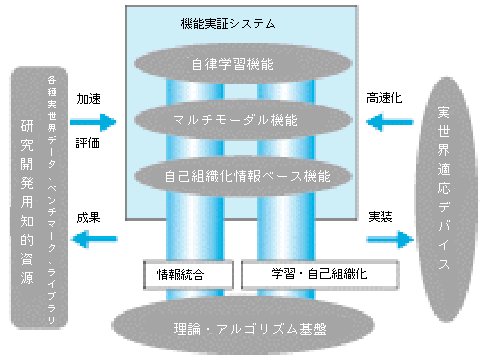
電総研は、今年4月から従来の研究室制を廃止し、よりミッション指向の強いラボ制に移行しました。これに伴い、本プロジェクトに関して8つのラボからなるスーパーラボ「実世界知能研究推進センター」を構成し、特に実世界知能技術分野の研究開発を先導すべく新たな体制で研究を進めております。実世界知能分野では、それぞれの領域毎のワーキンググループ、領域間の連携会議を通して、産官学の連携のもと、国際的な視野で実世界知能の研究と技術の流れを起こして行きたいと思っております。
|