PCS'97/SWoPP阿蘇'97の報告
| 参 加 者:
|
安藤 誠(並列分散システムパフォーマンスつくば研究室) |
| 期 間:
|
1997年8月18日~8月22日(5日間) |
| 参加会議:
|
HPCS '97(ハイパフォーマンスコンピューティング・シンポジウム 1997)
SWoPP阿蘇
'97(1997年並列/分数/協調処理に関する「火の国」サマー・ワークショップ) |
まだまだ残暑がきびしい8月の下旬、HPCS '97/SWoPP阿蘇
'97が南国熊本・阿蘇で開催されました。熊本は暑いだろうと少々心配していましたが,会場のグリーンピア南阿蘇は阿蘇の外輪山に位置していることもあって、予想に反してとても過ごしやすい気候でした。
■HPCS '97
HPCS
'97(ハイパフォーマンスコンピューティング・シンポジウム1997)は、情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会の主催によるシンポジウムで、8月18日に開催されました。午前の部では、RISC計算機とHPCプログラミング、そしてHPF言語の最近の動向に関する2件のチュートリアルが行われました。また、午後の招待講演の部では並列計算機による流体解析といったアプリケーションレベルのテーマから、プログラムの実行時並列化といったアーキテクチャレベルのテーマに至るまで、様々な分野の講演が行われました。特に午後の招待講演では、ハイパフォーマンスコンピューティングに関する技術を概観することができ、非常に有意義でした。
■SWoPP阿蘇 '97
SWoPPは、毎年夏に開催される並列/分散/協調処理に関するサマー・ワークショップで、日本の並列/分散処理に携わる研究者が一堂に会し、活発な議論が行われる合同研究会です。第10回を迎える今夏は、SWoPP発祥の地「阿蘇」で8月19日~22日に開かれました。
「並列/分散/協調処理」を横断的なキーワードとして、情報処理学会・電子情報通信学会の6つの研究会が同時に開催されました。発表は合計で127件(大学97件、企業14件、国立機関他16件、新情報は国立機関他に含まれる)で、参加者は265名でした(45大学202名、11企業36名、4国立機関他27名)。新情報からは、11件(集中研7件、分散研2件、実習生等2件)の発表がありました。
筆者は、初日の午後に行われた情報処理学会ハイパフォーマンスコンピューティング研究会の「性能評価」というセッションにおいて、「Knapsack問題における共有メモリ型/分散メモリ型並列計算機の性能比較」と題して発表しました。同セッションでは,田中主任研究員(並列分散システムパフォーマンスつくば研究室)による「SMPクラスタでの共有/分散融合プログラミング」の発表も行われました。本セッションは、並列/分散処理に関わるたくさんの研究者から注目を浴びていたようで、会場は聴講者であふれていました。
今回筆者が発表した研究は、木探索問題の典型例であるナップサック問題を用いて、共有メモリ型と分散メモリ型の並列計算機の性能を特徴づけるというものです。一般に木探索問題を解く場合、探索空間の大きさや探索処理の並列度は入力データに大きく依存します。そこで本発表では、まず入力データをいくつかのカテゴリに分類し、並列計算機の性能の解析を入力データの分類に従って系統的に行ったことを強調しました。このため、発表後の質疑応答においては、並列計算機の性能評価方法や木探索問題の解法のアルゴリズム、およびその並列化などについて幅広く活発な議論が行われました。また、2日目の夕方に開催された懇親会においても、様々な研究機関の研究者と意見を交換し合うことができ、筆者にとっては有益な刺激となりました。
今回のSWoPPでは、クラスタを構成するための技術の研究が多く見られました。これらは具体的には、ノード(ワークステーションやPC、SMP等)を接続するための高性能ネットワークの研究や、Myrinet上での既存の通信方式の性能評価や新しい通信方式の提案、クラスタ上でのプログラムのスケジューリング等です。クラスタに関する技術が、並列/分散処理に関わる研究者に注目されている重要なテーマであることを実感しました。
クラスタ技術の他にも、分散共有メモリ、数値計算、アプリケーション等のセッションを聴講し、有意義な5日間を過ごしました。
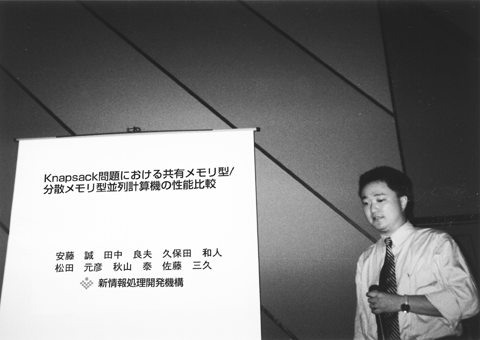
SWoPP阿蘇'97にて発表する筆者
|