海外出張報告
| 出 張 者:
|
田中 良夫(TRC並列分散パフォーマンス研究室) |
| 出張期間:
|
1997年4月27日~5月2日(6日間) |
| 訪 問 先:
|
HPCA(High Performance Computing Asia) '97(ソウル) |
ちょうど日本のゴールデンウィークの前半(と言っても今年は大型連休ではなかったが)に、韓国でハイパフォーマンスコンピューティングに関する国際会議HPCA(High
Performance Computing Asia) '97が開かれた。本稿では、本会議での研究発表および研究交流を目的とした韓国出張に関して報告する。
この会議はATIPのDavid
Kahaner博士が提唱し、アジア太平洋地域の諸国が協力して開いているもので、1995年9月に台北で開かれた第1回に次ぐものである。Tutorial、Technical
Session、Panel Discussion、Round
Table、Exhibitionなど多彩な発表があった。また、今回はIEEEの後援をとりつけたこと、開催会場(Seoul Hilton
Hotel)の広さや設備が充実していたこと、Banquetは國楽藝術團の伝統ダンスが行われるなど盛大であったことなどからも、主催者である韓国の情報通信省の力の入れようがうかがえた。20カ国から720名が集まり、規模の大きな会議であった。
初日の4月28日にはTutorialが開かれた。Tutorialは全日のものが1件、半日のものが10件であり、分散共有メモリシステムの概要からJavaの実践プログラミング技法に至るまで、ハイパフォーマンスコンピューティングに関する様々な分野のテーマが選ばれていた。また、この日にはTutorialと並行してthe
First Cenju WorkshopがNECおよびUniversity of Houstonの主催で開かれていた。
2日目から本会議が始まった。午後に行われたPlenary Talkでは、アメリカのJack
Dongarra教授と日本の小柳義夫教授が講演を行った。Dongarra教授は、アメリカのハイパフォーマンスコンピューティングの現状と、Netsolveを中心としたDongarra教授のグループの活動内容について講演した。小柳教授の講演は、並列アーキテクチャや並列ソフトウェアの現在の動向を述べ、今後の展開を占うという内容であった。日本でも何度か講演を聴講させて頂いたことのある小柳教授の発表であったが、主にアメリカと日本の並列処理研究のシナリオを比較しながら述べられた内容は、大変興味深いものであった。
著者の発表は"A Comparison of Collective Communication Performance and its
Application"と題して3日目の午後に行われた。各種の並列計算機上でのcollective通信の基本性能をデータベースとして保持し、World Wide
Webを通じて外部へデータおよびベンチマークプログラムを公開していることと、そのデータベースの活用法のひとつとして我々が提案したデータ並列プログラムの性能解析手法に関して述べた。Myrinetで接続されたワークステーションクラスタであればParagonやCM-5と同程度の性能が得られることに驚いていた研究者が多かったようである。また、Paragonを使っている研究者からParagonの並列性能特性に関して質問を受けるなど、評判は上々だったようである。実際、Best
Paper Awardの最終候補に著者の論文が選ばれたことが後程伝えられた。
また、Exhibitionには、SGI-Cray、HP、DEC、IBM、NEC、日立、富士通をはじめとする21の企業から出展があり、いろいろな並列計算機に関して説明を受けることができた。各企業とも賞品の当るクイズをやっていたようであるが、すべて韓国語で進行されていたので全く参加することができなかったのが残念である。
以下の写真は、Exhibitionの会場でお会いしたSydney Regional Visualisation LaboratoryのNicole
Bordes博士とBernard
Pailthorpe助教授である。Bordes博士は画像処理が御専門で、RWCのつくば研にも来所なさったことがあるとおっしゃっていた。
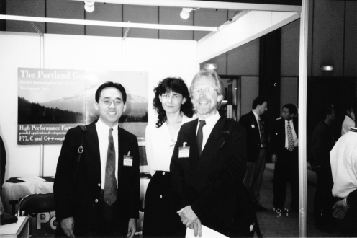
写真右からBordes博士、Paithorpe助教授、著者
最大で5つのセッションが並列に行われたため、聞くことのできなかった発表がいくつかあったことと、発表時間が質疑応答を含めて20分と短かったことが残念であったが、今後の研究活動に向けて数多くのことを得ることができた有意義な5日間であった。
|