新しい並列応用の開拓と並列処理技術の実証を目指して
並列応用つくば研究室長 秋山 泰
■ 並列アプリケーションの重要性
より高速で大容量の計算機を、その時代の標準的な部品で作るには、プロセッサを多数並べる並列処理のアイデアが必須で、今後の主流と考えられています。ハードウェア技術の進展により、近年ではマルチプロセッサ機や超並列機が比較的身近に見られるようになり、「並列処理」は我々のすぐそばまでやってきました。特にワークステーションやパソコンのクラスタ化技術は、並列機を大衆化する突破口になりそうです。
しかし、利用するソフトウェアが並列化されていなければ、得られる速度は従来機と何も変わりません。並列機は、単に多人数の仕事を便利にさばくサーバにすぎなくなり、一つ一つの処理の高速化の観点では、多数あるプロセッサの潜在能力は眠ったままです。
今まさに、実用的な並列アプリケーションを整備していく事が渇望されています。並列アプリの開発は、ハードが提供されれば一朝一夕に済むものではなく、ノウハウの蓄積や、文化としての醸成が重要です。しかし、並列研究はハード先行で進められてきた感が強く、アプリケーション技術面での立ち遅れは深刻です。
■ 研究室のアプローチ
並列応用つくば研究室では、並列応用分野の裾野を広げるための新しい応用の開拓を目指します。また実用的なアプリの開発を通じて、並列システムの価値の実証を行います。具体的には、計算化学と計算生物学の分野にモデル問題を求め、大規模かつ実用的な並列アプリケーションの実証開発を進めています。
計算化学や計算生物学は、現在まさに隆盛しつつある分野であり、流体解析や構造・衝突解析などの先行する並列応用に比べると、並列処理のパワーを活かした手法による、質的なブレークスルーが期待できます。
我々は、研究テーマの選択にあたり、常に次の3つの条件を課す事にしました。1)大規模並列化に適し相当な性能向上が見込めること、2)各分野で即戦力となる実用価値の高い並列プログラムを開発すること、3)我々自身がその応用分野のプロと自認できること。
第一の点は、並列化を検討する際の、しごく当然の出発点です。第二の点「実用性」という主張には、次の考えが込められています。語弊を恐れず単純化して言えば、並列研究者が従来作成した並列プログラムでそのまま実用に耐えるものは少ないと思われます。なぜならば研究の価値観が、並列化効率や並列アルゴリズム自身にあったからです。応用現場で要求される、ドロ臭い拡張機能や、最新の計算モデルへの対応は、開発を引き継いでくれる誰かに任せたい、普遍的でありたいという指向があります。しかし並列応用の恩恵を早く広めるためには、並列技術と応用各分野の間を隔てている「暗くて深い川」の中州あたりまで、双方が泥をかぶって泳ぎ寄る必要があると思われます。
第三の点は、第二の点と表裏一体です。当研究室ではターゲットを計算化学・計算生物学に定めて以来、それらを専門とする室員を募りました。分子動力学法の世界的な研究者、タンパク質二次構造予測の専門家、タンパク質立体構造解析の研究者、ヒトゲノム解析計画の担当者など、幅広い背景と深い専門性をもつ個性的な集団になっています。さながら研究室内は、学際研究の実験場のようでもあります。専門性を崩さずに並列効率も考えながら研究をするのは、正直言って、しんどい仕事ですが、楽しみも2倍かも知れません。
■ 研究内容の紹介
以下では、並列応用つくば研究室で現在すすめている研究内容を、簡単にご紹介します。
(1)タンパク質立体構造予測のための並列システム
アミノ酸配列の情報から、タンパク質の折り畳みを予測するための研究。部分構造予測など複数のモジュールと、共用の並列ライブラリ部を作成中です。(図1)
 図1 タンパク質立体構造の特徴的部位の予測
(2)カットオフをしない精密な並列分子動力学法
図1 タンパク質立体構造の特徴的部位の予測
(2)カットオフをしない精密な並列分子動力学法
溶媒中のタンパク質の挙動を精密に追跡するため、PPPC法に基づく分子動力学法を並列化しています。(図2)
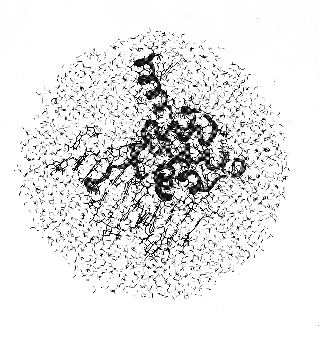 図2 水中でのタンパク質とDNAの分子動力学計算
(3)精密な進化系統樹作成の並列化
図2 水中でのタンパク質とDNAの分子動力学計算
(3)精密な進化系統樹作成の並列化
最尤法による精密な系統樹作成と、きわめて精度の高いマルチプルアライメント処理を並列化しています。
(4)宇宙プラズマ粒子シミュレーションの並列化
電磁場中の粒子運動の一次元シミュレータが完成。
静電孤立波(ESW)問題では、従来1ヶ月を要していた計算を、3時間(256台並列の場合)で行えるようになりました。(図3)
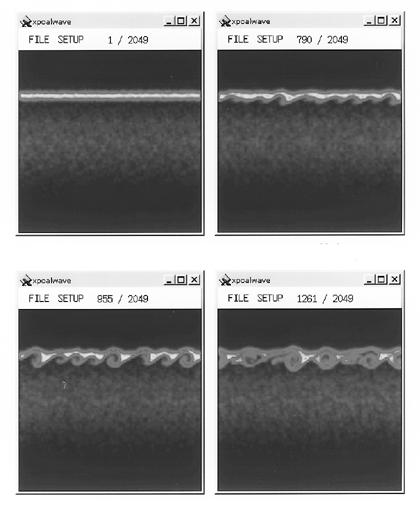 図3 宇宙プラズマ粒子シミュレーションで明らかになった地球磁気圏の静電孤立波(ESW)の発生メカニズム
タンパク質の立体構造予測は難しいテーマです。分子動力学法でタンパク質の現象を数ナノ秒は追跡可能ですが、折り畳み現象はミリ秒前後ですから、少なくとも百万倍の高速化が必要です。我々は並列分子動力学法により、タンパク質のマイクロ秒オーダーの現象に迫ることを目指していますが、折り畳み現象の直接シミュレーションにはまだまだ手が届きません。そのような力任せの方法だけでなく、αヘリックスやβシート等の部分構造の予測、各残基の内外性の統計的な予測、マクロな粒子モデルでの粗い力学計算、既知のフォールディングからの類推などの統計的・知識的な手法との並列統合化により、安定解探索を加速する方法が有望でしょう。個人的には、問題の一部を大規模な組合せ最適化問題へ帰着して解くことに興味をもっています(詳しくはRWC
NEWS,Vol.6,P.14の記事もご参照下さい)。
図3 宇宙プラズマ粒子シミュレーションで明らかになった地球磁気圏の静電孤立波(ESW)の発生メカニズム
タンパク質の立体構造予測は難しいテーマです。分子動力学法でタンパク質の現象を数ナノ秒は追跡可能ですが、折り畳み現象はミリ秒前後ですから、少なくとも百万倍の高速化が必要です。我々は並列分子動力学法により、タンパク質のマイクロ秒オーダーの現象に迫ることを目指していますが、折り畳み現象の直接シミュレーションにはまだまだ手が届きません。そのような力任せの方法だけでなく、αヘリックスやβシート等の部分構造の予測、各残基の内外性の統計的な予測、マクロな粒子モデルでの粗い力学計算、既知のフォールディングからの類推などの統計的・知識的な手法との並列統合化により、安定解探索を加速する方法が有望でしょう。個人的には、問題の一部を大規模な組合せ最適化問題へ帰着して解くことに興味をもっています(詳しくはRWC
NEWS,Vol.6,P.14の記事もご参照下さい)。
難しいテーマ設定なので、我々は常に研究協力者を求めています。
|