テクニカルセッション
印象記
光システム分野 光デバイスとシステム
筑波大学 物理工学系
教授 谷田貝 豊彦
光技術は、通信やメモリーの世界では大きな発展が見られたが、情報処理の分野では未だに、“期待”の段階にとどまっているように見える。光コンピューティングや光インターコネクションの夢が語られてから久しいが、最近ようやく、本格的な実用システムを念頭に置いた研究(特に光インターコネクションに関して)が出てきた。これがRWCシンポジウムの光関連の発表を見て感じた印象であった。
RWCシンポジウムの光デバイスとシステムのセッションは、デモンストレーション展示1件、他の14件はすべてポスターによる発表であった。その内訳は、光インターコネクション関連6件、光デバイス関連6件、光コンピューティング関連3件である。以下、筆者の印象に残った論文の幾つかを紹介する。
RWCPでは1024のプロセッサーを接続した超並列コンピュータRWC-1を開発中であるが、このシステムでは、各プロセッサーのスループットは10Gb/sにも達し、既存の配線技術の限界に近づきつつある。この限界を乗り越えるため、光インターコネクションは必須の技術と考えられている。

デモンストレーション展示は、光日立研究所とRWCPつくば研究センタによる、RWC-1テストベッドシステム用の光インターコネクションシステムであった。開発の内容は、12チャンネルの同期型パラレル光ファイバー(シングルモード)伝送用のトランシーバー・レシーバーモジュールの開発と、これを用いた光インターコネクションシステムである。1.3μm帯の12素子集積化レーザーダイオードアレイとフォトトランジスタアレイの開発により、チャンネル当たり250Mb/s、モジュール全体では3Gb/sの性能を達成している。テストシステム(SUTB1-H)では、12チャンネルの上記モジュールを8個用いて、全体では48ビット並列の伝送を100Mb/sで行い、全体で600MByte/sのスループットを実現している。伝送の距離は20mを想定しており、これは銅線系のインターコネクションでは実現不可能である。
光NEC研究所もRWC-1テストベッドシステム用の光インターコネクション技術の発表を行った。このシステムでは、マルチモードファイバーアレイを用いてGb/sクラスの性能を実現している。RWC-1では100Mb/sで48ビットパラレルのインターコネクションが必要であるが、本システムでは、まず、8ビット×6チャンネルのデータに変換し、これを8B10Bのコーディングを行い、10ビット6チャンネルのデータを60
:
6にマルチプレックスする。これを1チャンネル当たり1Gb/sの伝達を行うものである。このシステムを17.5時間連続運転を行い、エラー無しの伝送を行うことができ、10-14以下のBERを実現出来たとしている。
光インターコネクション用のデバイスとしては、面発光レーザー(VCSEL)(光NEC研、光富士通研、光古河研)、面型光アンプ(光東芝研)、ビーム偏向器(光古河研)、レシーバーアレイ(光住電研)が報告された。VCSELに関しては、各々特徴があり、発振波長が1.55μm(光NEC研)と1.3μm(光富士通研、光古河研)のものが開発され、また、マイクロマシン技術による外部共振器を用いて35nmの発振波長チューニングが可能となった(光古河研)。

光コンピューティング関連の発表としては、光ニューラルコンピューティング(電総研、光三菱研)、光ファジー制御(電総研)、並列ディジタル演算(光松下研)があり、光コンピューティング技術の応用にも発展があった。
光三菱研のニューロシステムの報告は、CMOS技術による感度可変光検出器アレイによる人工網膜チップの製作とこれを用いたステレオ写真のパターン相関演算による立体形状の測定実験である。
また、電総研の発表は、全光型のニューラルコンピューティングをめざし、ニューロンの結合荷重が負にならない演算法およびPROMと呼ばれる空間光変調器を用いた学習の段階を光で実現する方法の提案と実験成果に関するものである。また、従来から電総研で開発されているツインストライプ・レーザーダイオードを用いた光ファジー演算法による振り子安定化制御のデモンストレーション結果も報告された。
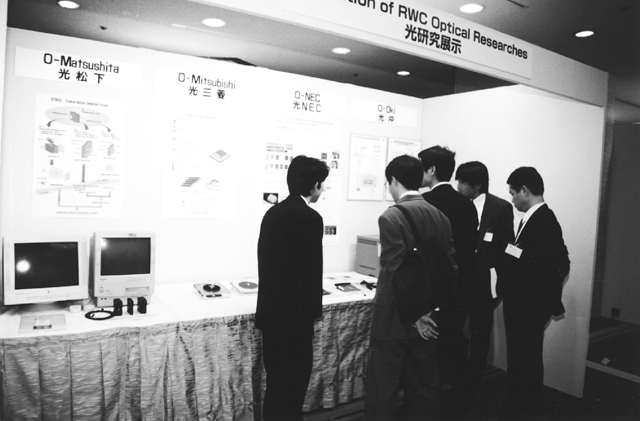
ディジタル光コンピューティングに関しては、光松下研が光ファイバーイメージプレイトなどを積層して、パターンの分岐、重ね合わせなどを行わせて並列演算を実行するシステムを開発した。STOCSと呼ばれるこのシステムを用いたアレイロジックの実現法とこのシステムの構成要素部品である回折光学素子を用いたパターンの4複製器が試作された。
従来から、光コンピューティング技術は並列性において優位であることが指摘されてきた。今回の発表にあるような比較的小規模な原理確認実験をさらに発展させ、今後はこれを大規模な実証システムの段階に進める必要があろう。
|