特別招待講演
コンピュータワールドとリアルワールド

| 東京大学 先端科学技術センター
客員教授 立花 隆 |
私は研究現場の人間ではありませんので、今日は少し引いた立場から、このプロジェクトの持つ意味について考えていきたいと思います。一言でいえば、私はもともと哲学のバックグラウンドの人間で、そういう見地からいうと、このプロジェクトは「人間にとってそもそもリアルワールドとは何なんだ」ということを深く感じさせるプロジェクトであるといえます。今日はそのあたりに視点を置いて考えていきたいと思います。
実は、昨年末、筑波にあるリアルワールド・コンピューティングの集中研を見学してきました。その際に、このシンポジウムのデモに出ているようなものを見せて頂いて、かつ研究者の方から話を伺い、論文も読ませて頂いたんですが、リアルワールド・コンピューティングというプロジェクトについて報道等では多少知ってはいたものの、見学して内容に触れるのは初めてのことでした。駆け足で見ただけですが、やはり今、先端的なコンピュータの研究というのは、もの凄く面白いところへ来ている、その面白さというのはコンピュータの専門家のいう意味の面白さではなく、私のような外側にいる人間にとって、哲学的な問題まで考えさせてしまうような面白さを含んでいるということを感じたわけです。
◆ ◆ ◆
まず、人工知能などの研究の流れの中での、このプロジェクトの位置付けあたりから話を始めたいと思います。「機械振興」という雑誌で以前、リアルワールド・コンピューティングの特集をしていましたが、平成7年の9月号には「第五世代コンピュータ・プロジェクトの13年」という記事が載っていまして(図1)、これが大変面白かった。リアルワールド・コンピューティングは別名第6世代といって第5世代の後継的なプロジェクトという位置付けなんですが、後継的な側面もあれば、かなり違う側面もあります。
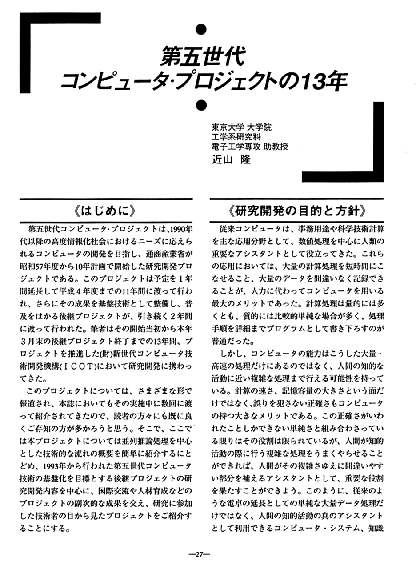
第5世代コンピュータというのは、僕らの世代の人は皆覚えていると思うんですが、プロジェクトがスタートした時、前宣伝が実に激しくて、夢のような人工知能の世界が目の前まで来ているような印象がありました。ところが、そのプロジェクトが10年プラス2年位で終わってみると、前宣伝で聞いた割にどうも成果が何となくパッとしない。この間、ある雑誌でビル・ゲイツとコンピュータの未来について話をしまして、たまたま第5世代の話が出たんですが、彼が物凄くけなすんですね。第5世代は全然駄目だったじゃないかと。
そういう側面は多少あるんですが、ただ第5世代には、基本的に2つのキーワード、つまり「並列」と「推論」というものを、それまでなかったコンピュータの世界に持ち込んで、それまで出来なかったようなコンピューティングをやっていくんだという発想があったわけです。実際に具体的なアウトプットも幾つか出しまして、並列推論マシンPIM、あるいはMulti-PSIという専用ハードウエアを作ったわけです。その上で走る言語も作ったし、OSも作ったし、一応幾つかソフトウエアもあるんですが、実はそのハードがコスト性能比を全く無視して実験的なものを数多く詰め込んで作られたので、実際にはマーケットでの競争力が全くなかった。ソフトウエアを無償で公開しようということになったけれども、公開ソフトウエアを入手した研究者も、それを動かすためのハードであるPIMを市場で入手することができない。従って、ソフトウエアは作品として人間が読むぐらいの使いみちしかなかった、というわけです。これでは世間の評価が低くても仕方ない。
しかし、第5世代が実際に成し遂げたものも非常にいろいろある。特に、第5世代プロジェクトのスタート時点では、日本のコンピュータ研究は国際的に大分立ち遅れていたけれども、この研究によって相当な勢いでキャッチアップでき、かつコンピュータ研究の人材を日本で広く育てたということは何にも替え難い成果であって、その基盤の上に第6世代が乗っているとも言えるわけです。
このように第5世代は、いろいろな意味でプラスのファクターもあるし、ネガティブなところもあるが、第5世代の反省点の1つとして前宣伝をやり過ぎて期待を膨らませ過ぎたのがまずかったという点があったので、恐らく第6世代はそうなることを避けようとしたのか、これまで第6世代の具体的な成果が一般のメディアに登場して、宣伝されるということがほとんどありませんでした。
しかし、もともと第6世代は、大きなアウトプットをドーンと出してこんなものが出来ましたという形でその成果を発表するというプロジェクトではなく、むしろ未来のコンピュータの行く方向は、こっちであるというコンセプチュアルな方向付けを実現するためのいろいろな要素技術を展開していくという発想で進んできているわけです。だから、アッと目をむくような大きなプロジェクトがそこに進行しているというのではなくて、ジワジワとある方向に向けて成果を上げているというのが、このプロジェクトだと思います。
◆ ◆ ◆
あまりにも宣伝しなさ過ぎたせいで、RWCというプロジェクトが走っていることは知っていても、具体的に何をやっているかというのは、私自身も実際に見学するまで知りませんでした。しかし、先日の見学でいろいろ見せて頂いて、また、このシンポジウムでもいろいろとデモや発表があるわけですが、これはやはり、確かに大変な要素技術が生れつつあるという感じがします。その成果のそれぞれについて話し出すと切りがないし、それは僕の任でもありませんからしませんが、これまでコンピュータの世界ではちょっと難しいんじゃないかと思われていたいろいろなことが、相当の水準で出来るようになりつつある。例えば、情報統合の問題とか、言葉や身振り手振りまで入れた本当にマルチモーダルなコンピュータと人間とのインタフェースが出来つつあるということなどです。また、記憶には人間の脳の幾つかのシステムがあるわけですが、そのうちのエピソード記憶というのをコンピュータにやらせようという研究が行われていたり、あるいは自律学習のシステムとか、自己組織型の情報のデータベースを作るとか、これらを見ていると、いろいろな挑戦が今、本当に着々と進んでいるという感じを受けるわけです。
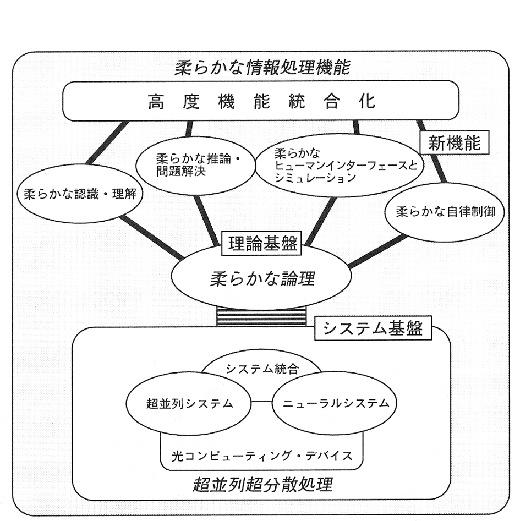
このプロジェクトの基本的な方向付けというのは、大雑把にキーワードにすると2つある。1つは「柔らかな情報処理」(図2)というものであり、もう1つは「リアルワールド」ということになると思うんです(図3)。今までコンピュータが相手にしていたのは抽象世界、つまり論理的世界であって、コンピュータはリアルワールドというものを自分の外に置いていた。リアルワールドにコンピュータが入って行くということは、すなわち一連の柔らかい情報処理というものを実現していくということだ、という基本コンセプトで進んでいるわけです。中間段階の成果を見せて頂くと、これはやはり方向付けとして非常に正しいし、かつ現在のいろいろな挑戦の実現状態を見ると、ゴールはまだかなり先ですが、確かに着実にゴールに向かって進んでいるという感じを受けます。
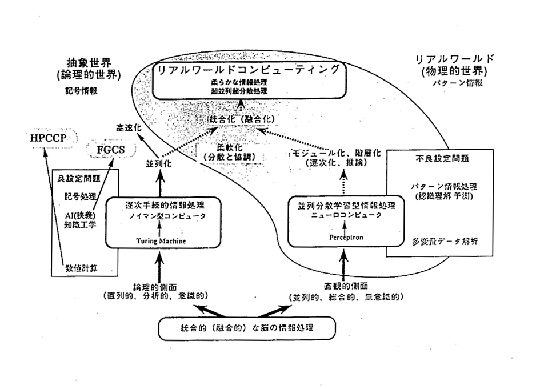
そうすると、この方向付けの延長線上でコンピュータの世界というのは一体どうなっていくんだろうかということになりますが、柔らかい情報処理とかリアルワールドを直接扱う人間に近いコンピュータということで誰でもすぐ思い出すのは、映画「2001年宇宙の旅」のHAL
9000だと思うんですね。HAL
9000は、今考えると非常に面白いコンピュータでして、実は昨日、もう一度あの映画のシナリオと小説を全部読み直してみたんですが、やはりこれは、映画の中ではあるけれども大変なものを実現したと思うわけです。
◆ ◆ ◆
ここで、HAL 9000を作るに至った時代背景と、RWCのプロジェクトが生まれるまでの大雑把な人工知能研究の流れを、ちょっと押さえておきたいと思います。

この数十年の流れを少し引いた立場から見て頂くといろいろ分かると思いますが、人工知能の研究が始まったのは、この年表よりも前のことです(図4)。
この年表はインターネットのカーネギーメロンのページにある実に詳しい人工知能研究史の年表で、非常にいい年表なんですが、これよりずっと前の1956年のダートマス会議で、人工知能の研究が始まるわけです。
1957年にサイモンがGPS、ジェネラル・プロブレム・ソルバを作ります。その時期にサイモンは非常に有名な予言を幾つか残しています。例えば、1957年に、その後10年以内にチェスのチャンピオンを人工知能が取ると予言しています。また、それから後10年以内に数学上の非常に価値のある定義をコンピュータが発見するとも言っています。また、それから後10年以内に心理学のほとんどはコンピュータのプログラムに命題が置き換えられてしまうであろうとも予言しています。
ところが実際には、10年経ってもそれらの予言はほとんど実現されませんでした。ただ、チェスのコンピュータの世界チャンピオンについては、去年ディープ・ブルーが少なくとも1回だけは世界チャンピオンを敗ったので、まあ時間遅れではあるけれども実現しつつある。また、定理の発見も、ある時期、ある程度のことはマシンがやるというようなこともあったんですが、基本的には出来なかった。ただ、この中で非常に面白いのは、1965年に「ドレイファスがAIの完成に対して異論を唱えた」とあるんですね。ドレイファスというのは結構チェスが強くて素人A級なんですが、人工知能がドレイファスにチェスの試合を仕掛けてドレイファスが負けちゃった。それで彼は悔しくて、その後1972年に、「コンピュータには何が出来ないか」という本を書いています。この本はつい最近日本で翻訳されて結構売れているようです。とにかく彼は、それから終始一貫して人工知能に非常に批判的な立場をとるわけです。
60年代を見てみますと、人工知能の歴史で時代を画するような有名なシステム等がいくつか出来ています。例えばDENDRALやSHRDLUのような、非常に有名な人工知能のシステムがこの時期に作られまして、デモのレベルではそれなりに相当な成功を収めるわけです。特にSHRDLUは、非常に小規模なレベルではありますが、自然言語処理をやってのけるわけです。
◆ ◆ ◆
この時期は、実にいろいろなものが成功を遂げ、50年代の終りから69年にかけては、アポロ計画も走っています。アポロを実現する過程でコンピュータに対する巨額の開発投資が行われて、いろいろな事が実現していきました。
幾つかの代表的な人工知能プロジェクトが成功したこともありまして、HAL
9000が生まれた1968年あたりは、この研究領域全体として大変楽観的な気分が漂っていたといえます。恐らくこの時期には、2001年になったら本当にHAL
9000並みのコンピュータができると考えていた研究者が少なからずいたと思います。
しかし、実際にその後の流れを追ってくると、80年代に入っていわゆる「人工知能の冬」という時期が訪れるわけです。その冬の始まりは何だったかと言うと、83年にビジネスウィークに載った「AI、革命が始まった」という記事です。
先ほどの年表に示したようなものは研究室レベルの、非常に領域を限った狭いレベルのテストベッド的なシステムだったと思うんですが、この時期に、実際にAIが産業のレベルで利用できるんだという見方が出てきた。そうなると企業にとってもAIを導入することによっていろいろと有利なものが生まれるということで、1984年から86年にかけて産業界から人工知能に対する多額の投資が行われる。確か、5000万ドルの投資が行われるわけです。しかし、それが結構駄目なんですね。やはりこの時期のAIというのは、扱う世界がトイワールドであるから成功したというシステムがほとんどだったわけです。しかし、産業が利用したいのは当然リアルワールドの人工知能なわけで、そうすると、リアルワールドでは役に立たないじゃないかという失望が広がって、人工知能の冬を迎えるということになったんだと思います。
人工知能の研究者たちは、SHRDLUにしても他のシステムにしても、非常に狭いトイワールドでは見事に成功しているわけです。しかし、それを実際にリアルワールドに広げようとすると大変な困難に直面するという事態が、全ての人工知能の側面において起こって来た。そのあたりをドレイファスなどは徹底的に攻撃するわけですが、現実問題としてリアルワールドというものは、当時の人工知能研究の範疇にはなかなか入って来ませんでした。
例えば、エキスパートシステム一つとっても、この領域の専門家がやっていることをそのまま踏襲して作ったものだからうまく動くだろうと思って動かすと、実際、原理的に動くことは動く。では現実に実用化レベルで動かすために、専門家の知識をもっと本格的にエキスパートシステムの中に入れようとする。しかし、人間の知識をどうやって移し替えるかという問題になると、人間が持っている知識というのは、持っている本人ですらうまく表現することができない。知識表現、知識記述、そういうところで大きな困難にぶつかる。
また、人間が非常に簡単にやっている、例えば特徴抽出とか、パターン認識とか、普通の人間が普通に頭を使えば何でもなく出来るいろいろなことが、コンピュータには大抵出来ない。特に自然言語処理などは、例えばSHRDLUの方式を拡大しようとすると、複雑さがどんどん増していって、それを全部うまく記述して組織的に処理できるようなシステムというのはなかなか作れない。つまり、一言でいえばスケーラビリティの問題と言いますか、そういう問題が起きてきて、原理的な成功をおさめたものが必ずしも実際のシステムには育たないということがわかったわけです。
◆ ◆ ◆
その同じ時期に、人工知能と脳科学と認知科学は、ちょうどお互いに重なり合って助け合う形でどんどん進んでいきます(図5)。
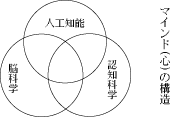
人工知能に関して楽観論が満ち溢れていた時期は、実は脳科学の方でも同じような楽観的な雰囲気があった。脳の基本的なことはほとんど分かってきて、もう少し研究を進めれば、脳というものは少なくとも情報処理の面では基本的に全部分かってしまうのではないかという楽観的な見方がありました。その楽観論を背景にして、人工知能の方も近々実現する脳科学の進歩が人工知能の研究を更に押し上げてくれるのではないかと期待し、楽観論の背景にお互いの楽観論があり、楽観論で重なり合っていたみたいなところがあるわけです。実は、人工知能が冬の時代を迎えている時に、脳科学の方でも、いろいろ基本的な所で物凄い問題にぶつかっていて、今も悪戦苦闘を続けているという状態にあるのです。
認知科学についていえば、その源流は心理学のある領域なんですが、認知科学が人工知能と脳科学の進歩に刺激され、新しい学問として今、どんどん育っている。認知科学の領域から思いがけない知見が発見され、それが人工知能に刺激を与えたり、脳科学に刺激を与えたり、という状況が続いています。
結局、コンピュータの未来を考えたときに、常にこの3つの領域がどのように連係しながら発展していくかというのが重要なわけです。
◆ ◆ ◆
もちろん、こういう科学のサポートとは別に、そもそもコンピュータそのもののハード、ソフトの進み具合というのが人工知能の領域では一番大きな影響を与えるところです。これはハンス・モラヴェックの「電脳生物たち」という本からとった表ですが(図6)、右の縦軸は、人間に相当する能力を持つハードウエアのコストで、人間並みのハードウエアを手にしようと思ったら幾らかかるかという計算です。単位はドルです。10の12乗といったら1兆ですから目茶苦茶お金がかかって、とてもそういうハードウエアを入手できっこないわけです。しかし、このグラフが明らかに示していることは、ハードウエアのコストがいかに劇的に下がっているか、そして性能がいかに劇的に上がっているか、ということで、その両方を掛け合わせるとこういうトレンドが出てくる。2030年頃には、人間の脳並みの能力を持つパソコンが1000ドル、つまり10万円位で世の中に出て来てしまう、そういうことが今明らかに予想されているんです。
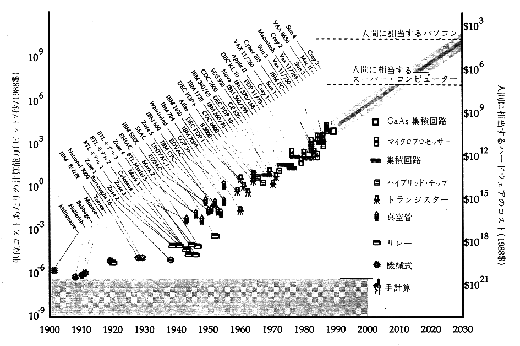
左の縦軸は、単位コスト当たりの計算能力(bit/秒/1988年レベルのドル)です。単位コスト当たりの能力がこれだけ上がっていくということがこの背景にあるわけでして、ハードウエアの劇的な進歩ということに繋がるわけです。とにかく、今たいへん急激なハードウエアの進化が、揺るぎないテンポで進んでいる。
プロセッサの方は段々加工限界に近づいてきていますが、これまで1個で逐次処理をしていたCPUをたくさん使って、第5世代コンピュータの成果の1つでもある並列処理が普通のコンピュータにもどんどん取り入れられている。並列処理を取り入れると、相変わらず直線で進んでいるという感じになるわけです。
更に最近、コンピュータの発展進化の面で見逃せないのは、遺伝アルゴリズムを使ってコンピュータ自体をいろいろな意味で機能的に進化させるという方式だと思います。これは既にいろいろな形でどんどん進んでいます。
最近、遺伝アルゴリズムを使ったコンピュータ進化を研究している研究者たちに続けて何人か会ったんですが、これはたいへん面白い領域で非常に可能性がある。
リアルワールド・コンピューティングの中でも、遺伝アルゴリズムを使ってコンピュータを発展させる研究が幾つかあるようですが、やはり自然世界の知能というのは、生物の進化史の中で進化しながら生まれて来て、かつ更に進化を続けて来たものなんです。その進化を人工知能の世界に取り入れれば、今はレベルが低い人工知能を、より高いレベルに押し上げていくことができるわけです。その極限として生まれているのがEHW、エボラブル・ハードウエア、つまり進化可能なハードウエアです(図7)。
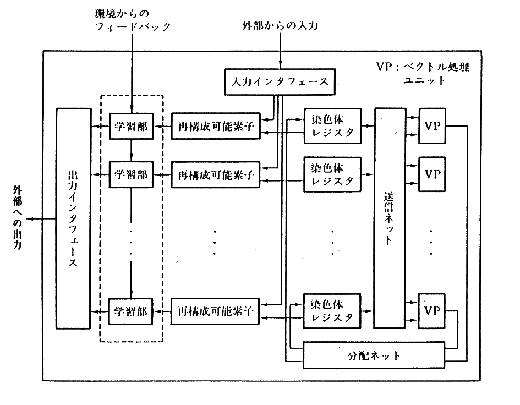
僕は最初、嘘みたいな話だと思ったし、ハードウエアが進化するはずがないじゃないかと普通の人は思うでしょうが、現実には、ハードウエアを進化させるということが技術的に可能な時代に入っているわけです。
一つはFPGA、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイをRAMと組合わせて、そこで遺伝アルゴリズムをどんどん走らせてRAMの中のソフトを進化させ、新しく進化した形にどんどん書き換えていくことによって事実上ハードウエアが進化する。これまでは割とそういう研究だったんですが、今、その次の段階まで来ていて、ハードウエアそのもの、つまり進化させる部分とそういう進化を利用する部分、これをワンチップで作ってしまう。チップ自体がその中でどんどん繋ぎ方を変えて進化していくという研究が今、実際に行われているんです。
実際にこういう研究をしている人たちが、リアルワールド・コンピューティングの一部を成している電総研にもいますし、関西のATRの研究所にもいます。
また、アメリカではMITにこの研究をやっている人たちがいて、これは本当に聞いてびっくりしたんですが、技術的にはそういうことが可能な領域に確かに入っている。そうすると、コンピュータのチップがどんどん進化していって、進化したチップを使ったシステム全体としてみれば、とんでもないものができる可能性が出て来る。これを取材していまして、本当に、何かとてつもないものが今、生れつつある時代なんだなという気がするわけです。
◆ ◆ ◆
さて、その延長線上に何が起こるかというと、ハードウエアが進化する、あるいはコンピュータの能力がどんどん上がることによって、これは既にこのリアルワールド・コンピューティングの中に萌芽が出ている、ヘビロボットの中に意識機能を入れるというような研究が生まれてきている(図8)。
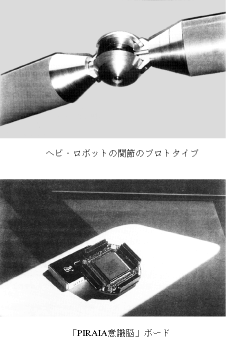
コンピュータが意識を持つということは、今までは常識として考えられなかった。そもそも何をもって意識とするかという定義の問題でいろいろな議論があると思いますが、機械に意識を持たせることによって、より高次の情報処理ができるようになっていく。そういう方向に現実の研究はある意味で進み始めていると思います。
コンピュータが意識を持つ、あるいは機械が意識を持つというのは、これまではSFの世界、つまりHAL
9000的なフィクションの世界の話であったわけですが、非常に萌芽的な形ではあるけれども、意識チップみたいなものが既に出てきている。この場合、では「意識」というのは何なんだということに当然なってくるわけです。
先ほどのハンス・モラヴェックというカーネギーメロンのロボットの研究者が書いた「電脳生物たち」ですが、これは、原題は「マインド・チルドレン」という本で、機械が持つ意識というものについて述べています。この中で、グリフィンの「動物の思考」という著書が紹介されています。この本も、つい最近、日本で翻訳が出た非常に有名な本です。そもそも東洋と西洋では随分ものの考え方が違って、西洋では一般に、動物と人間を画然と区別して動物の意識について語るなどということはほとんどタブーになっているんですが、そうではなくてやはり動物の意識というものも考えるべきである、とこの中で言っています。動物の行動は「意識」という言葉を使うと簡単に説明できるのであって、モラヴェックは「意識とは、いかに未熟であっても、動作の選択肢について考えるのを可能にするモデル―自分と環境と他の個体の内部モデルのことである。」と書いています。「行動の選択を可能にするのに十分な程度複雑な世界の内部モデル―それを『意識』と呼ぼうと呼ぶまいと―は、現在ロボット研究者たちが移動可能なロボットに持たせようとしているものである。」先ほど言ったRWCのプロジェクトでやっている「意識チップ」というのは、まさにこれだといえるでしょう。
意識とは何かというのは脳科学でも最大の問題でして、議論百出、いろいろなモデルがありますが、これは文化勲章を受章された伊藤正男先生が考えた心のモデルです(図9)。
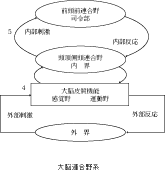
脳の外の世界から刺激を受けて脳に反応を戻すという、これが普通脳の研究で一般に行われていることです。しかし、実は脳の中には内部世界というものができている。内部世界で一度情報を統合して連合野を作る。この連合野で一つの世界が出来ている。ここで、外界とは切り離された内界の世界モデルが出来る。内界の世界モデルと頭頂葉の連合野にあるところが、つまり人格の中心である。そこと脳内部の司令部でやり取りしているものがいわゆる意識というものであり、心というものである、というモデルなんですね。これはかなり有効性を持ったモデルだと思います。
ポパーとエクルスの、「自我と脳」という有名な本にも、このようなモデルが出てきます(図10)。
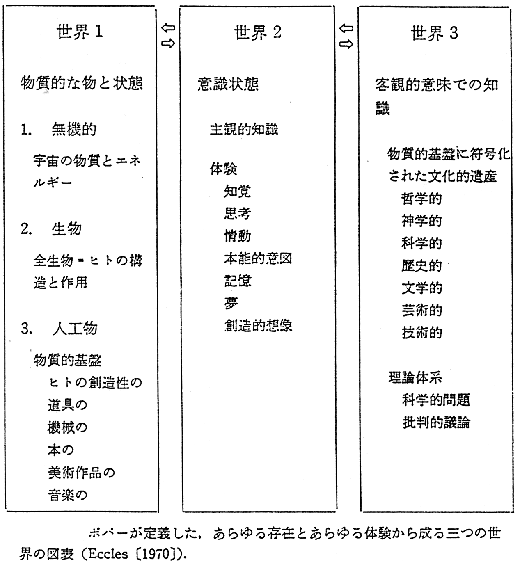
ここにもやはり、世界1、世界2というのがあります。これはどういうものかというと、世界1というのが純粋な外界の状態、世界2が意識状態で、この意識状態の中で更に作られていく内部世界が世界3という形になっているわけです。それぞれ世界1、2、3ができるという構造になっていて、要するに意識の問題は、まず最初に外界と直接連絡がある感覚入力で作られた内部世界の中で、世界のモデルを作っていく。それがそもそもの基本だというわけです。実はそういう世界モデルを作るということ自体が、知能というものにとって非常に重要であるということです。
ところが、これまでの人工知能の研究では、意識が人工知能の更なる発展に必要であるという発想がなかったわけです。ただ単なる記号処理としての情報処理の延長上に知能の世界というものを考えていた。しかし、知能というものがそれだけのものであるなら、インターネットの検索エンジンは何故利口にならないのか。
インターネットの検索エンジンというのは、コンピュータ・ロボットがやっているわけで、毎日毎日何百万ページを精力的に読んで、キーワードを叩き込むと犬みたいに走っていって、そのキーワードがあるページを拾ってくるわけです。そういうことを繰り返しているわけですから、これがもし、意識がある人間が毎日何百万ページもめくってウワーと走っているとすると、アッという間に目茶苦茶利口になるはずです。しかし、コンピュータの検索エンジンは毎日毎日それをやっているのに全然利口にならない。ザルで水をすくっているようなもので、情報のスループットはたくさんあるけれど、スループットがインプットにならない。こういう方向では真の知能というのは育たないと思います。
真の知能とはどういうものであるかというと、知的行為には目的というものがあって、その目的に基づいて意思とか意図というものがあり、そういう意思に基づいて情報を探して見つけて、見つけた情報から有用な部分をピックアップして、それを統合していろいろ組合わせを作り、既にある知識ボディの上にそれを積み上げていく、そういう非常に知的で、しかも意図というものをはっきり持ったタスク・オリエンティドな仕事だと思います。これには、目的とか意思とか意図とかが基本的に必要なわけで、知的な情報、知識のビルドアップはそういうものを抜きには成立しないわけです。
◆ ◆ ◆
人工知能学会が昨年で10周年を迎え、そこで私が喋ったことは、これまでの人工知能の研究というのは、すべて意図とか意思を抜きにして知能の世界は出来ているという前提があって、それは要するに知能は知能の世界だけで成立するということなんです。人工知能を作るとは、そういう知能を作ることであると考えていた。これは言ってみればデカルトの"Je
pense, donc je suis."(我思う、故に我あり)の上に乗っかったものの考え方だと思います(図11)。
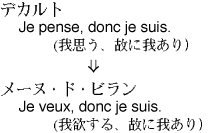
僕は、大学でメーヌ・ド・ビランという恐らくほとんど知られていないフランスの哲学者を卒論に選んだんですが、この人は、存在の一番根源には「考える」ことではなくて「意欲すること」、「欲すること」があるんだと言って"Je
veux, donc je
suis."という命題を立てました。メーヌ・ド・ビランという人はフランス革命の頃の哲学者ですが、その後、現代のベルクソンに至るいわゆる生の哲学の流れは、ここを源流にしているわけです。ヨーロッパの哲学の中には、知の世界を主知主義的に考えるのではなく、主意主義的に考える考え方がずっとあるわけです。まさに先ほどの認知科学にしろ、何にしろ、実は意志の働きがないと知能というものはそもそも成立しないんだということが、いろいろな形で今どんどん出ているんですが、これはそういう思想の流れに乗った考えでもあるといえます。
更に言えば、"Je sens, donc je suis".あるいは"Je fais, donc je suis."
sensは「感じる」で、faisは「する」「行う」、英語ならdoですね。「我感ずる、故に我あり」あるいは「我行為をなす、故に我あり」ということも言えるわけです。
実は人間の存在というものは、たとえば人工知能の世界でもミンスキーの「心の社会」などで段々そちらの方向に来たように、人間の内部世界というものに探り針を入れていくと、結局マルチエージェントの世界になっていくわけです。シンプルなストラクチャでは全然ない。「感ずる」「行為をする」それから先ほどの「考える」「意欲する」そういうものは全然違う柱としてあるわけで、その柱を抜きにすると、人間の知能の世界とか人間の総合的な能力は考えられない。例えば、脳科学の成果で脳がいろいろな領域に分かれていることがわかっています。そのいろいろな領域が他のどういう領域とどう繋がっているかを調べ抜いてトポロジカルに表現したものがこれです(図12)。
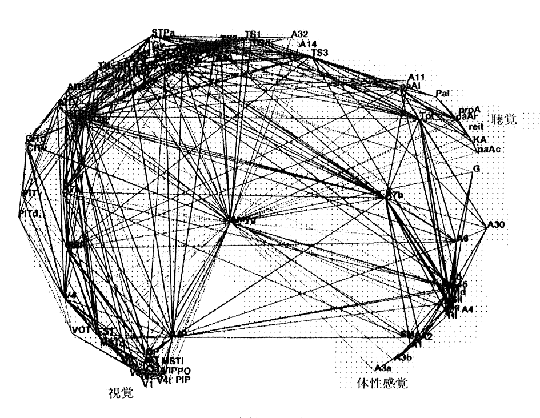
これを見るとすぐ分かるように、1つ集中点があります。これは何かというとアミグダラ、扁桃葉です。これが情動の中枢です。アミグダラが中心になっているということは、まさに"Je
sens, donc je suis."
という部分がやはり人間の知能の世界に非常に大きな働きを持っているということだと思います。人工知能の世界もそうですが、人間並みの知能を持ったシステムを作ってそれに人間並みの情報処理をやらせようと思ったら、こういう要素を抜きにしては恐らくできないはずで、人工知能の研究者の一部で、情動というシステムをその系の中に入れてみたら、その人工知能システムはうまく働くようになった、あるいは意思というようなものを入れたらうまく働くようになったという実験的な試みが実際に幾つか既に出ています。
結局、人間がある知的行為を行うとき、単純な認識から始まってどの過程をとっても、人間が頭だけでやっているものは何一つないのであって、全てが全人格的であるということが、今どんどん分かってきているわけです。
◆ ◆ ◆
そういう面で、認知科学の世界で、ギブソンという人が提案した(図13)「アフォーダンス」の理論というものが、今、注目されています。
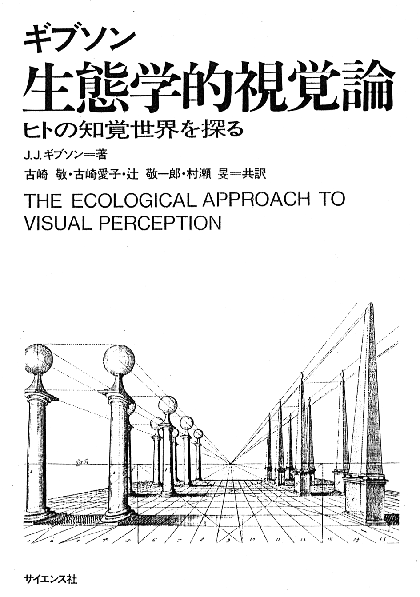
これは説明がものすごく大変で、最近アフォーダンス関係の理論の本がたくさん出ていますからそれを読んで頂きたいと思います。例えば、人間だけではなくあらゆる動物も、何かを認識するという時に何を認識しているのかを考えると、今の人工知能がやっているような、人間の情報処理の仕方に範をとっていろいろ分析するというようなことは全くしていなくて、いろいろな生物がやっていることは、結局アフォーダンスである。アフォーダンスというのは、実はギブソンの造語でして大変解説が難しいんですが、要するに環境が動物に提供する物、用意して備えている全ての物のセット概念なんです。つまり、何かを認識するという時は、そのものが自分に対して何をアフォードできるか、そのものがこちら側の主体に対してアフォードできるものの総体として認識というものは成立するんだというわけです。要するに、分解していって照らし合わせるという認識ではそもそもないんだということです。
これに関連して、最近私が非常に注目しているのは、人工知能の世界で出てきた「オントロジー」の問題です(図14)。
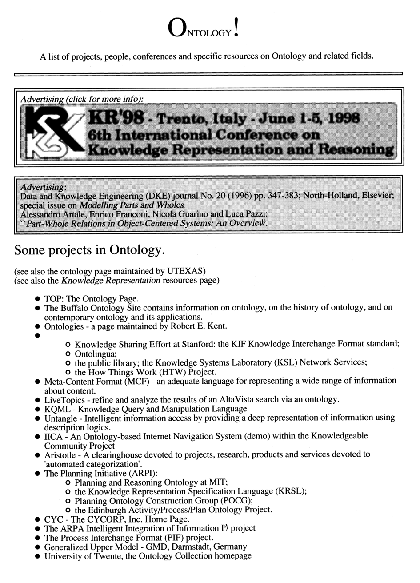
専門の研究をやっている人以外では、オントロジー概念を必ずしもご存じない方が多いかと思いますが、例えば去年の人工知能学会の予稿集では、オントロジーのカテゴリーだけでいろいろ論文が出ています。しかし、研究グループの数にするとそんなにはまだない。オントロジーとは何かというのは、これもWWWにたくさんオントロジー関係のサイトがありますからその辺を見て頂くと分かるんですが(図15)、オントロジーというのはまだ完全に確立した概念ではなくて、非常に議論の多い概念なんです。
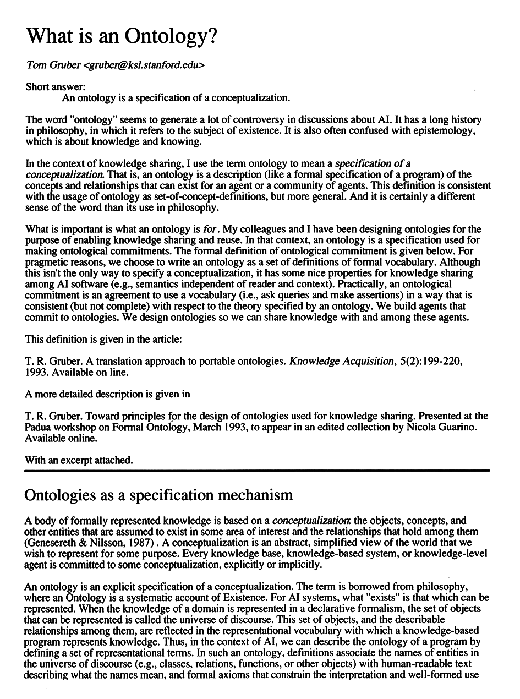
これは、僕らのように哲学のバックグラウンドを持つ人間にとっては非常に親しい概念であって、日本語でいえば、要するに「存在論」です。哲学というのは、存在論を主要なサブジェクトの一つとして何百年間にわたって議論を続けて来たわけで、そういう議論が言わば哲学みたいなものですから、私にとっては大変興味がある世界なんです。私がこの概念に初めて出会ったのは去年の人工知能学会でしたが、なぜオントロジーが人工知能の中に出てくるんだろうと思って本当にびっくりしまして、それから割と精力的にあちこち見て回ってなるほどと思いました。
つまりこれは、set-of-concept-definitionsである。どういうdefinitionsかというと、要するに世界の記述概念だというわけです(図16)。
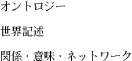
いろいろな概念によって世界を記述する。その記述の概念の首尾一貫性、それを作るものがオントロジーである。それはどのように作られていくかというと、いろいろな概念の間の関係、意味をネットワークの総体としてとらえて位置付けていく。実はこれは哲学の世界では常識なんですが、存在論と認識論というのは実は裏表の関係にあって、存在論がきちんと確立しているからこそ認識というものが成立するわけです。また、認識が成立するから存在が論じられるという逆の方向があって、認識があるから世界の記述というものができるという非常に微妙な関係に立っています。
これまで人工知能はいろいろな壁にぶつかってきたけれども、最大の壁は認識の問題です。その認識の問題の背景には、コンピュータの世界でオントロジーがちゃんと成立していなかった、ということがある。コンピュータが外界を認識する時、そこにまずオントロジーが必要であるという考えが、今初めて出て来たといえるわけです。
コンピュータの世界のオントロジーというのは、いろいろな論があって簡単には総括できない。コンセプトの世界で全部物事を考えているという人たちもいますし、実際に自律移動ロボットを走らせる時にその世界がどういう世界であるかということを記述する方式としてオントロジーをもっぱら考えている人もいる。いずれにしても、例えば自律移動ロボットが世界を認識するときには、前提としてオントロジーが必要なわけです。それがあって、実際にセンサから入ってくるいろいろな情報を統合していくわけです。これが、先ほどのギブソンのアフォーダンスの理論と実は非常にうまく重なり合っていて、人間が持っている概念で記述しても仕方がないのであって、例えばロボットの立場から見ての世界記述というものが必要になってきます。その場合に必要とされる記述というのは何かということを追い詰めていくと、先ほどのギブソンのアフォーダンスの理論とほぼ重なってくるわけです。
◆ ◆ ◆
リアルワールドという概念を皆さん何げなく使っていますが、実はこれはオントロジーと重なり合う概念なわけです。オントロジーがなければ何がリアルワールドかということも言えないわけです。そういう意味で人間にとってリアルワールドとは何かと考える前に、虫にとって、その辺に虫がいたとして、その虫にとってのリアルワールドとは何かを考えてみる。それは、人間にとってのリアルワールドと全然違う。これはまさにアフォーダンス理論が言っていることで、主体に対して環境は何を提供できるか、アフォードできるか、その総体、それが要するに、その生物にとっての必要情報である。その主体が、そこで働かせなければならない知能というのはまさにそこにある。
もし、これが一種のカテゴリー・エラーで方向がずれてしまうとどういうことになるかというと、実は有名な笑い話があります。ある人工知能の研究者が、地面を歩いている蟻が非常に複雑な歩き方をしているのをある日発見して、この歩き方のアルゴリズムは何だろうと考えだすわけですね。一生懸命考えるんだけどなかなか分からない。そのうちやっと分かったら、実は蟻は、ただ地面の高低に従って低い所を選んで歩いていただけだと。つまり、リアルワールドというものは、ある主体に対してのリアルワールドという形を常にとっているわけです。ある主体にとってのリアルワールドというのは、先ほどのオントロジーの記述もそうであり、アフォーダンスと同じように、ある特定の主体に対して環境が何を提供するかという、その総体のことなんです。オントロジーで記述された世界、これは先ほどいった意識の根底をなす世界モデルということになるわけです。世界記述というのは、即これが世界モデルであるということです。つまり、意識とオントロジー、それからリアルワールド、それらは全部切り離せない関係にあるわけです。
結局、意識は世界のモデルが生むわけです(図17)。

意識というものが生まれる、進化史的に言えば意識が「創発」した時点があります。ヘビロボットの意識チップでもそうですが、あれはまさに世界モデルを作るわけです。世界モデルを作ってその中でシミュレーションをするわけです。ある世界モデルを作ってその中で自己を客観的にモデルの中に投影して、それを頭の中で動かす。それがそもそも意識の最初であるということをいろいろな人が書いています。まさにそのレベルに今、機械、あるいはコンピュータが達して来たというわけです。これがもし遺伝アルゴリズムなどを使って世界モデルというものを更に進化させ、この世界がもし発展を始めたら、生物進化と違って電子的進化というのは目茶苦茶なスピードでいけますから、これは恐ろしく速い意識進化を遂げることなる。その延長には、HAL
9000のようなコンピュータが出現するということが十分に考えられると思います。
そうしますと、非常に重要な問題が出てくる。HAL 9000は決していい話ばかりではなく、「2001年宇宙の旅」のHAL
9000の最後を思い出して頂ければ分かるように、結局HAL
9000は独自の意識、つまり使う人間と離れた独自の意識、意図というものを持ち始めたがために人間に対して反逆するという問題が出てくるわけです(図18)。
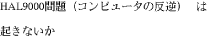
確かにこの方向に進んでいくと、これまでフィクションの中でしか考えられなかったようなことが本当に考えられると思います。ジェネティック・アルゴリズムを使った電子進化の速さを考えたら、相当早い段階からそのあたりのことをどうすればいいかを考えていかなければならない。そういう危険性があると思うんです。
◆ ◆ ◆
ニッセンという心理学者が、系統発生における生物の歴史、下等動物から人類に至る歴史における知能の発達を図のようにまとめています(図19)。
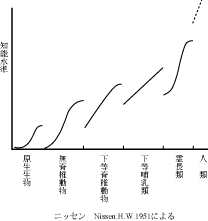
この知能水準は数学的に厳密に測ったものではなく彼独特の定義で測っているわけですが、やはり、進化に従って知能水準がどんどん上がっていく。霊長類までが実線で書かれていて、人類はまだよく分かってないから点線にしてあります。人類は人間社会の中にコンピュータや人工知能を取り込み、今、完全に人間とコンピュータとのハイブリッド社会を作りつつあると思います。ですから知能水準も、人間の生まれながらの知能プラスハイブリッドでくっつけている人工知能、あるいは我々の社会全体が利用している人工知能全体を考えてもいいわけですが、そういうものとして今、人類は非常に新しい進化の段階に来ている。
知能水準の上げ方はいろいろありますが、HAL
9000問題を始めとして人類が現在抱えている、あるいは将来当然予想されるさまざまな問題を十分考え、それを解くようなレベルに知能水準をどんどん上げていくということが必要な時点に今、来ている。
そして、そういう方向に向かって、今、このリアルワールド・コンピューティング・プロジェクトは、非常に大きな一歩を記したと評価できるのではないかと思います。
|