特別セッション
次世代情報処理基盤技術開発事業
実世界知能技術について

| 電子技術総合研究所
知能情報部
部長 大津 展之 |
実世界知能技術の分野について、概略をご説明したいと思います。まず、バックグラウンドについてお話しします(図1)。
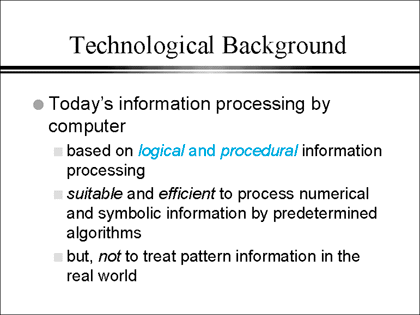
今日の情報処理技術は、ご承知のように、コンピュータの論理的かつ手続的な情報処理に立脚しています。そういう意味では、数値あるいは記号的な情報を、予め作り込まれたプログラム、アルゴリズムに沿って処理するには非常に効率のよい方法ではありますが、実世界におけるパターン情報を扱うのに適しているとはいえません。
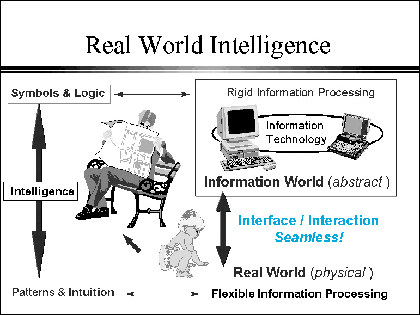
これは、実世界知能の概念を示した絵です(図2)。我々は、実世界とのインタラクションを通して知能を形成していきます。最初は実世界とただ戯れているだけですが、だんだんと賢くなって知能を形成していきます。知能にも、パターン及び直感を主体とした部分、それからさらに高次の記号及び論理を主体とした部分、というようにレベルがあります。現在のコンピュータ技術は、記号と論理を主体とした情報処理を実現したものです。そういう意味では、非常にリジッドな情報処理を行っているわけです。
一方、我々が自然に行っているような実世界での情報処理は、非常にフレキシブルです。
問題は、記号的な世界、つまり現在の情報世界と実世界との間に、非常に大きなギャップがあるということです。今日の情報処理における最も大きな技術的課題は、そのギャップを埋めるということだと思います。つまり、インターフェイスあるいはインタラクションをもっとシームレスにしていくということです。
これは、情報処理技術の過去から未来を一枚の図で表したものです(図3)。
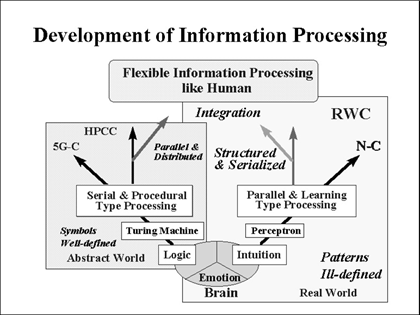
ご承知のように今日の情報処理技術は、Turing
Machineをモデルに、脳の論理的な側面を逐次的かつ手続的な情報処理として発達させたものです。第5世代コンピュータ(5G-C)は、その論理的な側面をさらに押し進めたプロジェクトでした。High
Performance Computing and Communication
Initiative(HPCC)は、並列分散化や高速化を狙った方向の政策です。いずれにしてもこれらの分野は、Well-definedな問題を扱うには非常に効率のよい分野です。つまり、抽象(情報)世界なわけです。
一方、我々の脳は、もう一つの側面を持っています。それは直感的な側面というか、端的にはパーセプトロンをモデルとしてニューラルネットワークが行っているような、並列かつ学習的な情報処理を行うという点です。これを極端に進めたものがニューラルコンピューティング(N-C)です。RWC、これは古いスライドですから全体的にまだRWCと言っていますが、実世界知能技術は、これらの方向をさらに進めて、柔軟な情報処理を目標としているわけです。
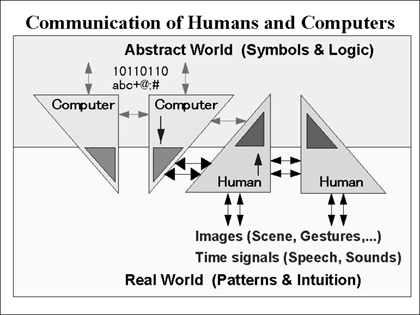
この図は、コンピュータと人との対話というタイトルで書いたものです(図4)。
ご承知のように、人間は実世界とのインタラクションを通して知能を発達させます。この場合のインタラクションは主に空間的な画像、あるいは時間的な音声といったパターン的な情報とのインタラクションです。それらを通して、高次の知能を記号世界に作っているわけです。一方、コンピュータは記号世界で非常に効率よく動いている。ところが実世界とのインタラクションは弱い。チャンネルが少ないということです。これまでコンピュータと人とのコミュニケーションは、細い記号世界を通して、つまりキーボードを通して行われていたわけですが、これがネックになっている。今後は、コンピュータと人との対話をもっと豊かなものにする必要があり、そのためにはコミュニケーション・チャンネルを拡大する必要があるということです。それには、我々が日常行っているのと同じようにパターン的な情報をダイレクトにコンピュータが理解できるようなチャンネルを作る必要があり、そのためには、実世界知能という部分を、コンピュータの人間とのインタラクションのチャンネルに形成する必要があるということです。
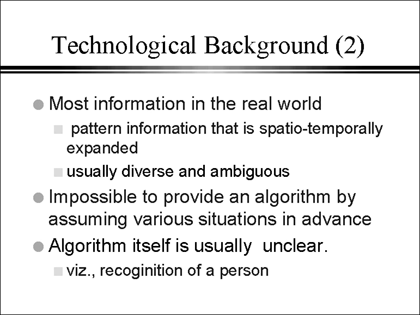
実世界での情報処理について考えますと(図5)、その情報の多くはパターン情報です。
それらは時空間的に広がったものであり、通常、非常に多様でかつ曖昧、不完全です。我々は一時に一部の情報しか手に入れることができないわけでして、そういう意味では部分的な情報のみがアベイラブルになっていると言えます。通常、前もってあらゆる場合を想定してプログラムをすることは難しいし、また、アルゴリズム自体も、非常に不明確です。例えば、我々は何気なく人を認識するわけですが、そのアルゴリズムは?と問われると、はたと困ってしまうということです。
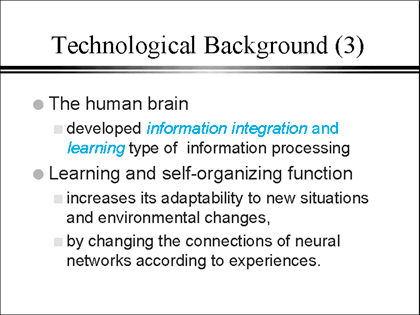
さて、人間の脳は情報を統合する、あるいは学習するタイプの情報処理技術を発達させたわけです(図6)。実世界におけるパターン情報に効率よく対処するために、こういうタイプの情報処理を発達させたといえます。実は、記号的な知能はその上に形成されています。学習あるいは自己組織化機能というものは、人間が実世界における多様な環境あるいは状況の変化に適用する能力を与えているというわけです。どのようにしているかといいますと、実際には、経験に従ってニューラルネットワークの結合を変えて対処しているわけです。そういう意味でだんだん賢くなっていく。
従って、今日最も重要な情報処理技術は、そうした実世界知能というような機能を、現在の情報処理システムに組み込む技術なのです(図7)。
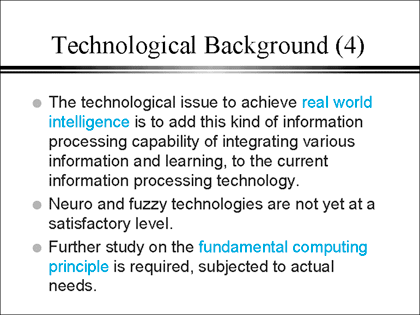
ニューロとかファジーというような技術が既にありますが、これらは、まだまだ不十分なレベルにあります。従って、さらに進んだ、もっと基本的な計算原理の研究が非常に重要です。もちろんそれには、実際のニーズとよく付き合わせて研究を行っていく必要があるでしょう。
従って、この分野の目標は、基盤技術の開発、つまりリアルワールドインテリジェンスを今日の情報処理システムに付加するための基盤的な技術を開発すること、それによって情報処理の応用範囲を広げる、ということです(図8)。
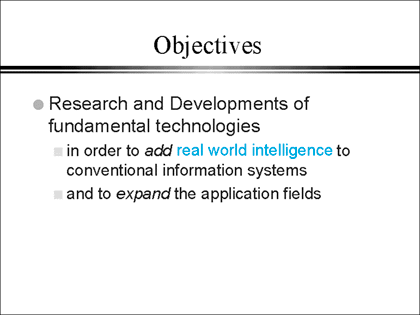
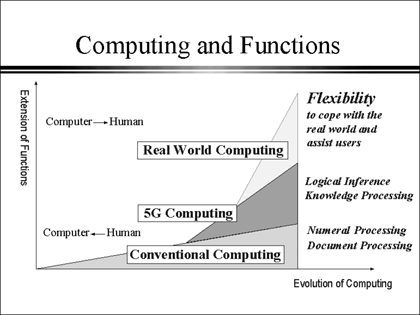
それを絵にしたのがこの図です(図9)。コンベンショナルなコンピューティングの上に、第5世代は、記号と論理を扱う方法を付加しました。リアルワールド・コンピューティングにおいては、実世界の多様な情報に対処する柔軟さを持った知能を追加したいというわけです。これまでのように、「コンピュータに人が近づく」というのではなくて、むしろ「コンピュータが人に近づく」必要があるということです。
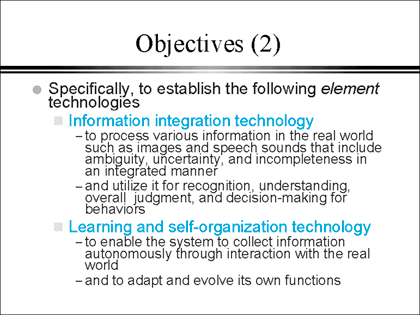
それには、次のような要素的、基本的な機能の研究開発を進める必要があります(図10)。
その一つは、情報を統合する技術です。これは、実世界における多様な情報を総合的に判断したり認識したり、あるいはそれらの情報を、次の行動のディシジョン・メイキングのために利用する技術です。
もうひとつは、学習および自己組織化技術です。これは、システムが自律的に実世界との相互作用を介して情報を獲得する、それによってシステム自身の機能を適用させたり進化させたりするという機能です。この二つがリアルワールド・インテリジェンスを実現させるための最も基本的な機能ということになるわけです。
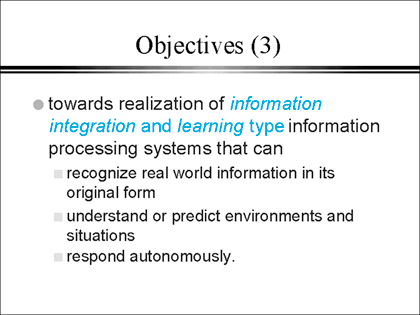
それによって、これまでの手続型の情報処理ではなく、情報統合及び学習型の情報処理を実現したい(図11)。それは、実世界の多様な情報をそのままの形で取り扱うことができて、環境を理解したり推論をしたり、あるいは自主的にレスポンスできるようなシステムを目指したいということです。
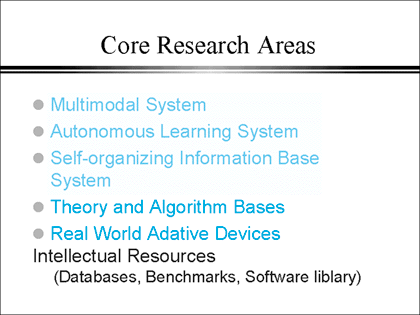
そのために我々は、5つのR&Dのコア・リサーチエリアを設定しています(図12)。基盤技術の研究を進めるためには、そのプロトタイプ・システムを想定して問題をよく洗い出しながら研究していく必要があります。そういう意味で我々は、3つのシステム領域を設定しました。これは、情報処理の基本的な能力、つまり、認識、理解、あるいは推論、コントロールといったものをカバーする最小限の部分だと思っています。
最初はマルチモーダル・システム、2番目は自律学習システム、3番目は自己組織化情報ベースシステム。この3つは、簡単にいうと、ヒューマン・インタフェース、自律ロボット、新しい形の情報ベース、と言い換えることが出来ます。
これらを支える基盤的な技術として、2つ考えています。まず一番重要なのは、理論的な基礎とアルゴリズム的な基礎です。そういったものをしっかりと研究してこの3つの領域を支えていく。これらの技術が単なるヒューリスティックスの寄せ集めにならないように、真にブレイクスルーをもたらすために、理論的な基盤が非常に大事であると考えているわけです。このインタラクションによって、本当に新しい技術が作られるだろうと思っています。
さらに、ハードウェア的な基盤が必要になってきます。これは、スーパーコンピュータが必要であるということではなく、このようなシステムを実世界でリアルタイムで実現していくためには、ある種の特殊なデバイスを必要とすることがあります。ここでは仮に、実世界適応デバイスと呼んでいますが、こういったものの開発も併せて必要であると思います。
このような研究開発をさらに加速したり、あるいは評価したりするためには、知的資源という名前で仮に呼んでいますが、例えば各種のデータベースを整備する、また、ベンチマーク課題をしっかりと設定して開発された手法を評価する、さらには新しく得られた手法を、きちんとソフトウェア・ライブラリとして整備していくということが非常に大事になります。
次に、それぞれのコアについて簡単に説明したいと思います(図13)。
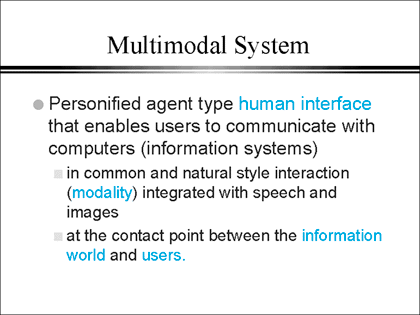
先ず、マルチモーダル・システムというのは、擬人化されたエージェント・システムのようなものです。これは人とコンピュータの対話をスムーズなものにすることを狙っているわけですが、スムーズであるというのはどういうことかというと、我々ユーザが日常使っているコミュニケーション・チャネルを使うということです。共通的で自然な形のインタラクション、つまり、モダリティーを使った計算機との対話。具体的には、音声、あるいは身振り手振りといったビジュアルな情報処理を含みます。この技術は、情報世界とユーザとの接点に位置する技術です。
次に、自律学習システムについてご説明します(図14)。
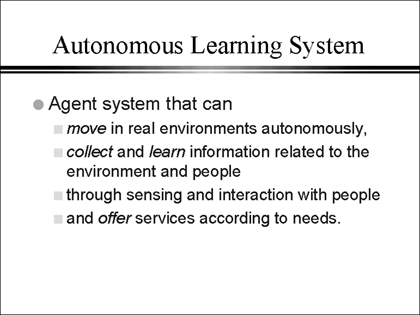
これは、実世界の中を自律的に動き回るエージェントと考えられます。実世界での多様な環境の情報や人々の情報を動き回って集め、そして学習していくようなシステム。ある意味でこれは、新機能を統合するテストベッドであると考えています。様々なセンシング、あるいは側にいる人と対話でインタラクションを行うといったことによって情報を獲得して学習し、だんだん賢くなっていくシステムです。そしてその先には、様々なニーズに応えることができるシステムを想定しています。
次は、自己組織化情報ベースシステムです(図15)。
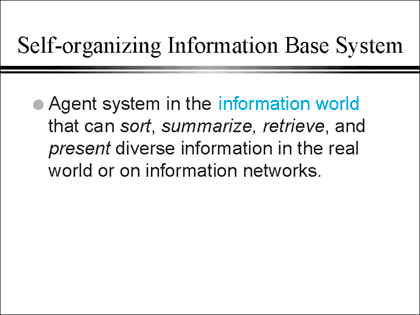
このシステムは、情報世界におけるエージェント・システムと考えることができると思います。実世界、あるいはネットワーク上にある膨大な情報を整理したり、要約したり、検索したり、あるいは人に分かりやすく表示する技術です。この技術は、現在の情報化社会において、特にインターネットに代表されるような情報洪水の現代にあって、早急に必要な技術だと思っています。ただそれを従来の手続的な方法ではなく、実世界知能における新しい手法によって柔軟に処理することのできるシステムを目指したいと思っています。
次に、これらを支える基盤技術について説明します。最初は理論・アルゴリズム基盤です(図16)。
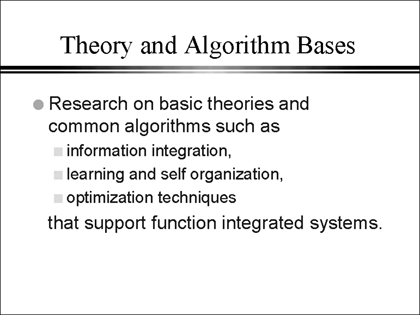
今、説明したような機能を統合化したシステムをサポートするために、共通となるアルゴリズム、あるいはより本格的な理論を研究します。例えば情報統合についての理論、学習・自己組織化に関する理論、さらには各種の最適化手法などを研究するわけです。
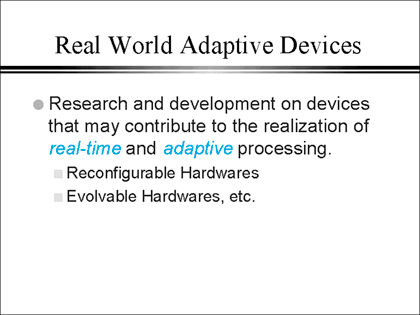
次に、実世界適応デバイスです(図17)。実世界でのシステムは、ある意味では非常に高速性、リアルタイム性を要求されます。ソフトウェア的にそれが実現できればいいのですが、場合によっては難しいことが多いわけです。そうしますと、どうしてもハードウェア的サポートが必要になる。学習や自己組織化もするわけですから、ついでにそれもハードウェアのレベルで出来たらいいというわけです。ここで考えているデバイスは、新しい形のReconfigurableなハードウェア、あるいは自らが進化できるハードウェアなどです。
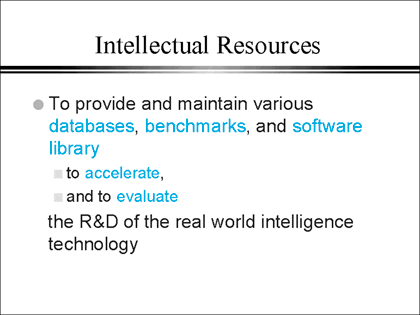
最後に、研究用知的資源と呼んでいる分野ですが(図18)、これは全体に関わってくるものです。例えば、音声や画像といった実世界データベースをしっかりと整備して持っておくということは、実世界知能システムをデザインする上でも、評価する上でも重要です。さらに、いろいろな手法を比較したり、研究のメルクマールをしっかりと打ち立てるためには、ベンチマークテスト課題を設定して開発を進めていく必要があります。そして、得られた手法がアドホックなレベルで消えてしまわないためには、しっかりとライブラリとして残すということが大切です。逆にそういったライブラリを使って研究を加速することができるわけですし、また、後世にしっかりとした形で成果を残すという意味でも重要だと考えています。
以上、研究の概略についてご説明しました。
それでは、以上のような研究開発を進める上での体制についてお話ししたいと思います(図19)。

現在我々は、各研究領域ごとに、それぞれの領域が最もやりやすいスタイルを考えながら、基本研究計画を策定中です。それを本格的に推進するためには、領域ごとの密な議論、方向付け、あるいは共同研究を推進する必要があります。そのためには、もっと頻繁に、それぞれのワークショップや委員会を領域内および領域間で開く必要があると考えています。
では、少し時間が余りましたので、もう少し立ち入った個人的な観点から意見を申し上げたいと思います(図20)。
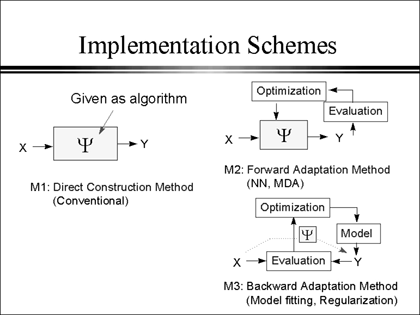
これまでの情報処理におけるいわゆる手続型処理は、線型モデル(M1)であり、入力情報を出力情報に変える適切な処理を、アルゴリズムとして与えてやる。そういう意味ではダイレクトな方法であり、固い枠組みになったりするわけです。
これに対して、ニューラル・ネットワークや多変量データ解析は、処理の方法に自由度を持たせてパラメータ等を含ませ、しっかりと評価をして、という最適化のフィードバックループに乗ったやり方であるといえます。これによって、例から最適な処理を習得していこうとしているわけです。ある意味では、フォワード・アダプティブな方法です(M2)。
さらに、モデルフィッティングや正則化理論の話は、逆にバック・アダプテーションといいますか、ある入力情報に対して相応しい出力情報をモデルとして想定し、この差を評価しながら更新していく。これによって、インプリシットですが、最適な処理を得ようとしているわけです(M3)。こういった新しいやり方を踏まえながら実世界知能というものを考えていく必要があるだろうと思います。
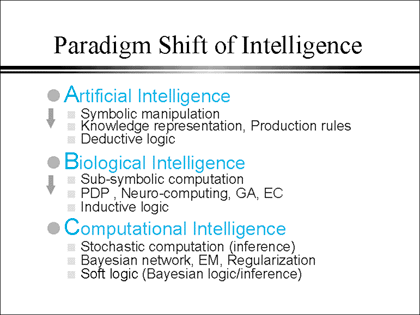
人工知能の弁証法的な発達段階を、私はよくABCで表します(図21)。Aはあまりにもアーティフィシャルな、従来の狭い意味での人工知能の研究です。これは主に記号処理や知識処理、知識表現、あるいはプロダクション・ルールといった演繹的な論理を主体とした知能の枠組みでした。
これに対して今日のニューラルネットワーク等のブームというのは、バイオロジカルなインテリジェンスです。これは、サブシンボリックなコンピュテーションを狙っています。もう少し帰納的な論理に主体が移ってきています。
しかし、こういった諸々の話の背後にあるもっと統一的な計算原理をしっかりとおさえて、理論的にも深めながら、このプロジェクトを推進していく必要があるだろうと思います。その一つはストカスティックなコンピュテーション、それからベージアン・ネットワーク、等々です。その基礎には、柔らかな論理と当初言っていましたが、ベイズ的な論理や推論、あるいはディシジョン・メーキングの枠組みがあると思っています。
さらに、実世界のパターン的な情報を扱うには、もう一度しっかりとパターン認識の話を認識する必要があると思います(図22)。
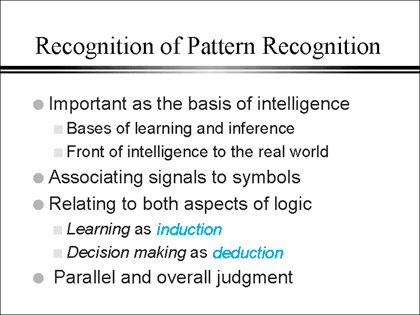
パターン認識は、知能の基礎として非常に重要です。学習、推論の基礎になるわけです。また、知能と実世界との接点にある。そして、パターンと記号をつなぐ技術である。さらに、論理的な立場からみますと、インダクションとしての学習のフェイズも持っていますし、ディシジョン・メーキングとしての演繹的な側面も持っているというわけです。さらに、本質的には並列処理とか総合的判断を主体としています。
柔軟な情報処理、例えばパターン認識、ニューラル・コンピュテーション、あるいはレギュラリゼーションとか、確率的な推論の背後には、ベイズ的な基礎があると思います(図23)。そういったものを最も簡単に線形モデルで表したのが多変量解析の世界だし、ある程度の非線形の関数の範囲で考えたのがニューラル・ネットワークです。それを究極な形まで持っていくと、ベイズ推定の話までいくというわけです。
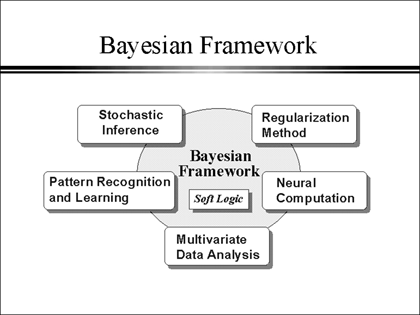
以上で私の講演を終わりたいと思います。
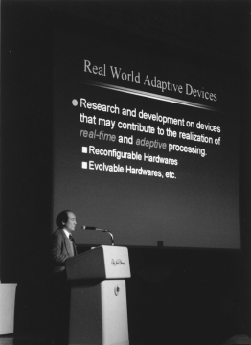
ご静聴ありがとうございました。
|