ICPR '96(International Conference on Pattern
Recognition)は、2年毎に開催され今回で13回目を数える、パターン認識全般の会議としては世界的に代表的な会議であり、今回はウィーンで行われました。内容としては、
Computer Vision, Pattern Recognition and Signal Analysis, Applications and
Robotic System, Parallel and Connectionist
Systemsの4つのTrackに分かれて、11件の招待講演、63件の口頭発表、452件のポスター発表が行われました。今回の海外出張では、他に、SICS
(Swedish Institute of Computer Science)、RISC-LINZ (Research Institute for
Symbolic Computation)、SNN (Foundation for Neural
Networks)の3つの研究機関も訪ねました。そして、各研究機関と学会にて、動画像を用いたロボットの位置推定方法について発表しました。ここでは、併せて実時間ジェスチャー認識のデモもビデオで示し、両者のシステムで用いられている連続DPの有用性を強調しました。
出張は、能動知能研究室の山川宏氏と2人で出発しました。山川さんは経験が豊富で飛行機の離着陸時にも沈着冷静でしたので、お陰で私もリラックスして飛行機の旅を楽しむことが出来ました。
初めの訪問先は、SICSでした。Dr. Martin
Nilssonは、日本の大学で研究していただけあって流暢な日本語を話されます。さらに、日本からちょっと小さめな畳を飛行機で持ち帰って自分のアパートに敷いて使っているくらいの日本通でした。Nilssonさんは、ヘビ型ロボットについて紹介して下さいました。現時点では、数十関節の本体を作成中であり、また地面との摩擦を考慮して強化学習のシミュレーションを行っているそうです。
次は、ウィーンで開催されたICPR
'96に出席しました。こちらでは、ポスターセッションで発表しました。私にとって初めての英語で行う公式発表でしたので、かなり緊張いたしました。山川さんもポスターセッションで同じ時間帯に発表があったのですが、発表中の私の写真を撮ってくれるほど落ちついていらっしゃいました。発表に関しては、全方位視覚センサや実時間ジェスチャー認識のデモに関する質問などがあり、本技術に対する関心の強さを感じること
ができました。
次に訪れたのはオーストリアのリンツにあるRISC-LINZでした。こちらは昨年までRWCPの海外再委託先であり、Dr. Witold
Jacakらと研究状況について議論しました。RISC-LINZでは、Symbolicな計算とNeural
networkの計算を相互に置き換える技術、および近接センサを備えたロボットアームについて紹介して頂きました。RWCPの再委託先を離れたものの、マルチメディアを中心とした日本との人的技術交流の推進を希望しているとのことでした。私の発表には、率直で厳しい質問を頂きました。それは、ロボットの視覚誘導の必要性に関するものであり、従来の内界センサを用いる手法との優位性を疑問視する意見でした。この質問に関しては、人が周りの風景を見て自分の位置が分かるように、ロボットも画像から自分の位置が分かると、電源投入時や性状の悪い床面においても位置推定が正しくできることを強調いたしました。
最後の訪問先は、アムステルダムにあるSNNでした。SNNは、RWCの分散研の 一つです。こちらでは、Dr. Ben J.A.Krose, Dr.
Bart ter Harr Romenyらと、マルチスケールコンピュータビジョンやオプティカルフローを用いた自律走行制御などについて議論を行いました。
今回の出張では、ジェスチャー認識に関する研究が盛んであるATRと大阪大学の研究者らと交流でき、参考になりました。また、国際会議の活発な雰囲気を感じ、RWCの分散研や海外再委託先の研究者と交流でき、自分自身の研究生活に良い刺激を頂くことができました。
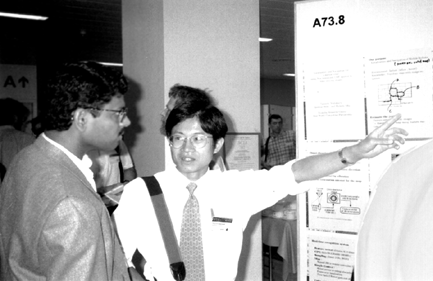
ICPR '96にて発表する筆者