-光NEC研究室-
プロセッサ間の自在な並列信号伝送を可能にする
光電融合プロセッサネットワークの研究
菅生 繁男
(日本電気株式会社 光エレクトロニクス研究所)
■研究の背景と目的
超並列コンピューティングを実現するためには、多数のプロセッサ間をつなぎ、高速、大容量、柔軟なデータ交換が可能なネットワークが必要とされ、光インターコネクションはこのようなネットワークを実現するキー技術として期待されています。例えば、プロセッサ数が1000規模の超並列計算機では、1つのプロセッサボードへの入出力ピン数が1000以上と膨大で、実装上、コネクタ断面積やケーブル重量が大きく、また、ビットレート・距離の限界もケーブルの周波数特性上問題になります。ここに、光接続の有する軽量、高スループット、長距離という特徴が生きてきます。
光NEC研究室では、従来にない高性能な光インターコネクションとして、エレクトロニクスとオプティクスの両方の利点を結合した光電融合プロセッサネットワークの実現を目指して、超並列コンピュータのプロセッサ間の自在な光並列信号伝送を可能とする光インターコネクションの研究を進めています。
具体的には、超並列計算機用光インタフェースボードの開発と、キーデバイスである光電融合スマートピクセル、及び、再構成可能な光インターコネクションを実現する立体光接続素子の3つのテーマで研究を行っています。前者は、集中研にて開発中の超並列計算機RWC-1用の光インターコネクションボードを開発するもので、光インターコネクション技術でボード間のピンボトルネックの解消を狙って研究を行っています。光電融合スマートピクセルについては、そのキーデバイスとして、2次元集積による超多チャンネル化が可能で光通信波長帯で発振する、長波帯面発光レーザの実現を進めています。これはボード間より進んで、パッケージ間のボトルネックの解消を狙っています。この面集積された機能素子間を繋ぐのが立体光接続素子で、この研究では、例えばデータの行く先をデータ自身で制御できる、いわゆるセルフルーティング機能など、高スループットの伝送路の実現を狙っています。
■現在までの成果
まず、光インタフェースボードの最近の成果についてご紹介します。図1(a)は、マザーボードに装着して使用する光データリンクサブシステムの送信側カードの写真です。大きさは15センチ角で、ボード中央に6芯テープファイバを接続したLDアレイモジュールが配置されています。RWC-1用光インタフェースの基本構成要素として試作したもので、100Mb/s並列48bit、計4.8Gbpsのデータ信号を1本の光テープファイバにのせて伝送します。こうした並列伝送では、それぞれのファイバ内を伝搬する光信号の到着タイミングの微妙なずれ(スキュー)のため、データの並列性が損なわれることがあります。今回のカードでは、専用に開発した信号処理ICによって、転送後も並列データとして扱えるよう±15ns(1.5T)のスキューを補償する機構を設けております。
次にRWC-1のデータ通信を行うICであるSU(Switching Unit)を元に構成したデータ転送実験用テストベッド(SUTB:SU Test
Bed)を用いて、実際にこの光インタフェースによるデータ伝送実験を行いました。図1(b)はSUTB光リンク実験系の構成図です。
SUTBはPEの替わりにWSによりVMTユニットを介してSUを制御します。
送信カード(TX)と受信カード(RX)間でデータ転送を行い、SUのデータ出力レジスタと伝送後入力レジスタの内容を比較することで、実際にRWC-1のプロトコルに則ったパケット転送が行えることを確認しました。さらにランダムパケットを連続生成して転送を行い、接続距離10mについて17.5時間以上エラー無く転送され(BER1x10-14以下に相当)、光インタフェースが問題なく動作することを確認しました。伝送距離は1kmまで試験しましたが同様に動作しています。
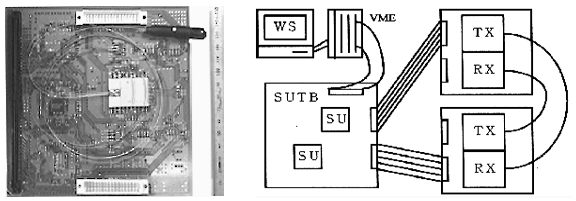
図1 光インターフェースカード
次に、先行的な研究として進めている、光電融合スマートピクセル/立体光接続素子についてご紹介します。光電融合スマートピクセルの基本要素となる面発光LDは、2次元集積化が可能である反面、光通信用の波長である1.3μmや1.55μmでの発振特性がよいものが得られにくいという問題点がありました。これは、この波長帯で使える光半導体の通常の組み合わせでは大きな屈折率差が得られず、その結果、レーザー発振に必要な99%以上の高い反射率をもつ半導体多層反射鏡(DBR)が作製困難だったためです。当研究室では、この問題の解決に、アンチモン(Sb)を含む新しい半導体の組成を提案し、結晶成長技術の開発を進め、実際に99%以上の高反射率のDBRを実現しております。図2は、このLDの構造の模式図です。発光層を上下から新材料からなるDBRではさみ光共振器を形成していて、発振光は基板の方向に出射します。現在、このDBRを備えた面発光LDの試作、特性測定を進めております。
また、この面発光LDをベースにした面発光アレイデバイスと組み合わせてルーティングを行うセレクタを設計及び試作も行っております。セレクタ部はGaAs-ICで構成し、その基本性能は、16chアッドレサブルトランスミッター動作及び各チャンネルが1Gb/sNRZ送信が可能です。これにより、低レータンシ、高スループット等の特徴をもった光電クロスバスイッチを実現することができます。さらに、2次元集積されたスマートピクセルを接続する手段として、空間光学系を用いた伝送路、立体光接続素子も研究しております。これには、光学系をアライメントフリーに実装できる光電融合MCM(Multi-Chip
Module)技術を開発、実際に、Al製の光電融合MCM基板に、2組の8×8面発光レーザ(VCSEL)アレイ光学系をアライメントフリー実装し、8ch-SDMスイッチの基本動作原理を確認しております。
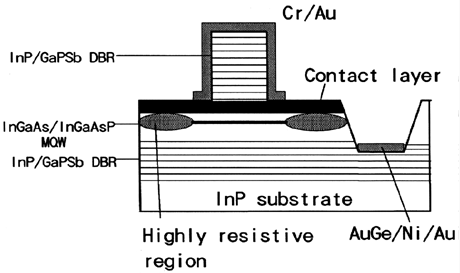
図2 スマートピクセル用面発光LD構造
■今後の予定
今後、光インタフェースボードについては、光インタフェースを搭載したRWC-1用プロセッサボードの試作を行い、実際の試験を目指していきます。また、光電融合スマートピクセル/立体光接続素子については、新材料系によるDBRを用いた面発光LDと、それを用いた光電融合スマートピクセルの実現をはかり、立体光接続素子での並列伝送実験を継続して、スイッチ及びネットワークのスケーラビリティの確認を目指していきます。
|