-新機能富士通研究室-
実世界情報を自律学習する知的システムを目指して
渡部 信雄
(株式会社富士通研究所 情報社会科学研究所)
■研究の背景(知的システムを使いやすく)
複雑で、しかも刻々と変化する実世界の情報をうまく処理するために、知的システムは内部に世界モデルを持ち、それを使つて環境変化を予測し、また、予測と現実の違いを利用して世界モデルを修正することで次の機会にさらに精度の高い予測をします。しかしそのモデルが人間に理解いくいものだと、与えた指示をシステムがどのようにやろうとしているのか人間が考えにくく、従つて高度な指示を安心して与えられず、結局使いにくいものになってしまいます。
そこで、人間が理解しやすい世界モデル、それを自律的に修正する学習機能を備えた知的システムを構築することを考えました。尖証システムとして、オフィス内を移動するロボットを用いたシステムを開発中です。このロボットは、人間の指示に従つて移動しながら、自分の世界モデルをどんどん更新し成長するとともに、発見したことを人間に知らせます。
■研究の目的 (自律学習する知的移動システム)
上で述べたことに基づき、新機能富士通研究室では、人間とのコミュニケーションを円滑に行い、かつ環境変化に適応するために更新の容易な世界モデルの構築と、その世界モデルを自律的に更新する機能の実現、さらに実証システムとしてそれらを搭載した知的情報処理システムの構築を目的として研究を続けています。
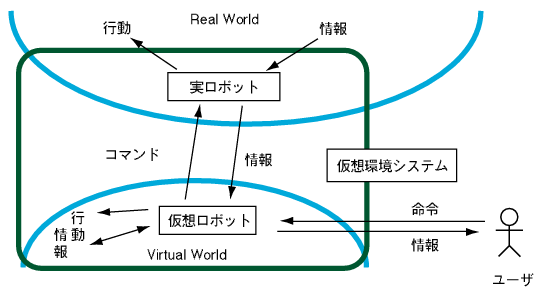
図1 仮想環境システム
■アプローチ(仮想環境システム、自律学習、成長機能、移動ロボット)
この目的の達成のために、図1のような仮想環境システムという枠組を考えました。点線が仮想環境システムで、これは仮想環境と実ロボットからなります。この仮想環境が、上で述べた世界モデルになります。仮想環境を使つてユーザの指示(移動命令)を実行する行動計画を立てます。仮想環境の中には仮想ロボットがいて、仮想ロボットと実ロボットは行動計画に従つてそれぞれ仮想環境内、実際のオフィス内を移動します。
実世界を完全にモデリングすることはできませんから、仮想ロボットの動き(予測)と実ロボットの動きは一致しません。そこで違いを見つけたら、それを新しい情報として仮想環境の中に書き込みます。この時、あらゆる違いをすべて取り込むことはできませんから、情報を取捨選択する必要があります。そして取捨選択の基準はユーザが与える指示に依存します。システムを新入社員にたとえると、仕事をこなしながら会社の仕組を理解していくように、与えられた指示をこなす(行動計画を実行する)ために覚えなくてはいけない部分(予測と違つて行動計画を変更しなければいけなくなった部分)から学習するのです。これを自律学習成長機能と名付けました。
システムと実世界とのインタフェースとして、私たちは移動ロボットを選びました。これは様々なセンサを付けることができ、ハンドを取り付けるなどして外界に働きかけることが容易であり、移動することで人間に近い視点から情報収集ができるからです。つまり仮想環境システムは、「移動する入出力装置を備えた実世界コンピュータ」です。
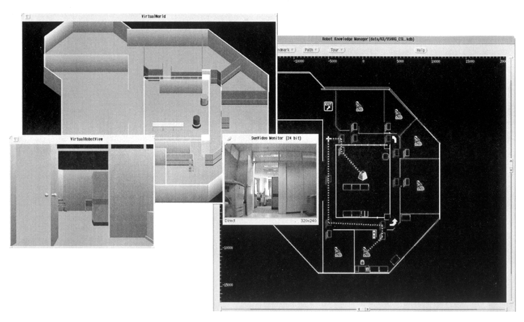
図2 仮想環境システム表示例
■現在までの成果(仮想環境システムによるシミュレーション実験)
いままでに私たちは、仮想環境と仮想ロボットを構築しました。実ロボットはまだ開発巾なので、実世界と実ロボットの部分は今はもう一組の仮想ロボットと仮想環境で代用しています。図2に仮想環境システムの表示例を示します。
仮想環境の表現法として、私たちは三次元モデルを選びました。(図2の左上のVirtual
Worldウィンドウ。) 前にも述べたとおり、予測・修正が可能で、しかも人間が理解しやすい表現方法です。この中を仮想ロボットが動きます。このようなモデルは、シミュレーションのための計算量が多くなり、実ロボットとの同期が難しくなるのですが、高速なハードウエアを使い、また実時間シミュレーション法を考案してこれを解決しました。
仮想ロボットが見た景色は、図2の左下のVirtual
Robot Viewウィンドウです。これがシミュレーションによる予測です。中央のSunVideo
Monitorウィンドウが実ロボットに積んだビデオカメラの画像です。この図では見やすくするためにビデオカメラ画像を表示していますが、実際はビデオ画像ではなく、レンジファインダによるデータを使う予定です。これは物体の形や大きさ、距離といった、移動に必要な情報がビデオ画像からより簡単に得られるからです。
図の右側のRobot
Knowledge
Managerウィンドウは、ロボットが計画した移動経路です。この経路に従つて仮想ロボット実ロボットを動かし、移動中は両ロボットのセンサ情報を比較し、大きな違い(ドアの開閉、障害物など)を発見したら、仮想環境を実環境にあわせて更新します。そして必要ならば再計画をします。ユーザはロボットが何を見、何に注目し、何を覚えたかをリアルタイムに、しかも三次元モデルという分かりやすい形でみることができます。
■今後の予定 (動的環境に適応するモデルの構築)
現在の仮想環境は、動く物(複数のロボット人間、・・・)のモデル化をしていません。従つて、そのようなものはいつも予期せぬ障害物として扱い、回避行動をとります。これでも簡単な用は足せますが、より知的にするために動く物をモデル化し、それも含めて行動計画が立てられるように仮想環境を高機能化する予定です。
人間と共存する移動型知的システムを実現するためには、多様な技術を統合しなければなりません。私たちはセンサ情報から人間が理解しやすい世界モデルを構築する機能に着目しましたが、雷総研の事情通ロボットの研究による対話を利用した状況の記号化、RWCつくぱ集中研の動的プログラミングの研究による位置同定機能などと連携して、トータルなシステムの枠組作りを考えています。
|