|
表1 光インタコネクトモジュールの報告例
LEDは特性の温度依存性が小さく、ファイバとの光結合が容易なため、当初より開発が活発である。NECより25mAの低駆動電流で622Mb/s動作可能なLEDアレイを用いて、200Mb/s/ch転送可能が報告されている。ATM(Asynchronous
Transfer Mode)交換機搭載も試みられた。AT&Tはファイバアレイの各光路長を調整して、200Mb/s、1km転送に成功している。4:
1多重分離CMOS-LSIを開発して、500Mb/s/ch動作も得ている。
LDはLEDに比べ発光効率が高く、高速動作可能なので200Mb/s以上の高速配線に有望である。しきい電流(Ith)のLD間バラツキと温度変化による発光遅延の変化が出力波形パターン依存性とスキュー要因となる。駆動回路簡素化のため、低しきい電流、高均一特性のLDアレイ開発が必須である。LD駆動(変調+バイアス)電流に温度依存性を持たせるのも有効である。LDを用いた高速転送実験は東芝より最初に報告された。
SMFのスキューは2ps/m以下と、MMF15ps/mの数分の一であり、数10m以上の長距離にはSMFが適している。LD/SMFを用いた200Mb/s/ch,
100mの高速長距離転送実験が日立より報告された。低スキュー化のためにIthを従来の10分の1以下、3mA以下のLDアレイを開発している。平板マイクロレンズアレイを用いた光結合方式により0.76ccという小型パッケージを実現した。高速転送実験は、富士通より622M,1.2Gb/s/ch、日立より800Mb/s/chと、Siemensより1Gb/s以上の報告がある。
LDの高速応答性を利用した時間多重化方式による高スループット化の報告もある。光モジュールの小型低消費電力、低価格化に有望な方式と考えられる。富士通は、155Mb/s信号に対し、4:1多重方式でスループット3G
b/sを報告した。フレームビットをCビット化し、これを基準にデータの並べ替えを行うことで、高速化に伴うスキューの問題を論理的に処理している。クロック供給方式、フレーム同期および同期回復時間低減が今後の課題である。
VCSEL(面発光LD)を用いた研究が米国を中心に活発である。VCSELは発光パターンの調整が容易で、このためファイバとの高効率光結合が可能である。ヘキ開工程が不用のため、オンウエハ検査可能等から高性能・低価格化に有望と考えられる。GaAs系材料が用いられているため、高信頼・長寿命化が今後の課題である。ARPA(Advanced
Research Project Agency)の支援で、OETC(GE, AT&T, Honeywell、IBM)とPOLO(HP, Du Pont,
AMP, USC,
SDL)が研究開発を行っている。共にスループット10Gb/s以上のWS用光リンクを目指している。Motorola社は独自にVCSELを開発しトランシーバ型レセプタクルモジュールを発表している。
VCSELを用いた光インタコネクションは、素子の高信頼性、スキューやモーダル雑音等の技術課題が現在あるが、小型・低価格化に極めて有望であり、今後一層その研究開発は活発化すると考えられる。
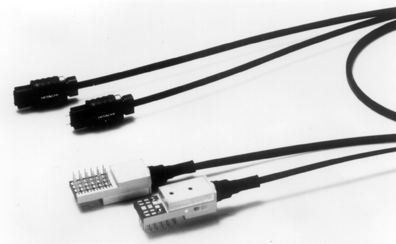
写真1 CMOSインタフェイス、+3.3V動作12チャネル集積化光インタコネクトモジュール
■システムへの適用と今後の課題
写真1は、CMOSインタフェイス、集積チャネル数12、+3.3V単一電源動作の光インタコネクトモジュールの外観写真である。チャネル構成は11データとクロック専用チャネルからなり、200Mb/s/chで100m転送可能である。1チャネル当りの消費電力は最大200mW、0~80℃まで動作可能である。光コネクタには、プッシュオン型MPOコネクタを採用している。アンフォーマットデータ転送が可能なため、様々なシステムに適用可能である。これを16個用いてスループット20Gb/
sのATM交換機用スイッチボードが報告されている。計算機へは、本プロジェクト(RWCP)で開発中の超並列計算機RWC1への適用が試みられている。写真2は、16個の光インタコネクトモジュールを用いたプロセッサノード通信用テストベッド用ボードである。20mのファイバを通したエラーフリー転送を確認し、RWC1への適用見通しを得ている。現在、光インタコネクション用プロセッサボードを開発中である。
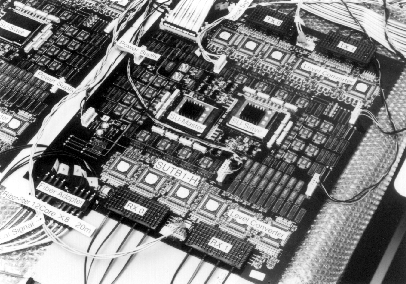
写真2 光インタコネクションを用いた超並列計算機RWC1テストベッドボード
このように光インタコネクションは実用化されつつあるが、幾つかの課題がある。その一つが、低価格化である。光デバイス、パッケージ、組み立てコストの低減が必要であるが、最大の動力は数量である。従って、汎用性のある光インタコネクションの標準化が課題となる。このハード(デバイス、実装)、システムが協力して進める必要がある。次に、高信頼化である。システムに大量導入するためには、従来の光通信用と比較して桁違い信頼性が必要である。特にレーザ、光コネクタ、光結合の高信頼化が鍵となる。光コネクタは挿抜時の劣化が問題となり、小型、セルフシーリング且つフローテング機能の開発が望まれる。
■光インタコネクションの展開と結び
光ファイバを用いた装置間・ボード間光インタコネクションは、長距離高密度配線だけでなく、LSIから入出力インタフェイスの負荷を解放し、より高性能高機能化を可能とする技術として、確実に実用化に向かうであろう。次に光ファイバが実装上の課題となり、プリント基板やマルチチップモジュール基板に光ファイバや光導波路を導入する光バックプレーン技術が必要になる。面発光レーザ、光導波路基板、光表面実装等の要素技術にブレークスルーが期待される。このような要素技術開発とともに、IC間・IC内光インタコネクション技術が立ち上がるであろう。ここでは、発受光素子の集積化も鍵となる。
図5は、これらの技術を用いて作られた3次元マルチチップ光インタコネクトモジュールのイメージである。来たるべき21世紀もマルチメデイア時代を支えるキーテクノジーに発展していくものと信じている。
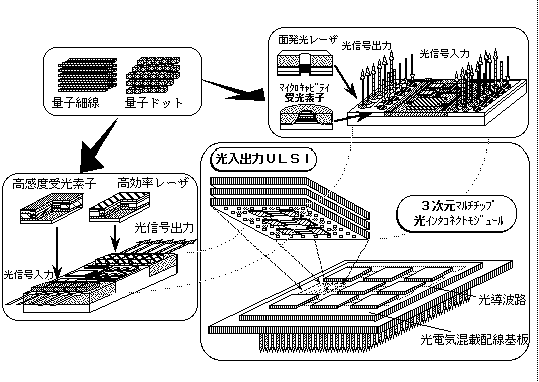
図5 3次元マッチチップIC 間・IC内光インタコネクトモジュール
これまで見てきたように光インタコネクションは、これまでの情報化社会を支え、今後も鍵となる半導体技術と、21世紀を支える光通信技術が融合し、新たな情報システムを実現可能とするハードウエア技術である。本RWCPは、我が国がこの光インタコネクション技術を発展させ、さらに世界に先駆け斬新な情報システムを提案していく格好の研究機関である。今後益々RWCPの成果を期待すると共に、この成果がわが国の情報産業発展に寄与することを願っている。
|