情報統合技術
---- 実世界知能のためのキーテクノロジー ----
 |
電子技術総合研究所
新情報計画室
麻生 英樹
|
■はじめに
人間は、生の感覚データから自然言語に至るまで、さまざまな種類の情報をごくあたりまえのように日常的に統合処理している。このことを反映して、コンピュータが扱う情報のレパートリーも、単なる数値データから、文書処理のためのテキスト、知識処理のための論理式、数式、と少しずつ拡大してきた。最近のいわゆる「マルチメディア」ブームも、その技術的基盤として、パソコンレベルの計算機でも(動)画像や音声がそれなりに扱えるようになってきた、という点が大きい。 このように、コンピュータが扱う情報の種類は確実に増加し、人間が行っているさまざまな情報処理の分野において一定の地位を占めるようになってきたが、その機能はあくまでも要素処理の代替が主であって、人間のようにそれらの多種多様な情報を適切に統合処理してゆく技術、「情報統合技術」は、未だ確立されてはいない。本格的なネットワーク社会を迎えて世界を流れる情報の種類と量が飛躍的に増加している中で、多数の情報をいかに関係づけてゆくかは情報生産の鍵である。従って、情報統合技術の必要性は今後高まることが予想されているが、その中でも特に、Real
World Computing
Programのめざす「実世界知能システム」、すなわち、実世界で人間や環境と密に協調して働けるような知的システムの実現にとって、情報統合技術はキーテクノロジの一つである。
■情報統合関連技術の流れ
情報統合技術を分類するときのカテゴリーとして、「水平統合」、「垂直統合」、「内部と外部の統合」の3つが挙げられることが多い(図1)。「水平統合」とは、視覚、聴覚、触覚など異なる情報源からの情報を統合することである。「垂直統合」とは、センサレベルのパターン情報と言語レベルの記号情報の統合である。「内部と外部の統合」は、システム内部の情報と外部環境の情報との統合である。この分類はそれほどすっきりとしたものではないが、とりあえずの作業仮説としては便利であるので、以下では、この分類に沿って関連する研究の流れを概観してゆく。
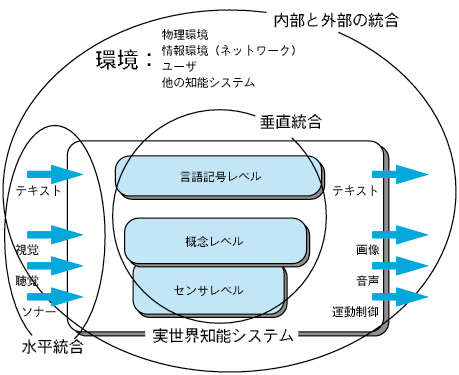
図1. 情報統合技術の分類
◆水平統合
このカテゴリーは、いわゆるセンサフュージョン技術、分散センシング技術、((動)画像と音声の統合としての)マルチメディア技術などと関係が深い。また、コンピュータビジョンの分野では、視覚情報という一つのモダリティの中において、両眼視差、陰影情報、模様情報などを統合することによって、直接観測できない外界のイメージを再構築する研究が行われてきた。仮想現実感技術においても、ユーザに視覚情報、音響情報、触覚情報などを統合的に提供することが必要であり、水平統合技術とのかかわりは深いと思われる。最近では、近未来のインターフェース技術の一つとして、マルチモーダル・インターフェースが研究トピックスとなっている。これは、システムとユーザとの間の情報チャネルの幅を、従来のキーボードベースの細いものから動画像、音声を含めた非常に太いものにすることで、システムとユーザ双方にとって負担の少ない、より快適で自然なインターフェースの実現をめざすものである。
視覚情報と聴覚情報、といったモダリティの異なる情報の組合せを扱う場合の困難はどこにあるのだろうか。視覚情報と聴覚情報の性質の違いが、統合における大きな障害になっているようには見えない。たとえば、時系列情報を扱う標準的な手法となりつつある隠れマルコフモデルや、RWCにおいて開発された標準パターン区間自由連続DPマッチング技術RIFCDPは、音声に対してと同様に、動画に対しても有効であることが示されつつある。実際に、マルチモーダルインターフェースの研究に少しだけかかわった経験から大胆に推測すると、最大の困難は、どの情報の組合せから役に立つ情報が得られるか、を見出すところにあるように思われる。
多種の情報を統合する、といっても、ある瞬間、あるいは個別の状況ごとに見てゆけば、利用されている情報はその一部にすぎない。あらゆる場面で、すべての情報を実時間で処理する、ということは現実的には不可能であるし、また必要でもない。そこで、ある瞬間、状況においてどの情報の組合せに着目するか、ということが重要な問題になる。従来は、モダリティというアプリオリな情報の分け方が与えられており、それに沿って処理技術が構築されてきたのであるが、その壁を壊して相互作用の規制が緩和されてみると、どのような状況でどの情報をどう組み合せると、どんなうまい話があるのか、が案外わからないのである。この意味で、「情報統合とは実は情報の動的再分割である」と言えるかもしれない。これと関係した問題として、異なるセンサから来た情報が同じ対象についてのものであることをどのようにして知るか、という問題がある。両眼立体視における対応づけの問題が典型的であるが、センサの数が増えることによって、この問題の困難さも増すと思われる。
これらは、多くの情報の中から状況に即して有意味なチャンクを切り出すという意味では情報分節の問題であり、どの情報(の組合せ)に注意するか、という意味では、いわゆる「注意」の問題の一つでもある。一度ある対象に向けた注意を維持するための技術については、トラッキング(追跡)などいくつかの研究開発がなされているが、注意の単位やきっかけについてはそれほど明らかになっていない。実際に、多種の情報の処理を必要とするようなタスク(たとえば車の運転、リアルタイムゲームなど)下での認知科学的な人間研究や、脳科学からの知見なども参考にしつつ、有効な情報の組合せを発見し、実現してゆくことが必要である。それとともに、システム自身が、多種にわたるセンサ情報の空間を、タスク依存、状況依存的に自己組織してゆくような技術の研究開発も重要であろう。
もう一つの困難は、データの蓄積の不足である。特にパターン処理の分野では、音声データ、手書き文字データなど、標準的なデータの収集とデータベースの確立が分野の発展に大きく寄与してきたことが明らかである。しかし、複数のモダリティが有効になるような状況についてのきちんとしたデータベースはまだそれほど存在していない。したがって、データベースの作製は重要である。これと同時に、多様な情報の組合せについてデータベースの整備を期待するのは難しい面もあるため、システム自体が能動的に必要なデータを収集し、それを用いて学習してゆく技術が重要であるだろう。
現在この領域に関して最も鋭い感覚を持っているのは、おそらく、リアルタイム対戦型のゲーム製作および映画、CG、アニメーション製作の関係者であると思われる。このような領域で蓄積されているノウハウを技術化するような研究も重要かもしれない。
◆垂直統合
赤いりんごがあったとしよう。その事態を記述する表現は赤いりんごのカラー写真、白黒写真、ハイパーリアルに写生した絵、絵本の絵、漫画の絵、「赤いりんご」という言葉、というようにたくさんある。水平統合が、赤いりんごの色、味、といったような多様性の統合を問題にするとすれば、垂直統合は上記のような、「精度」(この言葉はたぶん不適切であるが)の異なる表現の統合を問題にする。
この世界は非常に複雑であるため、一つの記述レベルですべてを記述・処理することは現実的ではない。すなわち、抽象化という操作が不可欠であり、写真も漫画も、そして文章も日常的に利用されている。このようなさまざまな抽象レベルの表現を扱うために、まず、どのような抽象表現をどう構築するか、という問題、そして、多数のレベルの情報が与えられたときに、処理、あるいは情報の流れ方をどう制御するか、という問題が生じる。
後者の、記述レベルの異なる複数の表現を利用した処理の制御の例としては、実時間連続音声認識システムがイメージしやすい。そこでは、音声波形という生データからスペクトル情報が抽出され、音素レベルのベクトル量子化コードに変換される。さらに音素の間の関係である単語辞書と、単語の間の関係である文法を用いて解析が行われ、最終的に認識結果が一つの文として出力される。画像理解の研究においても、画素レベルの明度からまとまりをもつ要素領域が抽出され、要素領域間の関係であるイメージ辞書と、イメージの間の関係である画像文法を用いた解析が行われ始めている。これらのシステムの多くでは、処理は階層的に、ボトムアップに行われているが、たとえば、トップダウンな予測とボトムアップな処理との統合は常に課題とされてきた。
水平統合に関連してさらに深い問題は、複数の表現が複雑に相互照応したような構造を持つ表現体系の解明あるいは構築である。この方向の研究としては、人工知能における「シンボルグラウンディング(記号接地)問題」があげられる。これは、主に自然言語理解の研究から生じてきた問題意識で、名付け親である
Harnadによれば「形式的な記号システムの意味的解釈をどのようにしてシステムと環境に内在する固有のものに接地するか」という問題であり、「記号の意味」という古くからの大問題に直接関係している。この問題を逆にパターン的なセンサ信号の側から見れば、「センサ信号の空間をいかに分節して記号的な表現との関係をつけるか、あるいは記号的な表現を創発させるか」という問題であり、古くからの課題である「パターン認識」や「パターン理解」と直接的な関連を持つ。
これはシステムが本格的に「言葉の意味」を扱う場合に最も重要になってくる技術である。しかし、自然言語まで到らないにしても、離散的で組合せ構造を持てるような内部表現が有効な処理についてもある程度は必要になる技術である。たとえば、知能ロボットの行動計画などがそれにあたる。ロボットに、自分が思う通りの行動をさせようと考えたときに、最も単純な方法は、現在のプレイバック型の産業用ロボットが行っているように、非常に微小な時間間隔でロボットの位置や関節角度を指定することである。これに対して、「コップを取れ」というような(半自然言語的な)レベルで命令できるためには、「コップ」という記号を自分の視覚系から得られる情報と対応づけなくてはならないし、「取る」という記号を自分の運動制御系の制御信号と対応づけなくてはならない。たとえば同じ「取る」であってもコップを取る場合とスプーンを取る場合とでは具体的な運動制御信号はかなり異なるであろうし、同じ「コップを取る」であってさえ、コップの形や姿勢によって具体的な制御信号はかなり異なるのである。このように複数の表現の間の高度に文脈依存的で複雑な関係を、どのように生成、管理、維持するかという問題は、情報統合の中でも特に難しい問題である。
◆内部と外部の統合
このカテゴリーもまた知能ロボットの研究との関係が深い。システムに知的な振舞いをさせる場合に、システム内部に外界のモデルを持たせ、それを用いた予測や推論によって適切と思われる行動を選択させる、というのは自然な考え方である。しかしながら、ここで生じる問題は、「どのような内部モデルを持つべきか」である。大きすぎる、あるいは精密すぎる内部モデルを持つと、現実の外部環境との一致性の維持や予測や推論の計算コストが問題になる。反対に内部モデルが貧弱すぎると、得られる行動が反射的なものに留まり、知的さに限界が生じるだろう。
MITのBrooksらは、昆虫のような単純なレベルの知能の観察をモチーフとして、たとえ内部モデルが貧弱であっても、外部環境から実時間で得られる情報と内部モデルとを上手に統合して利用することによって、一見複雑で知的に見えるような行動を実現できる可能性があることを示した。この内部と外部の統合を実現し、システムをリアクティブにするために提案されたアーキテクチャが「サブサンプション・アーキテクチャ」である。
このような内部モデルに関する議論の源流を、たとえば
1960年代の「サイバネティクス」に遡ることができる。そこで提出された「フィードバック制御」のアイデアは、制御行動の結果を内部モデルによって予測するのではなく、実際にやってみた結果として制御対象自体に計算させる、という内部モデル無しの制御であり、リアクティブなシステムとは、この概念をより高速で密な情報の流れを前提として拡張したものであると見なすこともできるからである。
ここでの課題は、内部モデルからの情報と外部からその都度補給される情報とをうまく反応させて安定なパターンを生成させることである。つまり、内部と外部を統合する適切な情報ループの設計が問題である。
内部と外部の統合は、情報統合全体の中間目標であるともいえる。すなわち、水平統合や垂直統合はこれを実現するための手段として使われる。実際、「サブサンプション・アーキテクチャ」には、水平統合や垂直統合への配慮も含まれている。「知的システム」における内部と外部の統合の重要性は、たとえば
MaturanaとVarelaが提唱するシステム論「オートポイエーシス」でも(より過激に、内部と外部という分け方を消去するという形で)強く主張されている。人工知能におけるマルチエージェントの協調形成、認知科学におけるGibsonの「アフォーダンス」、「解釈学」などとも関連し、広がりを持つ課題である。
◆統合のための一般的な技法
ここまで、情報統合の分類に従ってそれぞれのカテゴリに関連する研究の流れを見てきたが、より一般的な立場から、情報統合に向けた情報処理アーキテクチャ、プログラム言語、モデルの研究も行われている。
たとえば電子技術総合研究所の橋田は、知的システムの設計の本質を複雑かつ状況依存的な多様な情報の流れの実現、と捉える立場から、そのための一般的設計法として制約指向の設計を提唱し、それに基づく統合的な音声対話システムを実現している。これは「情報の間の関係だけを処理手順を捨象した形で記述しておき、具体的な処理手順は現場でシステムを動かしながら決める」というもので、「宣言的プログラミング」などとも関係が深い。北海道大学の赤間は宣言的プログラミング言語を提案し、自然言語理解の例題において、複数のレベルの知識の統合の創発を示している。RWCの岡の提唱する「場による統合処理」も、情報の表現の粒度はかなり異なるものの、制約指向という意味では共通性がある。
脳科学と認知科学から生まれたコネクショニズムもまた、「情報統合」のためのアーキテクチャの探求であると言える。たとえば、記号とパターンの統合のための具体的な提案として、Smolenskyのテンソル積ネットワーク、東京農工大学の大森らによる「PATON」などがある。人工知能の分野においては、Minskyの著書「心の社会」や、ネットワークの発達による分散人工知能技術の進展を背景として、複雑なシステムの実現法として、「(マルチ)エージェントベースト」という概念が提唱されており、たとえば岡山大学の松山らはこの立場から
Computer
Visionにおける情報統合について考察している。電子技術総合研究所の中島らによる「有機的プログラミング」は状況理論から触発されたもので、状況認識と状況依存処理を組み合せることによって状況依存的行動を実現するためのものである。脳における比較的速い情動判断系(大脳辺縁系)と遅い認識系(新皮質)との組合せを想わせる。また、東京大学の金子、北海道大学の津田、SONY
CSLの谷らは、非線形ダイナミカルシステムに基づくアイデアを深めている。
一方、大量で多種かつ不完全な情報を扱うという意味で、あるいは「(内部)モデルによるデータの解釈」という意味でも、統計学は老舗である。特に、最近の計算機の進歩によって、計算機に強く依存した確率的手法が発達してきていることもあり、確率・統計的な理論と技法の蓄積が、情報統合の技術に活用できるのではないかという期待は大きい。
■結び
情報統合に関連する研究の流れについて概観した。
RWCプログラムは、計画当初より、「情報統合」を一つのキーコンセプトとした研究開発を進めてきた。プログラム後期においては、核となるシステムイメージとして、「マルチモーダル対話システム」、「自己組織情報ベース」、「自律学習システム」、「能動知能システム」の
4つを取り上げ、さらに研究開発を進めて行く予定である。これらのそれぞれについては、また別の機会にこの場で紹介されることを期待したい。
大量の異種表現を「結び合せるパターン」を探り、重要で安定な「パターン」に注意をあてる「情報統合技術」は、人間を含む環境とシステムとの間の相互作用を密にし、人間にとって親和性の高い情報処理技術を実現してゆくために必須な技術であるとともに、学問的にも大きな広がりを持つテーマである。さらなる研究の発展を祈念する。
謝辞:この記事を書くにあたり、RWCPによる「情報統合ワークショップ」および「記号とパターンの統合ワークショップ」での議論が大変役にたちました。ワークショップ参加者のみなさま、特に、統計数理研究所の伊庭幸人さん、電子技術総合研究所の中島秀之さん、
RWCの岡隆一さん、東京農工大の大森隆司さんに感謝いたします。
|