--- 再委託研究室 ---
|
Erlangen大学における研究〈パターン認識講座〉
|
Volker Fischer
(Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nurunberg)
|

|
Dr.Volker Fischer
Erlangen大学 パターン認識講座
|
当大学のパターン認識講座は、Friedrich-Alexander大学計算機科学科の講座として1975年に創設され、工学博士H.Niemann教授が創設当初より講座主任を務めています。
パターン認識講座の一般研究分野は、信号処理、連続音声認識、対話システム、自然言語処理、画像処理、画像分析、知識ベース画像解釈、ロボティクスです。現在、上記分野に17名の研究スタッフを擁し、内10名はBMBFあるいはドイツ研究基金(DFG)の後援による共同プロジェクト、またはESPRITプロジェクトに参加しています。
これまでの画像処理研究では、低レベルの画像処理と、意味ネットワークを使用した知識ベース画像解析を扱い、医療アプリケーション向け画像理解システムを開発しました。現在の研究は、3次元オブジェクト認識とセグメンテーション、統計的、幾何学的3次元モデルの生成、動きの検出と記述に及んでいます。能動視覚の研究により、閉ループ・リアルタイム・オブジェクト追跡システムが開発されましたが、この研究を高レベル視覚にまで拡張し、今後の研究テーマとしていく予定です。
これまでの発話認識研究では、企業並びに他大学とのBMFT共同研究プロジェクトにおけるインターシティ列車問合せ用ドイツ語発話理解対話システムの設計と実装を行いました。この研究は、現在、携帯式発話翻訳システムの開発を目指すVERBMOBILプロジェクトに引き継がれています。単語認識、多音字、ポリグラフの併用により、VERBMOBIL単語認識テストで優れた結果が得られました。
ESPRIT SUNDIALプロジェクトでは、単語認識と対話の研究を行いました。開発された稼働バージョンの対話システムは、現在、電話回線での科学的評価に使用されています。また、対話システム研究の多言語多機能システムへの拡張を目的とする新しいプロジェクトを最近開始しました。今後の研究では、韻律解析、F0予測の改良、韻律解析の対話制御への統合、韻律による成句境界の検出を扱っていきます。
1994年、本講座は、Real World Computing Partnership (RWCP)の再委託機関になりました。RWCプログラムにおける長期研究目標は、実世界へのアプリケーションに必要なマルチモーダル情報の理解のための統一方式の開発です。現在のRWCP研究グループは、Niemann主任教授、V.Fischer博士、J.Fischer工学士の3名で構成されています。
1995年6月、我々は、東京のTEPIAで開催されたRWCシンポジウムに参加して、リアルタイム発話理解システムのアイデアを発表しました。この機会にRWCPの他の研究プロジェクトの知見を得ることができたことは、RWCプログラムの新規参加者である我々にとって極めて有意義でした。また、1995年度は、2度にわたり日本からの派遣団がErlangen大学を訪れました。1995年9月には、RWCPの伊藤慶明氏、岡隆一氏および大阪大学の山下教授が我々の研究室を訪れ、発話理解研究の主要課題について討論しました。また、その後の、研究調整および中間検査のためのRWCP研究企画課
渡辺昭裕氏、国際部 橋本一俊氏の訪問は、RWCPの事務処理上の手続き等を理解する上で有益でした。
発話は、1990年代末までに、コンピュータ通信の上で最も重要な入力源のひとつになると期待されているため、RWCプログラムにおける最近の研究では、主にリアルタイム発話理解システムの開発を進めています。我々の研究の一般的な枠組は、ドイツのインターシティ列車時刻表についての問合せに回答する機能を持つ発話理解システムに顕著に表れています。このシステムは、公衆電話回線に接続されているため、システムモジュール(単語認識、韻律情報など)の改良と新しいコンポーネント(確率対話モデルなど)の開発の双方のための、大量の自然発話サンプルを収集することが可能です。
発話理解では、利用者が期待する反応を得るために、発話信号をシステムのタスク領域の内部表現にマップする必要があります。不完全な単語認識率とシステムの言語知識ベースに内在する曖昧さから、このマッピングにも曖昧さが残るため、最適マッピングの計算には大規模な検索空間の探索が必要になります。
リアルタイム発話理解への我々の基本的アプローチは、反復最適化手法(シミュレーティッドアニーリング、great delugeアルゴリズム、遺伝的アルゴリズムなど)と、下位概念レベルでの知識ベース並列処理の利用です。反復最適化を利用すると、通常、処理時間が一定していないリアルワールド・アプリケーションに、「任意時間利用」能力という重要なシステム動作が得られます。意味ネットワークを使用する知識ベースの並列最適化と超並列処理により、「任意時間利用」機能を改良することができます。従って、並列最適化によって検索空間のさまざまな部分を同時に探索できるようになり、知識ベース超並列処理により、反復1回当りの計算所要時間を減らすことが可能になります。
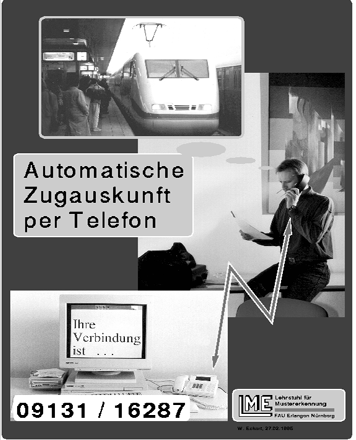
リアルタイム発話理解実験システム
"Call +49 9131 16287 for German Interrcity Train Time Table"
現在、最初の稼働バージョンの評価を進めており、高速ワークステーションのローカル・エリア・ネットワークへの並列システムの実装も、最近開始しました。このプロトタイプ・システムから得られる成果によって、最適化アルゴリズム並びに検索空間を縮小するための並列制約処理をさらに完全なものにできるでしょう。
RWCプログラムにおける我々の今後の研究は、並列発話理解システムの更なる改良と、マルチモーダル情報処理における長期研究が中心となる予定です。 発話理解システムを完成させるためには、研究を対話レベルに拡げる必要があります。更に、リアルタイム機能を達成するため、インクリメンタルな知識処理に取り組まなければなりません。そのため、我々は、発話信号の意味のある部分の境界を言語解析に与えるために、韻律情報の利用を検討していく予定です。
我々の意味ネットワーク形式と反復制御アルゴリズムは、すでに画像理解タスクで正常動作が確認済みであるため、このアプローチはマルチモーダル情報の知識処理に利用できるものと確信しています。また、最近、ステレオヘッドに対する読唇と自然言語のインタフェースを使用して発話認識を強化するためのコネクショニスト・アプローチなど、異なる情報源の統合に関する準備的研究も開始しました。
|