情報統合と21世紀の技術開発
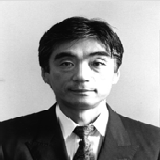 |
慶応義塾大学 理工学部
学部長 安西 祐一郎
|
人間がふだん行っている情報処理のように、あるいはそれを超えて、実世界の多種多様な情報を「柔らかく」処理する新しい情報処理技術の体系、それがリアルワールドコンピューティング技術である。
他方、人間が日常行っているほとんどすべてのことは、情動、感覚、知覚、記憶、思考、言語、運動、その他多くの情報処理能力が「重なりあって」発現している。実世界の多様な情報を「柔らかく」処理する人間の能力は、多くの情報処理が時空間的に整合し、融合されることから現れてくる。
そうだとすれば、リアルワールドコンピューティング技術は、少なくともどのようにして多種多様な情報の統合処理を行うかという問題を扱わなければならないだろう。
情報の統合については、現在でも多くの分野でさまざまなアプローチがとられている。たとえば、いわゆるマルチメディア技術の依って立つ一つの基盤は、多種多様なモダリティの情報が、表現としてはデジタルに、伝送形式についてはパケットに統合されている点にある。センサフュージョンもまた、種々のセンサから得られる異なるモダリティの情報を融合する。認知神経科学においてホットな話題となっているBinding
Problemもまた、異なるモダリティの情報処理が、脳のどこで、どのようにして統合されているのかという問題である。さらには、情報統合の最も基本的な問題の一つである「可能な文脈を前もって特定できない問題(つまり実世界の問題!)について妥当な計算量で処理を行う方法」についても、多くの研究がなされている。現在、リアルワールドコンピューティング・プログラムのもとに「情報統合ワークショップ」があって、情報統合の問題について定期的に活発な議論が行われている。
さて、試みに情報統合の問題をさらに拡大して考えると、一人ひとりの人間が扱う情報を超えて、建物、車、道路、都市など、空間的に広がった対象の情報統合という問題が考えられる。たとえば、都市を人間になぞらえると、道路や建物が骨格や筋肉に、水道、電力、ガス供給網が血管に対応し、インターネットのような情報ネットワークが神経系に対応する。しかし、たとえばライフラインや道路の寿命、あるいは地震波に対する建物の状況のような都市の状態をリアルタイムで検知する感覚・知覚機能や、外部からの(比喩としての)病原菌を撃退する免疫機能はほとんどなく、緊急事態に対処するための危機管理機能も、特に我が国では不足している。
少なくとも都市のような社会インフラから直接得られる情報と人間の処理している多くの情報をネットワーク上で統合することによって、さまざまな意味で安心して暮らせる生活を保障したい。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。…」川端康成の『雪国』が書き始められた1935年の頃、トンネルや汽車や信号所を作り、雪崩報知の電力線をトンネルの南北に引いたのは、当時の先端技術者たちであった。それから100年後、21世紀の技術開発はどのようになされているだろうか。
それは、『雪国』の生活を世界につなげた当時の技術開発と同じように、安心できる社会の実現を願う、意欲ある人々の手によって遂行されるであろう。そして今度は、センサ情報、言語情報、その他いろいろな種類の情報を適切に統合する技術がきわめて重要な位置を占めるようになるであろう。なぜなら、21世紀においても、技術開発の目的は人間が安心感をもって暮らせる社会の実現にあり、人間の特徴は、未来の行動を決めるために一度に処理できる情報の量がきわめて限られていることにあるからである。
リアルワールドコンピューティング技術の開発が、このような意味でも21世紀における技術開発を先導する役割を担ってくれることを期待したい。
|