オプトエレクトロニクス技術
-------- 情報化社会へのインパクト --------
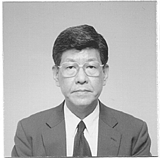 |
東京大学 工学系研究科
教授 神谷武志
|
■はじめに
21世紀の情報化社会を支えるハードウエア技術の柱の一つが半導体技術であり、また光技術がもう一つの柱であることは大方の一致した見方であろう。光の物理の歴史は遠くニュートンの時代にさかのぼり、また写真の発明から数えても1.5世紀になんなんとしているにも関わらず高い期待が持続している理由は、大きく分けて二つある(図1)。
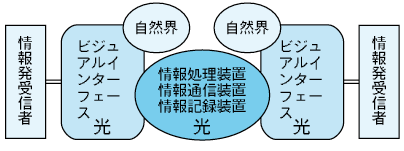
図1.光と情報
一つは情報を担う物理的媒体として見たとき、光は許容される情報容量が極めて大きく、また情報の伝送速度が極めて早いことによっている。もう一つの理由は、情報装置と人間のインターフェースにおいてもっとも大きな情報レートを担う視覚情報が、今後ますます支配的になると考えられるからである。現在すでに実用化している例で言えば、前者には大容量かつ長距離の光ファイバ伝送技術や、忠実な情報の記録再生を実現したディジタル方式の光ディスクメモリーが属し、また後者では、テレビジョンおよびビデオなどの動画像ディスプレイや、さらに進んで最近の映画やテレビ番組の制作に急速に取り入れられているコンピュータグラフィクス等が挙げられる。
さらにこれからの発展を考えると、光による情報のインプットおよびアウトプットと画像情報の処理、伝送、蓄積が複合化した、より総合的な情報システムへと発展することが予想され、そこでは光の役割はさらに大きくなるものと期待される。このような夢に向かって、現在の光エレクトロニクス研究はどこまで進んでおり、どこへ向かって走っているのだろうか。身近な話題を紹介するとともに、それらの及ぼすインパクトについて考えてみることは無駄ではあるまい。
■マルチメディア時代の光技術
20世紀後半に実用化した情報化の主役は、テレビ放送、CATV、コンピュータ、光ファイバ長距離電話回線、衛星通信、コンパクトディスク、ビデオテープなどであり、まさに電子と光の技術を柱とした情報通信の革命、普及の歴史であったが、そのカテゴリーは、放送、コンピュータ、公共通信、情報記録、ディスプレイなどがそれぞれ技術としてもビジネスとしてもほぼ独立した形で成立していた。これらは情報の形態でいえば数値情報、文字情報、音声情報、画像情報などであり、相互変換は不可能ではないものの簡単でなかったことが、縦割りの技術体系の展開を促したとみることができる。近年これらの情報の形態がほとんどすべてディジタル化されるようになり、ディジタル情報の変換、多重化、伝送、識別、処理などの機能を備えたシステムにおいては、情報の形態によらずに総合的に対処できるような状況が生まれてきた。これがマルチメディア情報システムの考えであり、総合ディジタル情報網(ISDN)という表現で1980年代にそのコンセプトが登場した。
1990年代なかばの今日、既にマルチメディアパソコンとかマルチメディアLANシステムのような商品が出回るようになっている。ただしそれらは、まだ本格的な展開に先駆ける初期的な試みというべきもので、パーソナルコンピュータの場合、CDROMによる画像情報の取り込みおよびディスプレイやディジタルサウンドによるステレオ音響出力のついたものを、マルチメディアPCと呼んでいるようである。
21世紀に期待されるマルチメディアシステムの夢は、そのようなシンプルなものだけではない。もっと広くかつ深くわれわれの職業生活に、またプライベートな生活に入り込んできて、われわれの知的生活を一変させるようなものであることが予感される(図2)。具体的にどこまで情報化が進むのかは予断を許さないところがあるが、最近急速に普及しているインターネットによる自由な情報の流通とこれを利用した新しい仕事のやり方は、21世紀の情報化への方向を指し示している。
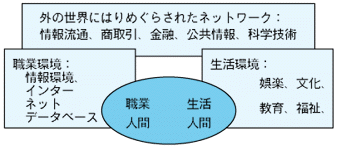
図2.未来システム
一つの大きな潮流は、世界中どこでも誰とでもほとんど瞬時にコミュニケーションができるようになったこと、したがって機関にまたがった共同作業が現実化したことである。もうひとつの特質は、電子ネットワークの上に仮想的な巨大バザールが成立し、もの(情報)の売り手と買い手が自由に交流することが可能となりつつある、という点である。最近はそのような商取り引きに関わる支払いを、電子マネーで行うところまで進みつつある。現時点でのインターネットの情報の転送速度では、記号データを実時間で送るのが精一杯で、画像データの転送には多くの時間が必要とされるが、これも時代とともに解決されるであろう。
商業の取り引きからさらに進んで、金融や保険の契約、流通や交通機関のロジスティクス、公共機関の住民サービス等、職業生活や消費生活に広く入り込むのは時間の問題であるとされる。また、娯楽、文化、教育や医療、福祉、環境等への展開も末広がりになるものと予想される。これらは国内ネットワークだけでなく、世界に開かれたシステムとして発展するので、生活のすべての面でのオープン化が進んでゆくと期待できる。
これらの幸せな夢のもう一つの側面として、重要情報の漏洩に対する安全性の確保の問題がある。これまでにも、コンピュータシステムが通信ネットワークに接続された結果として外部のハッカーによって侵入され、種々のいたずらの対象とされたことがあったが、重要な契約、取り引きや守秘義務のあるデータの取扱いについては、高度の安全性確保の対策が講じられなければならない。暗号技術、情報拡散技術の積極的導入によって、その解決がはかられようとしている。
ここで光技術に寄せられる期待を簡単にまとめて表現すると、(1)十分な余裕のあるチャンネル容量を確保できる高速度信号転送、分配技術の確立、(2)大量の情報の中から意味のある情報を手際よく選び出し、処理する技術の確立、の2点が最も重要になると思われる。
■光情報ネットワークの展開
現時点で商用のディジタル通信回線によるデータ伝送の速度は、国内で最高毎秒150メガビットである。これらを束ねた幹線通信回線の最大伝送容量は毎秒10ギガビットであるから、約60チャネル分を通すことができる。一方カラーテレビを帯域圧縮なしでディジタル化すると、1チャネル当たり毎秒100メガビット必要である。ディジタル化された動画像を常時10チャネル以上受けるには、各家庭あたり少なくとも1ギガビットが要求される。もし1000家庭をひとかたまりとするCATVないしLANを構築すると仮定すれば、総伝送容量は毎秒1000ギガビット、すなわち1テラビット級の信号伝送能力が要請される。将来のマルチメディアシステムでは、ビデオオンディマンドのようなサービスのほかに買い物や諸契約等もできなければならないから、十分な信号伝送容量を確保することが必要課題である。
冒頭に述べたように、幸いにして光技術には3重の意味で信号を多重化することが可能である。即ち時間分割多重方式(TDM)、波長分割多重方式(WDM)及び空間分割多重(SDM)がそれである(図3)。信号を遠くへ届けるには伝送路の損失が最小となる波長を選ぶ必要があるが、石英光ファイバの損失は波長1.3および1.5ミクロンで極小となるので、中、長距離システムには必ずこの波長帯が利用される。現時点での研究開発の最先端では時間軸上の最高値は毎秒200ギガビットであり、また波長多重では1チャンネルあたりの伝送速度を毎秒1ギガビットとして1000波長多重の計画も検討されている。空間並列の巨大システム計画には現実的なものはまだないが、通常のテレビ受像機の画素数の並列度を仮定すれば約25万チャネル並列が可能であり、チャンネル毎に30メガビット/秒を仮定すると全スループットは毎秒7.5テラビットに及ぶ。これらの未来技術には、すでに利用可能となっている要素と未発達の要素が混在しているため、今後の継続的な開発努力が不可欠である。
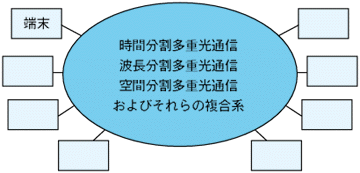
図3.ネットワーク
■基幹光要素技術の開発:光半導体および 光機能部品を中心として(図4)
高度な光システムを構築する上でその性能を左右する最も重要なデバイスは、丁度集積回路においてトランジスタがそうであったように、光能動デバイスである。具体的には、半導体レーザ、フォトダイオード、および光変調器で、主として化合物半導体で作成される。実際、低損失の石英光ファイバによる長距離光通信が成功したのは、Inp系の長波長半導体レーザの開発、実用化に負っていたし、低価格の光ディスクプレーヤーが世界中に普及したのも、GaAs系の可視光レーザを大量生産できる均一大面積エピタキシアル結晶成長技術の確立によるところ大である。半導体レーザ技術の展開も第3世代に入ったが、その勢いは衰えを見せていない。
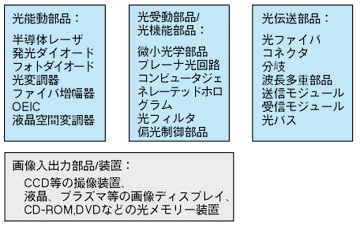
図4. 光要素技術
1980年後半から1990年代前半にかけての第2世代半導体レーザでは、高効率の量子井戸構造の導入、波長選択性と高効率を両立させる歪超格子構造の導入などが果たされ、単一モードのDFBレーザの普及や、高出力のエルビウムドープファイバ増幅器を励起する数百ミリワットの高出力レーザの実用化が進められたが、現在のホットな研究ターゲットの一つは、入出力結合の容易な面発光レーザの実用化とこれによる空間並列インターコネクションの普及である。
第2のトピックスとしては、ファイバトゥーザホームや各種端末機器への適用が容易な低価格、高安定なメインテナンスフリーレーザおよびそのアレイ構造モジュールの実用化である。
第3の課題は、より高性能化を目指した半導体レーザからの極限的高速度信号を可能とする高繰り返しの超短パルスの発生と、制御および半導体レーザ増幅器の非線形性等を利用した高速のスイッチングや波長変換の試みがある。受光系においても高速化の追及、使いやすさの追及が進められているが、これと並んで画像入力機器としてのCCDの普及は目覚ましいものがある。
光システムが高度化すればするほど回路実装の負担は大きくなる。微小光学部品、導波路型集積光学部品、コンピュータジェネレイテッドホログラムやこれらをもとにした機能光学部品の役割はますます重要になってきた。光ファイバの製造で成功を納めたVAD法を平面構造へ適用するCVD法がNTTによって開発され、プレーナ光回路(PLC)として各種応用の試みが続いているが、WDMの高度なモジュールの実現にはなくてはならないものとなりつつある。さらにかつてカラーテレビの視覚特性の飛躍的向上と普及のブラックマトリックススクリーン技術が革命的な役割を果たしたように、画像入出力装置においても各種の機能性フィルタリング、アダプティブオプティクス、新方式ディスプレイなどが歴史的展開の鍵を握る可能性も高い。このような観点から、液晶技術、プラズマ技術や真空マイクロエレクトロニクス技術の展開からも目が離せない。
光技術の展開を予想するには、当然のことながら電子装置とのインターフェースが重要となる。場合によっては光デバイスを駆動するドライバーICの成否が全体のパフォーマンスを決めるといっても良い。光インターコネクションモジュール設計、OEIC設計等においては特に重要である。材料面からは集積回路を担うシリコン材料と光デバイスを担う化合物半導体を一体化する試みが続けられており、ヘテロエピタキシー結晶成長技術に加えて、密着張合せ法の好データが報告されるようになってきた。
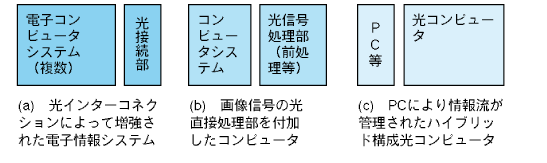
図5. 光情報処理
■光コンピューティングおよび光インターコネクションの試み
光と情報を直接結びつける概念として光コンピューティングがある。レーザの発明直後からアナログコンピューティング、ディジタルコンピューティングの諸方式の提案がなされ、実験的な試みも積み重ねられてきたが、小規模な光情報システムを除いては実用化に達したものは少ないのが現状である。一方で光の持つ潜在的なポテンシアルは依然として高く、特に並列の画像信号入出力を支える並列伝送、並列処理系を光によって実現できれば、高度な処理をほぼ実時間で遂行できることになるので、この分野への関心は引き続き高い状態である。
特に我が国では、本プロジェクト(RWCP)の主要な柱の一つとして光コンピュータが取り上げられ、産官学の活発なグループへの支援がなされていることや、1996年4月に光コンピューティング国際会議(optical
computing)と交換フォトニクス国際会議(photonics in
switching)が仙台で合同開催されるということも刺激となって、国内、国外にむけてすでに相当の情報発信がなされている。
光コンピューティングをシステムとして考えるときに、必ず電子的なコンピューティングとの関係を整理しつつ研究対象を絞ってゆくことが重要であり、電子的情報処理、および電子情報記憶技術の進歩にともなってそのインターフェースも変わって行く(図5)。したがって、基本となる光コンピューティングの原理は継続的であっても、インプリメントするのに用いられる技術の進展によって全くといってよいほど新しい機能を盛り込める可能性がある。これらを想定して、光半導体、液晶、CGHなどの新技術の展開が図られている。
■結び
光技術の展開は急速であり、また広がりも増し続けている。レーザおよびオプトエレクトロニクスの初期のように、一研究者がその全容を把握することは容易でなくなった。研究ターゲットも、ともすると絞り込まれた目標に向かって狭く深く突き進むタイプのものが主流となりがちである。未来型の研究プロジェクトや国公立の研究機関、および大学においては、樹も森も見る研究方針を立てるように気を引き締める必要があろう。
我が国が情報化の先頭に立ち、高付加価値産業の発展に貢献する情報基盤技術研究のターゲットとして光エレクトロニクスがますます輝きを獲得するべく、関係者のひとりとして今後も微力を注ぎたいと思う次第である。
|