米国出張報告
出張者: 末広尚士(TRC能動知能研究室)
出張期間:1995.8.3 - 1995.8.14(12日間)
訪問先: Intelligent Robots and Systems(IROS)'95 参加
ペンシルバニア大学グラスプラボ
CMUロボティクス研究所
MITAIラボ、MIT機械工学科ロボット関係研究室、メディアラボ
今回の出張はピッツバーグで行なわれたIROS'95
への参加が主な目的で、それに合わせて会議前にフィラデルフィアにあるペンシルバニア大学グラスプラボ、会議中に CMUロボティクス研究所、会議後にボストンにある
MITのロボット関連の研究室を訪問してロボット研究の動向調査を行なってきました。
まずメインのIROS'95は、発表論文総数268件で4つのパラレルセッションでした。論文の地域別内訳は、米国
125件、アジア100件(日本約80件)、欧州43件でした。この分野は日本の研究が高いレベルにあるのでこのような海外での国際会議でも日本人が多数参加しています。会議の副題はHuman
Robot Interaction and Cooperative
Robotsであり、我々の研究室が目指している人間と共存するロボットという方向が世界的な潮流であるということが確認できました。しかし、 Human Robot
Interaction and Cooperative Robotsのセッションは1
つだけであり、内容がそれにマッチした論文はその中でも1つだけでした。私の論文もまだマルチエージェントによるマニピュレータのサーボの実現という内容であるため分散システムのセッションに分類されていました。人間との共存というのが大きな流れではあっても実際のロボットシステムを構築していくというのは、なかなか大変なものであるというのを改めて認識させられました。
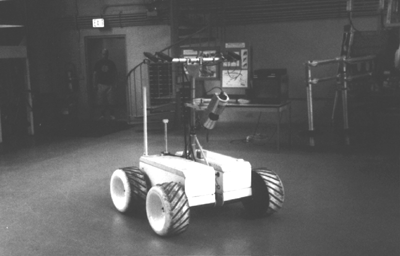
今回の会議のジェネラルチェア(2人の内1人)はCMUの池内教授でした。彼は電総研0Bでもあり私の1年間CMUでの在外研究のホストでした。夜は彼に招かれ会議場のホテルの大部屋で、池内教授の手作りワイン(注)に興じながら、さまざまな国籍の人々と親交を深めていました。
会議前に訪問したペンシルバニア大学グラスプラボは
Bajcsy教授が率いているグループです。ラボの名前からはハンドの研究が中心のような印象を与えますがハンドの研究はやっておらず、移動ロボット、複数ロボット協調、視覚、オプティカルフローを用いた動視覚、注視制御のmacro-micro協調、マニピュレーションスキルなどそれ以外のロボット全般に渡って手広く研究を行なっていました。以前RWCつくば研にも来訪したこともあり電総研のロボットグループとの交流も深いので教授の自宅まで招かれ自慢のウォシュレットのトイレを見せてもらいました。
会議中に見学したCMUロボティクス研究所は金出教授という日本人が所長をしています。池内教授もコンピュータサイエンスとこことを併任していて日本からの客員研究員も多数います。この研究所はロボットの研究グループとしては規模は世界一でしょう。研究分野はロボット関係全部に渡っていますし、月面探査ロボット、宇宙ステーション用ロボット、自動走行車などのシステムから、ロボットビジョン用の専用装置、チップの開発まで本当に色々やっています。自動走行車などは車メーカとタイアップして9?%以上(正確な数字は忘れました)自動でアメリカ大陸横断中などと宣伝していました。もっともアメリカのハイウェイならオートクルーズと簡単な操舵のみで十分なので、できない話しではないと思いました。
会議後のMITでは、AIラボ、機械工学科ロボット関係研究室、 メディアラボ、と3箇所を訪問しました。 AI
ラボ、機械工学科ロボット関係研究室は大規模ではないが着実に大学的にやっているという印象を受けました。特に印象的だったのは、チーブビジョンマシンと蟻ロボット。チープビジョンマシンはAIラボで開発した安価な標準ビジョンシステムで多数の研究室で共通に使っているとのことでした。蟻ロボットは直径3cmほどのロボットでこれを学生一人で開発していると聞いて驚きました。サブサンプションアーキテクチャで有名なブルックス教授のところは移動だけではあきたらずヒューマノイドを開発していましたが、組み上がっているのはまだ首と胴だけという状態でした。我々のグループも後期は研究成果をヒューマノイドシステムとしてまとめる予定ですが開発を急げば十分に対抗できると思いました。メディアラボは、普通はMIT内部の人でもなかなか入れてもらえないと言う話しだったのですが、以前、電総研にきた学生がアレンジしてくれて学生ボランティアによる見学をしてもらうことができました。ここはロボット研究というよりはマルチメディアの研究が中心でした。金をかけてかなり計算機パワーを使った力ずくの研究という感じですがマルチメディア電子メイルのようなそれなりに面白いという印象を受けました。
以上、簡単に米国出張の報告をしました。最後に今回の出張の事務処理でお世話になった企画部の皆様、有意義な見学のセッティングをしていただいた電総研および見学を受け入れて下さった皆様に感謝致します。
注:ペンシルバニアでは成人1り当たり年間750リットルまでの個人消費のワイン作りは合法です。
|