光日立研究室
光技術と計算機の融合に向け
西村信治
(株)日立製作所中央研究所 研究員
信号を光に乗せて伝送する技術は、長距離にわたって劣化せずに高速信号を伝えられる事から伝送分野において確固たる地位を築いてます。しかし、計算機の分野はまだ未開拓な応用分野でありRWCPの光分野狙いもそこにあると理解しています。これを踏まえ私共光日立研究室では「超並列用コンピュータ用光インタコネクト技術の研究」というテーマで、巨大なネットワークである超並列計算機に光技術を応用する研究をRWCつくば研と共同で進めております。光技術を計算機内に応用する試みは様々ありますが、大きくは光情報処理と光インタコネクションに分けられます。光情報処理はホログラフィ技術等を用い光そのもので演算を行うもので、光を用いた高速な並列処理の実現が将来期待されます。これに対し光インタコネクションは、複雑な演算処理はSi-LSIに任せ、光の得意な情報伝達の部分を光で実現していこうという試みです。計算機はこの光インターコネクションによりデータ転送速度Gbps以上の高速レートで伝達可能な光のデータバスを備えることが可能となります。この光インターコネクションは接続距離に応じて、「装置間」「ボード間」「チップ間」の分野に分けられ、本RWC内でも面発光レーザやSi基板上にOEICを作る試み等さまざまな形で提案されています。このなかで、本研究室の研究はこのうち、図1に示したような「装置間」もしくは「ボード間」の分野において、超並列計算機内ボード間を光ファイバで接続した光インタコネクションを実現する試みです。私共の会社ではこのボード間光インタコネクション実現のため、レーザ素子とホトディテクタを各12個ずつモノリシック集積し、その間を12芯のリボンファイバで接続した形の光インターコネクションモジュールを研究開発しております。本モジュールは12個の各チャネルが250Mbps以上の高速スピードで伝送可能な特性を有し、全体で最大3Gbpsの大容量信号をビットパラレル、低スキュー(パラレル展開したビット信号間の到着時間差の小さいこと)な形で100mの距離にわたって送ることが可能です。本研究室の大きな研究テーマはこのモジュールをRWCつくば研が開発中の超並列計算機(RWC-1)の一部に搭載することで、「光信号で接続された初めての超並列計算機」を実現するのを目的としています。本研究のようにビットパラレルな信号伝送の場合、ビットシリアルな形にMUX/DEMUXする等の処理上のオーバーヘッドをなくせる半面、展開したビット信号間の到着時間に差が生じるいわゆる「スキュー」が新たに問題となります。今回のボード間通信においては50Mbps以上のクロックで動作する36bitの同期信号の転送を要求されるのですが、私共の研究室ではインタコモジュール4つを同期動作させる事で一切MUX/DEMUX等を加えずにダイレクトに36bit転送することを試みています。これには、アレイ集積されたレーザ等の特性の高い均質化はもちろん、駆動回路特性や多層基板内の配線長のばらつき等様々なスキュー要因を制御、抑圧する技術が必要となります。本研究ではこれら諸問題をクリアし、同一基板内に計算装置と光送受信器を高密度実装することにより、スキュー管理要求の厳しい計算機内のビットパラレル通信において、長距離/高速な信号伝送の可能な光技術の特性を明確に実証することができると考えています。叉同時に、軽量な光ファイバを用いたことにより装置組立の容易にし、長距離の電気信号配線をLSIで駆動する際のドライブの負荷やピン数増加に伴うピンネックに対しても一つの解を提供し、延いては計算機アーキテクチャ自体にもインパクトを与えることを期待してます。本研究室では、この実際の計算機ボードに光部品を搭載する試みと平行し、将来必要とされるより高速かつ高効率な光インタコネクション技術に不可欠な技術として、高効率レーザ用の材料デバイス研究等も本年度より着手いたしました。これら研究の進展により、より高速大容量な光インタコネクションを具体的な形で実証すべく研究を進めており、全体としてRWCプロジェクトの標榜する、「柔らかな情報処理システムの確立」に寄与できればと考えています。
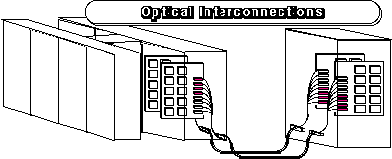
図1 ボード間光インタコネクションのイメージ図
|