RWC News 第3号 巻頭言
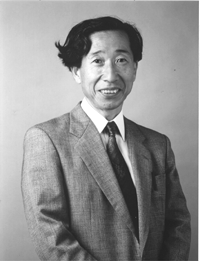 |
「RWC研究者に期待する」
東京大学工学部計数工学科 教授
甘 利 俊 一
|
古来、人々は自然の仕組みに畏怖すると共にこれに大いなる興味を抱いてきた。この仕組みを利用し工夫を加えると、物事が驚くほどうまく働らく。これが技術の、そして科学の始まりであろう。文明が進み、機械文明時代に入るにつれ、このようなことを専業とする人達が現われてくる。科学者であり技術者である。こうした研究者は一匹狼的な存在であり、自分自身のアイディアと腕前とを世に問う勝負師であった。しかるに、科学・技術が高度に発展するにつれ研究もまた高度に組織化されてきた。いまや科学は巨大化し国家的威信をかけてのプロジェクトとなり、技術は企業の飛躍と生き残りをかけた死闘の鍵を握るとまでいわれている。この中で研究者の存在が問われている。
これまで、日本では組織的な研究活動により手堅く技術開発を進め、技術の先頭に踊り出るのが得意といわれた。これが日本人の独創性の欠如に通じるというのだが、私はそうは思わない。遡れば、江戸時代の「カラクリ」ものに見られるように、我々は工夫発明、そして独創的なアイディアをじっくりと考えるのは好きだった筈である。それが追いつき追い越せの技術開発の体制の中では十分に発揮できなかっただけなのかもしれない。情報科学やソフトウェア開発での遅れがこれを如実に物語っている。
人間に学びこれと共生する技術を求めて、従来の枠を越えた研究体制でRWCはスタートした。10年後の目標を固定せず自己組織的に構築していくことを含めて、ここでは研究者が思いきり腕を奮える場が与えられる。しかし場を与えれば中味が自動的にできるわけではない。ここでこそ研究者の独創性、思想性、実行力がためされる。自由の場にでて眩暈がして方向を失っては困るのである。
個人の独創性を十分に発揮するには、優れた指導者の構想力と指導力、さらには研究者の側の``思い込み''が必要である。自分の信念といってもよい。しかし、閉じた思い込みは危険である。大きな体制の中で自由な交流を通じて思い込みを点検し修正し、発展させていかなければいけない。このためには、思い込んでいる自分を冷静に見つめているもう一人の自分が必要なのだと思う。
RWCは時限付のプロジェクトである。新しい構想が生きるか否かはこれにたずさわる研究者の1人1人にかかっている。固定した目標の中の歯車の一つとなって無事に力を出していくのではなく、野武士の如く芸人の如く、自分のアイディアを全体の構想の中で大きく発揮させていければ素晴らしいのである。これこそ技術者の夢の復権である。もとよりこれはきわめて困難なことである。しかし、終わってから力いっぱいやりとげたという満足感、情報技術の歴史の一つを担ったという満足感が残ること、さらに終了した後も雲散霧消することのない研究者どうしの連体感が国際的に残ること、こういった研究者が輩出することをこのプロジェクトに期待したい。
|