最近の研究活動状況
光沖研究室
(光配線+LSI = Si-based OEIC)
上條健
(沖電気工業株式会社 半導体技術研究所 光沖研究室 室長)
光技術とコンピューティングはどうすれば蜜月を迎えることができるのか?「光技術とコンピューティングの新しい関係」この命題に正面から取り組むのがRWCPにおける光コンピューティング研究分野の課題との考え方から光配線のSi-LSIへのアプローチを展開しているのが、我々光沖研究室です。
コンピューティングにおける超並列化の流れなどの新たな潮流の中で、ボード間、MCM(Multi-Chip
Module)内などSi-LSIを取り巻くハードウエアにおける配線ネック問題が顕在化していることから、光配線に大きな期待が生まれてきています。Si-LSI技術は、様々なシステムをチップ上に形成できる技術を提供することでコンピュータハードウエアの発展を牽引してきました。このハードウエアに光配線技術を利用しようとするならば、光技術をSi-LSI中心のハードウエアに融合し、Si-LSIと一緒にチップ上にシステムを形成できることが必要である思われます。
図1は、我々が開発しようとしている新しいタイプの集積回路のイメージです。光技術の立場から見れば、これは”OEIC(Optoelectronic
Integrated
Circuit:光電子集積回路)”といえますが、Si-LSIの入出力部が光配線機能で置き換えられているとみても差し支えないものです。この集積回路は,
OEICからみればSiベースの集積デバイスとして、Si-LSIからみれば化合物半導体デバイスの集積をともなう光配線機能付LSIとしての新規性を持つことになり、両者の立場から新規技術の開発が検討される立場にあります。我々は、この集積回路を異種の材料系で構成することから”Multi-Material
OEIC”と呼んでいます。もし、このような集積回路を作製できる技術を開発できれば、従来材料選択性により制限されていた集積回路アーキテクチャの壁を取り除くことができるといったインパクトももたらすと考えられます。
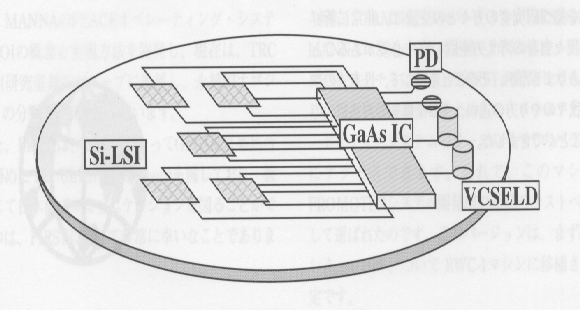
Multi-Material OEIC誕生へ
如何にしてこの集積回路を作製するのかというのが目下のところの研究課題です。この場合、光配線光源としてはInP系半導体で構成される1.3 あるいは1.5
μm帯の半導体レーザです。一方、受光器はこの波長に対応するInGaAs系のフォトダイオードが採用されます。この波長域を選択する理由は、Siに透明な波長域を採用するためです。それは、光学実装を必要とする光配線においては、平坦なSi基板の裏面から光を入出力することが有利となるからです。この結果、半導体レーザは、面発光レーザ構造が最終的に用いられることになります。この構成は、将来、配線密度を向上させる場合、並列光配線を2次元構造で実現できるとという発展性も期待できます。このため光デバイスは半田などの光を遮る物質を介在させて集積できないという状況にあります。そこで、当面の研究課題は「如何にして化合物半導体デバイスである光デバイスをSi-LSIに集積するか?」であり、以下に研究の状況を紹介します。従来、Si基板上に化合物半導体デバイスを形成するための技術としては、”エピタキシャル成長”と呼ばれる薄膜結晶をSi基板上に堆積させる技術をを中心に研究が進められてきました。しかし、Si-LSIの一部の空間に、Si-LSI形成後に光配線デバイスを形成しようとした場合、エピタキシャル成長は700℃程度の高温プロセスであることや空間的な一部に再成長を含む複数のステップの成長が必要なこと、成長した化合物半導体に高密度の転位を発生することなどから困難な手法と考えられています。さらに、複数の材料系を集積しようとするならば、プロセスはさらに複雑になります。この問題を解決するために我々は、異種基板の”直接ボンディング”という手段を採用すべく開発を進めています。この手法は、従来Si-SiあるいはSi-SiO2の構造を形成するために開発されていた手法を化合物半導体に拡張するものです。この手法を採用した場合、予め化合物基板上に形成したデバイス構造を有する積層エピタキシャル構造をSi-LSIの一部に直接ボンディングし、その後従来のデバイスプロセスの手法でデバイス化しようとするものです。この結果、光学的アライメントを含め位置精度はフォトリソグラフィで決定されるため、微細な配置が期待できます。一方、異なった材料系のデバイスを空間的に配置することも比較的容易にできるという利点もあります。直接ボンディングプロセスに課せられる要件としては、1)Si-LSIを劣化させないプロセスであること、2)直接ボンディングした材料が格子欠陥を生成するなどして劣化しないことなどが上げられます。既にこれまでの研究で、Si基板上にInPを直接ボンディングする手法を開発してきました。特に、94年度の研究においては、直接ボンディングプロセスの低温化に成功し、400℃のInP-Siの直接ボンディングで十分なボンディング強度が得られることを示しました。この低温化は、先に挙げた直接ボンディングプロセスの要件に関わって、Si-LSIの劣化温度の上限を決定するLSI内Al系配線の劣化温度(~450℃)を下回るもので、Si-LSIプロセスとの整合性を実現したものです。このような結果をさらに進展させるべく、現在半導体レーザのSi基板上への集積化について検討しています。最近、InGaAsP/InP半導体レーザの直接ボンディングに成功し、室温連続発振に成功しています。この結果、直接ボンディングによりSi基板上に形成した素子が通常のInP基板上の素子と遜色ない性能を示すことが明らかになり、この手法の有効性が実証されたと言えます。今後は、Si-LSIへの集積化、面発光レーザへの集積化などの実証について研究を進めて行きたいと考えています。当研究室では、チップ間の光配線を実現する光学実装の研究も進めており、光配線がコンピューティングにおいてシステムの一部として親和する技術となることを目指しております。さらに、光配線技術が新たなコンピューティングアーキテクチャの実現を刺激する技術となること、そしてRWCプロジェクトから光配線を使った新しい技術の芽が生まれることを期待しています。
本研究について、ご意見、ご質問、議論をお寄せください。(kamijoh@hlabs. oki. co.jp)
|