RWC研究開発の動向(現状と展望)
電子技術総合研究所
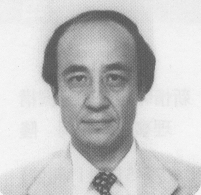
知能情報部長 大津展之
はじめに
RWC計画の研究開発が始まり、早3年近くになろうとしています。推進者の一員として、当初の計画の理念に照らして研究開発動向を見つめるとともに、現状における課題、周辺状況、そして今後の展望についての考え(感じる所)を述べさせて頂きます。
当初計画における理念と体制
RWC計画は、海外を含めて延べ100人にも及ぶ有識者による「新情報処理技術調査委員会」(2年)での熱心な議論と、「フィージビリティー調査」(1年)での基本計画書の策定を経て、スタートしました。その基本理念:
Real World Computing
は、21世紀の高度情報化社会における情報処理技術の新たな地平を切り拓くべく、そこでのニーズと課題を深く分析し突き詰めることにより、実世界の多種多様な情報を処理できる人に近い柔軟な知的情報処理、いわば「柔らかな情報処理」の実現を目指して設定されています。
RWCは、新しい情報処理パラダイムとしての、実世界性と柔軟性へのチャレンジであり、その研究への要請条件と評価基準となる3つの座標は、「開放性」、「曖昧性」、「実時間性」への対処です。このための基本となる新機能として、「多様な情報の統合」と「学習・自己組織化」の機能があげられています。これらの基礎としては、これまでの想定世界での記号を主体とした「集約逐次手順型情報処理」に対して、実世界でのパターンを主体とした「分散並列学習型情報処理」の追及が重要であり、後者の理論的な原理の究明と、技術的な実証および応用に関する真に先端的・独創的な研究が求められています。
このような野心的かつ先導的な研究開発を押し進めるための新しいプロジェクト体制として、初めて海外を含めた国際化と大学を含めた学際化が開かれています。また、委託先のRWCP(技術研究組合:新情報処理開発機構)においても、各分散研における、より要素的な研究開発とTRC(筑波研究センタ)における、より集中的な研究開発との有機的な連携、そして前半での比較的広く探索的なフェーズから、中間評価と見直しを経て、後半でのより集約的なフェーズへといった、評価に基づく「分散と協調」やGA的なダイナミクスが採用されています。
さらに、RWCPを横から支える形で、電総研も、少ない予算ながら、10テーマ延べ
60名の大部隊でRWCの先導的研究を行なっております。当方も、電総研でのRWCの核となるコンセプトの深化と研究の芽を育てることが全体の研究開発の推進に急務であるとの認識から、この4月からは、TRCの首席研究員の兼任を辞して、これに専念しております。
研究開発の現状と課題
このような21世紀の新しい情報処理への独創的基盤を目指したRWC計画の進展、特に前半における進展は、既存コンセプトのハードウェア化を主体とした従来の開発型プロジェクトの観点からすれば、遅々としてバラけた感じを与えるかも知れません。しかし、真に新しい独創的なコンセプトとそれに基づく技術の醸成には、それなりの時間が必要であり、いったん核が創生されると、一気に様々な場面に新規の応用技術が育って行くといった性質のものであるとの認識も必要でしょう。あまり成果を急ぐと、小じんまりとしたアイデアとあまりインパクトの無い研究の寄せ集めとなって、基盤体系が育たない結果にもなります。かと言って、各自バラバラにのんびりやっていると、すぐに10年は過ぎてしまいます。要は、明確な共通の理念と問題意識を持って、それぞれの分野の研究のペースを尊重しつつ、しかし相互の接触面積(触発機会)は最大限確保しつつ、研究開発を活性化することであると思われます。
このような観点からRWC研究開発の現状を見つめてみますと、いくつかの成果の芽が既に出始めているとも言えますし、またいくつかの解決すべき課題も見えてくるように思います。以下、その内のいくつかについて、思い付くままに言及したいと思います。
柔らかな情報処理の計算基盤をなす超並列システムの研究開発では、汎用プラットフォームマシンとしてのRWC-1の開発が進み、来年に完成の予定です。また、そのOSや、
C++を拡張した並列オブジェクト指向言語のソフトの開発も、国際標準化を意識しつつ進んでいます。一方で、マスタープランにあったもう一つの新しい超並列システムとしてのニューラルアーキテクチャの研究開発が、諸般の事情や予算の制約のため、蔭に隠れて不調なのは残念な気がします。
汎用超並列システムは、新機能の研究との接触において、いかにこれを支える新規性(RWCらしさ)を出せるかが課題と思われます。また、これらを通して、後期では、進展してくるでろうニューロや進化関連の研究から、真にRWCらしい新しいアーキテクチャを追及する方向も重要と思われます。
光の研究開発は、TRCに集中研が無く、また米国との協定(JOP)もあって、立ち上がりが遅れ、現在のところ分散研ベースで基礎的な研究が行なわれているように思われます。しかし光インターコネクションの研究開発は、RWC-1への実装を目標に、前倒しの形で加速されています。ただし、それだけでは寂しい気もいたします。その反面において、並列性と実時間性を生かしたRWCらしい光コンピューティングの新規性のある研究や、新機能への直接の接点(特に画像の初期処理)を求めた研究の芽が減速されないことが、課題かと思われます。
理論・新機能の分野は、結局はRWC計画の中心となる研究開発であり、最終的には理論の成果と新機能の要素技術が統合され、TRCを中心に新しい情報処理システムとして具体的に示されることが要求されていると思います。現在、TRC、内外の分散研や再委託先、電総研、さらには各種のワークショップでの議論において、様々な形で推進されています。少しづつ核となる芽やグループ化の傾向が出始めているように思われます。例えば、マスタープランにある2つの機能統合方向としての、マルチモーダルなマンマシン対話、そして実世界環境における自律学習ロボットの線が出てきています。
ただし、未だ他との関連が見えない孤立した要素課題の研究や、従来の手法の単なる延長と思われる研究も混じっているのも事実です(特に画像処理など、いわゆる要素的なパターン認識をゴールに設定し、そのサブ課題をゴールとした研究)。また、理念の不徹底や、応用の貧困(実世界問題が少ない)も見受けられます。
今後の課題としては、より実際的なRWCらしい応用場面を想定した展開、例えば、マンマシン対話では、ネットワーク情報環境を想定した各種の意志決定支援や情報サービス、また自律学習ロボットでは、意義のある各種行動の代行や人との対話と協調の方向が摸索されるべきと思われます。もっとも、それらの核はいくつか出始めていて、それらを他の要素研究とうまくコーディネートして、連携の強化をはかることが重要だと思われます。
電総研においても、これらの2つの機能統合の方向を、理論を含めて総合性を生かし、連携の強化を図りつつ追及しております(WWW参照)。また、これらに関連して、共通となる並列計算の新しいアーキテクチャ(例えばイベント駆動型の言語や進化するハードウェア)や、RWCらしい共通的な確率統計手法や最適化手法をパッケージとしてライブラリー化する動きが出てきていております。
さらに、せっかく企業が参加しているRWCPですから、並列計算に基づく大規模最適化の実世界問題、例えば交通、流通、電力、各種プラント等の系統的な最適制御問題なども、ニューロやGA等の最適化手法の本格的な研究課題として、追及されることが期待されます。
研究開発強化に向けての展望
ここで、これらの課題の解決、そしてRWC研究開発の強化に向けて、少し展望してみたいと思います。
理念の徹底
まず、当初のRWCの理念のさらなる徹底が必要に思われます。現在、TRCを中心に、RWC計画を情報統合論のメッカにすべく、ワークショップの開催(今年4月)など、活動がなされております。これは、理念の徹底と連携の強化の意味で大変良いことだと思います。
「情報統合」には、垂直と水平の2つの側面があります。垂直的な「パターンと記号の(情報)統合」は、昔からパターン情報処理と人工知能研究との間のギャップに位置する重要な課題であり、これまでいろいろと議論されてきた難しい大問題です。パターンと記号という2元論的な議論は、収束しない形而上学的な議論に陥り、安易な妥協に基づくこれらの統合アルゴリズムは、これまでの研究でもあまり実りある成果となっていません。
一方、水平的な情報統合としての「マルチメディア情報の統合」があります。これまでメディア毎に個別に研究が行なわれてきた画像や音声など(自然言語は記号的で垂直的だが、パターンとして)の認識・理解の問題を、より高次の総合的理解や判断のために、また対話における意図の理解や表現のモードとして統合する研究で、最近盛んになっております。ただしこれも、突き詰めるとメディア表現の背後の意味の問題に至る本質的な課題を含んでいて、安易な(従来の手続き的な)技法による単に曖昧性解消(
disambiguation)のための異なるメディア情報の相補的な利用ではすまない問題です。
これらの情報統合は、実世界の認識と総合的な判断に係わる問題であり、パターン認識の理論的枠組みからのより深い考察が必要であり、情報表現、とりわけパターンと記号の中間表現(しかも普遍的な表現)としての特徴表現が重要だと思います。そして、これらの表現を(の間を)より自由に統合(連合・連想)する枠組みに関する、理論的かつ計算論的な原理の究明とモデル化を含めた深い研究が必要です。
さらに言えば、情報統合論だけでは偏りが生じ、従来のパターン認識の研究に安易に流れる危険性があると私は思います。「情報統合」が主に「曖昧性」への対処とすれば、「学習・自己組織化」は主に「開放性」への対処として重要なもう1つの基本機能です。これも合わせて研究することが重要です。むしろ開放性への対処こそが、生体における生きた情報処理の根源的な柔らかさとも言え、RWCの中心をなすべき新機能とも言えるかも知れません。実は、この観点が無くしては、真の情報統合や機能統合の在り方も議論できないように思うのです。情報統合を含めて、生体の持つ柔軟な情報処理や知能は、進化の過程において、実世界のもつ開放性に対処すべく自らのシステムの開放性として、学習と自己組織機能によって獲得されたものだと考えられるからです。
このように、情報統合や機能統合の機能は、学習・自己組織化の機能と密接に関係していて、それらはボトムアップに与えられるというよりも、より上位の「評価と最適化」の枠組みからの帰結としてトップダウンに導かれるべきもののように思えます。RWCの理論と新機能の研究開発においては、処理や統合の在り方それ自体を対象とするメタレベルの処理としての「評価と最適化」の枠組みの研究が重要だし、そのための方式としても、また不完全さや不確かさを伴なう実世界情報への対処として、GAを含めた確率統計的な定式化と手法の強化が望まれます。
さらに言えば、情報表現の統合と表現間の対応関係の学習を含めて、確率的推論としてのベイズ推定や、リスクや効用の評価を加えた最適化としてのベイズ決定理論の枠組みが重要であり、そこから情報統合や機能統合も出てくるのだと私は思います。この観点こそが、RWCの研究開発をまとめる真のポイントであり求心力となるものと思っております。それなくしては、従来の個別手法の延長や個別のアルゴリズムにバラけて、新しい情報処理の基盤体系と成りにくく、「柔らかな情報処理」の真の柔らかさや機能の新規性も出てこないのではないかと思っております。
連携の強化
次に、連携の強化です。いくつか研究の芽が出てきておりますが、それらを含め、いくつかの関連の強い研究をグループ化し(出来れば産官学三位一体で)、それらの内部(intra)と間(inter)の相互作用を早急に強化する必要があると思います。その際、ボトムアップに手元の技術から可能な応用をイメージするだけでなく、同時に研究開発の現状を踏まえてトップダウンに、応用として真に新規性を必要とするRWCらしい本格的な実世界問題をいくつか設定し、それらの課題をブレークダウンして、研究開発の技術マップと時間的なマイルストーンを明確にし、グループの位置づけ(張り付け)、補強、そして相互の共同研究の強化を図ることも重要だと思います。
そのためには、現在の数多いワークショップの見直しと再編も必要でしょうし、産官学の役割も含めた体制の検討もしていく必要があると思います。
電総研では、先導的研究推進の役割の強化、成果を見える形にして行く努力が望まれますし、TRC始め、RWCPの国内外の分散研や再委託先との研究交流を強化していく覚悟です。
また、TRCには、後期に向けて、単に分散研に類する研究ではなく、全体で行なわれている研究をうまく取りまとめ、典型的なRWCシステムとして示す方向への観点に立って、より統合的・実証的研究を進める体制への転換を期待したいと思います。
さらに、連携強化の研究インフラとして、理論・新機能や超並列システムの研究開発のベンチマークテストのための各種の実世界データや自然言語コーパスなどの大規模共用データの整備、そして共用コンピューティング環境(例えば電総研のロボットシミュレーター:MARS)の整備や、共通手法のライブラリー化と共用化が必要と思います。また、それぞれの成果を見える形(FTP)で整備し、情報ネットワークとして共有するための整備や、グループ内/間の連携強化のためのネットワークを利用したニュースグループや討論の場の整備も必要です。既に、いくつか動き初めていますが、TRCの役割の一環として、さらに大いに推進して頂きたいと思います。
周辺状況
最後にRWCを取り巻く周辺状況を見てみますと、RWCの立ち上がり後、国内的にはバブルがはじけて経済の衰退と産業の空洞化が懸念され、日本の企業も今一つ元気が出ない状況があります。一方、世界に目をやれば、米国の情報ハイウェー構想に代表されるように、堅実な情報インフラ整備の上に経済活動を活性化させようとする動きがあります。通産政策も難しい局面を迎え、これまでのcatch-up型の産業政策から脱却し中長期的な視点からの独創的技術の醸成の必要性を認めるものの、その糸口がなかなか見えない苛立ちと、一方で上記の情報インフラへの反省回帰との間で揺れていて、ややもするとRWCへの厳しい見直し論がなされています。
しかし、海外の先端研究の動向は、一方ではしっかりと、むしろ我々の言う柔らかな情報処理の流れが強くなっているのも見落とせない事実です。例えば、ニューラルネットおけるEMアルゴリズムなどの統計理論的な展開や、GA、AL、ECなどの生体にinspireされた研究の活発化です。こうした先端の基礎的な研究が、結局は先での新しい情報産業の育成の源になっているという、これまでの図式をしっかりと見つめて、全体の産業政策を整理する中で、先端基盤研究としてのRWCの位置づけをしっかりとすべきと思われます。
本来、RWCは、情報インフラ整備後のネットワーク情報主導社会を想定し、そこで必要とされる新しい知的情報処理の基盤を狙うものであり、けっして前者の推進と無縁の物ではなく、密接に関連しているのです。ネットワークに分散する情報の爆発的増大と質の多様化、いわば実世界化の状況と、これを容易に利用したい人との間にあって、両者を仲介する新しい情報システムの在り方、新しい応用分野の創生、ひいては新規産業の創生にも、深く係わっているのです。この観点から、情報インフラと情報スープラをきちんと区別した議論の中で、ニーズとシーズの擦り合わせ作業も必要となると思われます。本来、もっと世界に向けて発信し、一体となって、この流れの先端研究としてRWCを強力に押し進める必要性があると思われます。
おわりに
以上、思いつくまま、かなり勝手なことを述べましたが、要は、RWC計画にとって今もっとも大切なのは、有機的連携の強化と後期に向けての見直しだと思います。そして海外研究動向との接触、理念と成果の積極的な発信が望まれます。
今日、巷で取りざたされている情報インフラとしての「マルチメディア」や「ネットワーク」の進展は必然であり、その上に加速度的に創出される情報の多様化と流動化、いわば実世界化の流れにおいて、RWCの狙う新たな情報処理パラダイムの必要性が真に認識されるのは、それほど先のことではないと思われます。そのような情報技術の流れを意識し、より明確なイメージを持って、そして自信を持って、皆様と共にRWC計画を推進して行きたいと考えております。
|