松岡 浩司
TRC超並列アーキテクチャ研究室
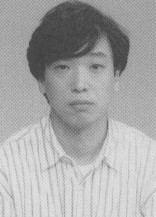
プロフィール
- 生年月日:1961年8月13日
- 出身地:高知県
- 略歴:
- 1984年東京工業大学工学部電気電子工学科卒業
- 1986年同大学院理工学研究科修了
- 同年日本電気(株)入社
- 1992年(技組)新情報処理開発機構に出向
- 趣味: ファミコン、ゴルフ
こんちにちは、超並列アーキテクチャ研究室の松岡と申します。文章で自己紹介をする機会など生まれてこのかた一度も無かったので、何を書いて良いか非常に悩みました。が、それはそれ、ハード屋さんと言うことで、いきなり真面目にお仕事の話しをしたいと思います。
我々、超並列アーキテクチャ研究室では、新しい理論に基づく次世代の情報処理を担う汎用超並列計算機の研究開発を進めています。この超並列計算機の特徴は、一言で言って、従来の計算機では効率良く扱えなかった問題を効率良く扱うことができるという点にあります。ちょっと抽象的ですね。と言うわけで、数値計算を例に技術的な観点からその特徴を簡単に整理してみましょう。
数値計算の基幹をなす技術として行列積の計算を挙げることができます。行列積の計算は、例えば、航空機の設計に用いる数値シミュレーションなどに多用されています。この行列積の計算では、解行列の各要素は、掛け合わせる2つの行列の対応する行と列の各要素の積の総和として求められます。で、この計算には、特筆すべき性質があります。解行列の各要素の計算は独立して行なうことができるため、行列積の計算は非常に並列性に富み、ほとんどどのような構造の並列計算機において効率的に実行することができます。また、解行列の要素の積和計算は連続して実行されるので、i番目の計算を行なう時点で、j番目の計算に要するデータが必要になるタイミングを予測することができます。データがどの時点で必要になるかがあらかじめ判るわけですから、計算に前もってデータを取り寄せることによって、処理を高速化することが可能です。数値計算に関して素人の私がこのようなことを言うのは僭越だと思うのですが、1つの捉え方をすれば、このような複雑なプログラミングを行なうことなく高速化できる問題のみが、従来、並列(化できる)問題として扱われてきたと言っても過言ではないでしょう。
もちろん、このような行列積の計算だけが効率良く実行できても、超並列計算機としては不十分であることは言うまでもありません。しかし、ものごと簡単にはいかないのが世の常で、扱うデータの構造が複雑になればなるほど、データを必要とするタイミングを予測することが難しく、計算を高速化することが非常に困難なものとなっていきます。我々が研究開発を進めている超並列計算機では、独自の技術で計算に必要とするデータを得るために要する時間をできるだけ短くすることによって、このような問題点を回避しています。
ハードウェア開発の担当者として超並列計算機の実現に全力を尽くす所存ですが、一方、我々が開発する超並列計算機によって、従来の並列計算機上では扱われことがなかった問題が研究対象となり、いろいろな並列処理の可能性が見い出されることを願ってやみません。
|