能動知能研究室
末廣尚士(研究室長)
能動知能研究室では、新しい情報処理技術の応用面からの切り口として、実世界に適応して自律的に行動できるシステム、いわゆる柔らかなロボットの研究・開発を行っています。私たちは実世界の典型として人間がいる環境を想定し「人間と共存するロボット」をキャッチフレーズとして研究に取り組んでいます。本稿では、そのような柔らかなロボットの手として人間の手と同じようにいろいろな形状や柔らかな物体を扱ったり、道具を使ったりすることのできる指を持った手を目指して研究・開発を進めている多指ハンドを紹介します。
現在までにも産業用ロボットの手としては様々なものが工夫されてきています。それらは一見非常に巧みに物体を操作しますし、中には豆腐のような柔らかいものを掴んだりすることができるものもあります。しかし、多くの場合それらは1つの作業しか行いませんし、基本的な動作は、開く、閉じるだけの1つの関節の自由度しかありません。そのような手では人間が日常の生活で扱っている物体や道具を巧みに扱うことは非常に難しいものになります。そこで人間と同じように多くの自由度を持った指を複数備えた多指ハンドの研究がいろいろな研究所で行われています。本研究室の多指ハンドの金物本体は、(株)安川電機製で指1本当たり3自由度、4本指で合う12自由度の独立に動かすことができる関節を持っています(写真1)。各関節には関節角エンコーダとハーモニックドライブのギアを組み込んだ小型、高出力のACサーボモータを直接配置しています。また、それぞれの指先には、3方向からの力を検出することのできる力センサが取り付けられています。この指に1つの動作をさせる時には12関節を同時に制御しなくてはなりません。これを関節1つ1つのレベルで制御しようとすると、そのようなプログラムを書くことが非常に難しくなります。ところが、人間は自分の手を使って物を操るときに指の関節1つ1つの動きを意識することはありません。同様に多くの自由度と多くのセンサを持つロボットの指にも関節1つ1つを意識することなく巧みな動作を行わせることができないだろうかというのが1つの課題となります。これに対する我々のアプローチ手法は、簡単には以下のようにまとめることができます。
- スキルによる作業構造の分解
ロボットが行う作業はそれぞれ独自の構造を持っています。ここで言うスキルとは、人間が名前を付けることができるがその動作自体を言葉で表現するのは難しいという粒度の動作単位です。これは丁度、新情報テーマの1つであるパターンとシンボルの橋渡し的な階層になります。この階層を導入することにより人間によるプログラミングをはじめとして計算機による動作計画や学習も容易になります。
- マルチエージェントによる制御
スキル動作を調べてみると、いくつかの異なるセンサフィードバック動作モードをセンサ自称により切り替えていくというのがその基本的な内部構造になります。そのような動作モードや事象検出をエージェントとしてそれらを柔軟に組み合わせることによって様々なスキル動作を実現することができ、柔軟なロボットシステムが構築されます。
- 人真似に基づく学習
上のアプローチでもロボットの動作をあらかじめすべてプログラムしておくことは難しいし、実際に動作してみなくては上手くいくかどうか分からない部分もあります。そこでその様な動作を人間の動作を観察し、またそれを実行しながら学習させることを考えています。現在は、トランスピュータネットワーク上でマルチエージェント間の柔軟な通信を可能にする機構を開発して実装しているところです。今後はいくつかのスキルを手書きで開発する過程でキーになるセンサ事象や制御法を抽出しそれに基づいて人真似に基づく学習の手法を開発していく予定です。以上のアプローチは、ここで述べた多指ハンドだけではなく能動知能研究室のロボットシステム全体に適用されており、人間と共存することのできる柔軟なロボットシステムを構築するための核となる手法であり、柔らかな情報処理技術への1つのブレークスルーとなるのではないかと期待されています。
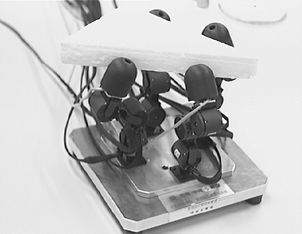
|