RWCをとりまく最近の状況

通商産業省機械情報産業局
電子機器課 松原浩司
RWC研究計画と経緯
21世紀に向けて我が国が世界の国々と取り組むべき新しい情報処理技術体系について検討を行うために、「新情報処理技術調査研究委員会」が組織されたのが1989年のことです。同委員会では、3つの分科会(基礎研究分科会、計算機科学分科会、社会応用分科会)を設けて2年間にわたり熱心な議論と、海外研究動向調査や国際ワークショップシンポジウムなどの開催を通じて検討を重ねた結果、「柔らかな情報処理」、「超並列超分散情報処理」などのキーコンセプトを提唱しました。
その後、調査研究の成果をもとに1991年からは、フィージビリティ調査を行い、より具体的な研究計画書を策定しましたこ
当初「新情報処理」はNIPT(New Information Processing Technology)と呼ばれており、RWC(Real
World Computing)という基本理念が提唱されたのは、1991年秋のことでした。その後もしばらくはNIPTと RWCという呼び名が混在しており、プロジェクトが開始した1992年度から正式にRWCの呼び名が使われはじめたのです。
1992年7月にRWC計画の研究委託先である技術研究組合新情報処理開発機構が設立され、10月にはつくば研究センタ(TRC:集中研)と組合員企業内に分散研究室
(分散研)が設置されて研究がスタートしました。早いもので、その時から数えて、すでに2年半が過ぎたことになります。
内外の研究体制
1992年10月にはTRCと2つの分散研だけだったものが、現在は分散研の数は37を数えるまでに拡大しています。このほか、国内大学への再委託が33件、海外機関への再委託も5件と非常に多岐に渡る研究テーマをかかえています。
一方、電子技術総合研究所(電総研)は調査研究の段階からRWC計画に深く関わっており、プロジェクトにおいては、組合が実証的な研究を行なうのに対し、先導的研究を行なっています。
本プロジェクトの特徴の一つに、海外の研究機関が組合員や再委託先として多数研究参加している国際共同研究であることがあげられます。NIPTの時代から国際協力を唱い、広く海外からの参加を呼びかけた結果、組合設立後、まもなくドイツ国立情報処理研究所
(GMD)が組合員として参加、その後1993年5月にはシンガポール大学・システム・ソフトウエア研究所 (ISS,NUS)、オランダニューラルネットワーク協会
(SNN)、スウェーデン・コンピュータ・サイエンス研究所 (SICS)の3機関が、さらに組合員に加わりました。また、同年にはシドニー大学(オーストラリア)、RISC-LINZ
(オーストリア)、IRST(イタリア)が再委託先として研究に参加し、1994年度からは、これにマンチェスター大学(イギリス)とエルランゲンーニュルンベルク大学
(ドイツ)が加わりました。このように国際的に開かれた研究体制は非常に望ましいのですが、海外機関が参加しているだけの名目的な国際共同研究になってはなりません。
RWCPでは、昨年8月からつくば研究所にドイツ GMDから研究者が出向して研究を行うなど、具体的な人的交流を通して協力活動を展開しています。
今後、つくば研究所を中心として国内研究テーマとの間の協力関係の構築をますます進めていっていただきたいところです。
光研究プロジェクトの日米協力
米国との協力関係では、現在、日米の光エレクトロニクスプロジェクト(JOP=Joint Optoelectronics Project) が進行中です。これはNIPTの時代から、米国との協力形態について日米政府間で協議を尽くした結果であり、日米科学技術協定の政策的枠組みのもとに進められています。
本プロジェクトでは、日米双方の革新的かつ先進的な光エレクトロニクスのデバイス製造者とそのようなデバイスを用いてシステムを構築するユーザとの間の交流を促進する機構を構築します。これによって、これまで入手不可能たった研究開発段階の先進的光デバイスを購入することが可能になり、光コンピュータシステムの研究が大きく前進することに期待が寄せられます。具体的には、図1に示すように日米双方にブローカと呼ばれる仲介機関を設けます。
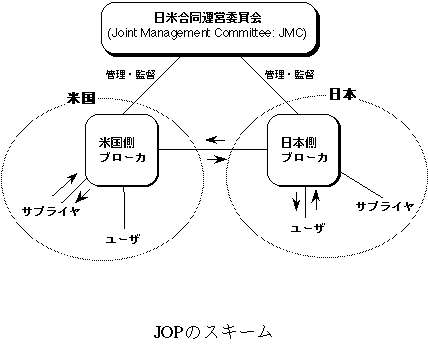
本プロジェクトについては、昨年4月に日米の合同運営委員会(JMC:Joint Management Committee)で実施計画書が策定され、6月には米国側運営委員が来日し、第2回の日米JMC会議が筑波第一ホテルで行われました。6月の来日の際には、日本側ブローカである
(財)光産業技術振興協会と米国側委員の会合も開かれ、日本側ブロー力のプロジェクト運営の方針などについての考え方を説明し、意見交換を行いました。また、関係各企業、大学の協力を待て、日本側のユーザ/サプラィヤになる可能性のある企業、大学や電総研、TRCなどの見学も併せて行われました。その後、米国標準技術研究所(NIST)によって米国側ブローカの公募が行われ、OIDA(Optoelecoonics
lndustry Development Association)が選定され、本年2月1日より活動を開始しています。

日米合同運営委員会(米国側議長Dr.French)
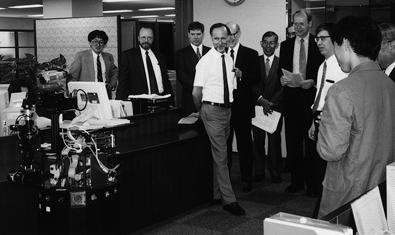
米国側JMCのつくば研究所見学
JOPは、本年2月より2年間の期限付きで行われるが、スキームがうまく働くようであれば、日米合同運営委員会で期間の延長が検討されることになつています。
プロジェクトの成功は、ユーザ/サプライヤが、どれだけプロジェクトの理念を理解し、この仕組みを利用するかにかかっています。その意味でも今後とも関係企業、大学などのご理解とご協力をお願いします。
研究インフラの整備
RWC計画では、国内外の研究機関が一体となって研究を遂行するためには相互の密接な情報交換が必要であるとの認識から、研究インフラとしてのネットワーク(RWCネットワーク)の整備を行なっています。
現在、東京NOC(Network Operating Center)を中心につくば集中研、国内外の分散研、電総研を結ぶ、図2のようなネットワークが構築されています。
平成7年3月には、11省庁の公的な研究機関を結ぶ研究情報ネットワークである省際ネットワークとの接続と、シンガポール大学・システム・サイエンス研究所へのフレームリレー接続を開始しました。5月にはオーストラリアへもネットワークを延長する予定です。
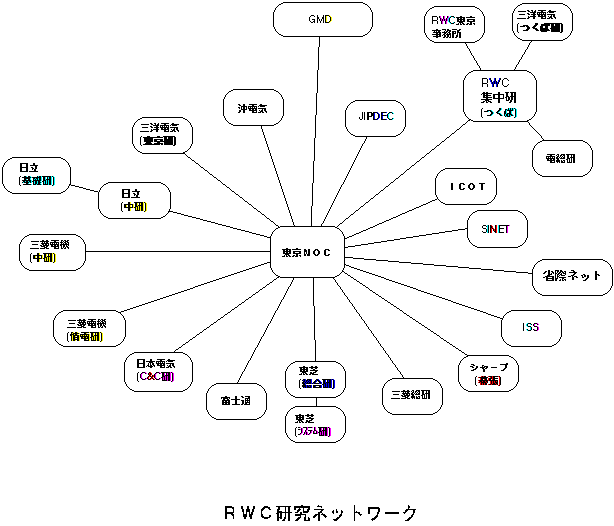
研究成果(ソフトウエア)の公開準備
第5世代コンピュータ・プロジェクトでは、(財)新世代コンピュータ技術開発機構(ICOT)が研究開発の途中で作成された有益なソフトウエアの無償公開を、1992年から行っています。
RWC計画では、ICOTでの方法に倣ってソフトウエアの無償公開を行っていく方針であり、平成7年度から無償公開に通したソフトであるかどうかを判定する委員会を開き、順次ソフトの無償公開を行っていく予定です。
RWCプログラムの現状と展開
通産省では、コンピュータシステム間の相互運用性の確立、簡易操作型電子設計・生産支援システムに関する研究開発、超高速ネットワーク・コンピュータ統合化技術の試験研究、新ソフトウエア構造化モデルの研究開発など数多くの情報化関連施策を推し進めておりますが、その中でもRWCは「第5世代コンピュータ・プロジェクト」の後継プロジェクトとして、第5世代を上回る予算総額700億円を想定した最大規模のものです。
プロジェクト開始からの予算の推移をみると、初年度(平成4年度)が約9億円から36億 -> 50億 -> 60億と順調に増加してきており、RWCプログラムへの期待の高さがうかがわれます。
10年間の研究計画において、平成8~9年度は中間評価の年です。この中間評価において、前半の研究成果をみて後半の研究テーマを絞り込むことになっています。従って、平成7年度は、中間評価に向けてRWCの研究の真価が問われる年なのです。
実りある成果があがり、国際的にも国内的にもRWCプログラムが高い評価を得られることを期待しています。
|